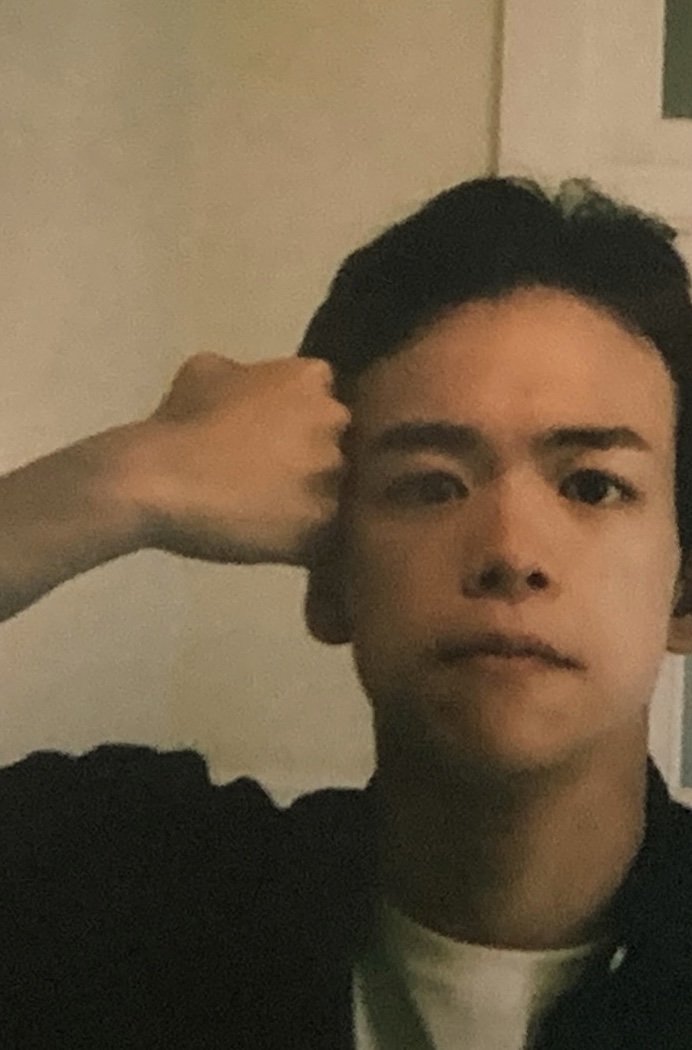毎回、勝手に〝2本立て〟形式で映画を並べてご紹介する。共通項といってもさまざまだが、本連載で作品を結びつけるのは〝ディテール〟である。ある映画を見て、無関係な作品の似ている場面を思い出す──そんな意義のないたのしさを大事にしたい。また、未知の併映作への思いがけぬ熱狂、再見がもたらす新鮮な驚きなど、2本立て特有の幸福な体験を呼び起こしたいという思惑もある。同じ上映に参加する気持ちで、ぜひ組み合わせを試していただけたらうれしい。
「ケイコ 目を澄ませて」©2022 「ケイコ 目を澄ませて」製作委員会 COMME DES CINÉMAS.
2023.2.05
日記を書くひと、読むひと、聞くひと 「ケイコ 目を澄ませて」:勝手に2本立て
2022年の冬、公開されてすぐに三宅唱監督作「ケイコ 目を澄ませて」を見て、魅了された。見たあとも、ふとした瞬間にあらゆる場面が脳裏に浮かび、記憶が連なり、気がつけば反芻(はんすう)されている。わたしは、この映画に夢中なのだ。
とはいえ、書きたいことはあまたあれど、すべてに触れてはいられない。公開から1カ月以上が経過しており、既にご覧になった方も少なくないだろう。今回は、とりわけ印象的だった点のみについて書くことにしたい。
環境音を再認識させる語りの驚き
まず、本作ではあきらかに無声映画が意識されている。むろんそれは、岸井ゆきの演じる主人公ケイコが耳の聞こえないボクサーであることによる発想だろう。しかし同時に、本作は豊かな音にあふれた映画でもある。
「目を澄ませて」と題にある通り、たしかに本作は音に頼り切ってはいない。だが、観客は主人公の耳が聞こえないと知っているがために、いつも以上に耳をそばだてることになるのだ。その結果、場所=場面が変われば、編集点を経て雑踏の音も様変わりする、といったある意味では当然な、常日ごろ聞き流していた環境音を再認識することになる。
そして、そんなわれわれを牽引(けんいん)するかのように、三浦友和演じるボクシングジムの会長は、まさに「聞く人」として現れる。であればこそ、間違いなく主要人物の一人であり開幕早々から姿を見せるにもかかわらず、彼が口を開き言葉を発するのは、想像よりもずっと遅い。

無声映画を意識した音の映画
本作はあらゆる面で突き詰められ、研ぎ澄まされていながら、同時に窮屈さを感じさせない風通しの良さがあり、それがすばらしい。無声映画を意識しながら、音の映画でもある。環境音は豊かだが、重要な音の多くは画面内で出所が明確に示されていて、「聞こえないこと」を描くにあたってきわめて誠実な配慮がなされ、過度に利用したりはしない。「聞く人」が、幾度か「しゃべる人」になるとき、あるいは終盤「見る人」として描かれるさいの感動(そしてそれをわれわれだけでなくケイコもまた目撃する)。
意図や方法に縛られず、設けた枠を絶えず更新していくような、容易には一言でくくれない逸脱の解放的瞬間が、絶えず波のように訪れる。そこがいい。たとえば、予告にも出てくるケイコと弟が手話で話をする場面。
これは、まさに無声映画を意識した中間字幕――「話してよ」「どうせ人は一人でしょ?」の部分のこと――によって表現されているが、手話の対話が必ずしもこの手法で描かれるわけではなく、画面下部に普通に字幕が表示されることもあれば、全く何も表示されないこともある。決め事をかわしながら、むしろ都度、最適なかたちに語りを変幻させるのだ。

読み上げられるケイコの日記
とりわけ感動的だったのは、予告編でもその一端が用いられている日記をめぐる場面。終盤、入院中の会長を見舞ったケイコが手にしていた日記を、妻――仙道敦子が演じる――が一時的に借り受け、後日ベッドに横たわる会長=夫へ読み上げてやる……そんな美しい場面だ。
基本的に、日記の内容は素っ気ない。日ごとの記述はそう多くないようだし、大部分が日々のトレーニングの記録である。けれど、それを読み上げる声の響きとともに、画面で移ろうケイコの日々はひたすらみずみずしく見える。それまで描かれてきた場面とは、何かが違う。それは豊かな音が排された、本作で唯一の「聞こえない」場面だからかもしれない。けれど画面にはケイコが平然と映されていて、ことさら主観性が強調されているわけでもない。
幾度も目にしたランニング、自宅の風景、姉弟のやりとり。どれも、なぜだか、やはりそれまでと違うものを目にしているような気になる。これまで見えていなかったものが見えるようになったような感触。世界の見え方が変わってゆくような新鮮さ。画面の推移を見つめていれば次第に、その多くが、それまでと違った捉えられ方で撮影されているからだと分かるだろう。位置ないし空間の差異だ。
たとえば、これまでも幾度か描かれたはずの姉弟の会話は、前もってケイコが通る姿も描かれていたマンションの外廊下で起きるのだが、それまでは姉弟が会話する場は家の中に限られていたのだし、外廊下もまた日記場面のモンタージュとは違った、距離を置いた位置から撮影されていたはずだ。
はじめての場所での会話、はじめての位置から見つめられる場所。既出の要素が、新しく提示され直す(言うまでもなく、それまでと違ったケイコの練習風景=縄跳びなど出来事単位で目新しい描写もある)。見え方が変わるという視覚的体験が、初めてケイコの心奥を聞く日記朗読による聴覚的体験と共鳴し、それを耳にしているさなかの会長=三浦友和へと結びついていく。

「ベンジャミン・バトン 数奇な人生」© Paramount Pictures Corporation and Warner Bros. Entertainment Inc
日記を読んで書き手に近づく「ベンジャミン・バトン 数奇な人生」
本作の日記をめぐる場面について考えたところ、デビッド・フィンチャー監督作「ベンジャミン・バトン 数奇な人生」(2008年)もまた、読み上げられる日記の映画だと思い出した。
老いた身体で生まれ、だんだんと若返っていく男ベンジャミン・バトンの生涯を描いた映画ではあるものの、彼ではなく、いまにも息絶えそうな初老の女性デイジーの病室から始まる。彼女は傍らの娘に「カバンに入っている日記帳を読んで聞かせてほしい」とせがむのだが、それがベンジャミンの日記なのだ。こうして、物語は朗読される日記の記述を推力に展開されていくのである。
本作も「ケイコ」と同じく、日記を読むことが書き手の人物を知ることになるという映画。朗読を聞くことでデイジーは想(おも)い人の心中にようやく近づくし、読み上げる娘もベンジャミンの視点を通して母を知る。書いている姿が映されないから、主人公ベンジャミンがいつどのように文章を書いたのかは分からないが、読み上げている娘が「日記はここで終わりみたい」と言う地点に書き手の心境がうかがえるだろう。
ここまでずっと続いてきた日記の朗読がふと途絶える終盤、残り僅かな時間で、伏せる初老女性デイジーが語りを引き継ぎ、書かれなかった続きを語る。その姿には、「聞く人」が「話す人」に転じる感動があり、三浦友和がぽつりぽつりとぎこちなく話す姿の魅力とも重なるかもしれない。ぜひ併せて見ていただけたらうれしい。

「ベンジャミン・バトン 数奇な人生」は、U-NEXTで配信中。