マーク・カズンズ監督の「ストーリー・オブ・フィルム 111の映画旅行」は、2010~21年の12年間の、映画をめぐるドキュメンタリーだ。世界中の映画を集め、比較し考察する、映画の「今」。博覧強記、記憶力抜群のカズンズ監督に、話を聞いた。
直近の12年を総ざらえ「ストーリー・オブ・フィルム 111の映画旅行」
カズンズ監督は11年、映画史の自著を基に、映画の始まりから2010年までを網羅した英国のテレビシリーズを製作しており、今作はその続編にあたる。テレビシリーズは合計900分以上の大作で、大変な労力を費やした。二度とごめんだと思ったそうだが、コロナ禍で蟄居(ちっきょ)を余儀なくされる間にアイデアが膨らんだ。
「映画を作るのにたくさん旅をしていたのにコロナ禍でできなくなって、インキュベーションの時間だった。低予算で作るのは大変だから映画にしようとは思わなかったんだが、アイデアが魅力的で取りつかれてしまったんだ。知的で創造的な挑戦だった」
この12年の映画の変貌ぶりは、映画全史の中でも急激で大きかった。デジタル化が進み、動画配信サービスが普及した。描かれる内容も変わってきた。

技術も取り巻く環境も変わった

「技術も進歩したし、映画を取り巻く社会も大きく変わった。女性や性的マイノリティー、人種など、映画の中でこれまで欠落していたものに目が向けられている。作り手も、映画が届ける声も多様化して、これはとてもいいことだ」
「デジタル化は、映画史に埋もれた古典をよみがえらせている。成瀬巳喜男や今村昌平の映画をより手軽に見られるようになったし、田中絹代をフェミニスト的な視点から捉え直すことも進んでいる」
一方で、良くない変化も感じている。「ビジネスの映画支配が強まった。1920年代、60年代の映画黄金期には、商業性はずっと薄かった。大衆映画は好きだが、商業化されすぎるのも不健康だと思う」
動画配信サービスを「映画好きには黄金期」と表現する。「だって、今なら松本俊夫の『薔薇の葬列』を、見たいと思ったら1分で見始められるのだから」。「薔薇の葬列」は、69年に作られた松本俊夫監督の前衛的なカルト映画。日本映画にも精通しているだけあって、あげる作品もマニアック。もっとも「自分では配信はほとんど見ない」そうだ。「映画監督は支配するものだから、スクリーンの光の中で、より大きなものにのみ込まれて振り回されたいからね」
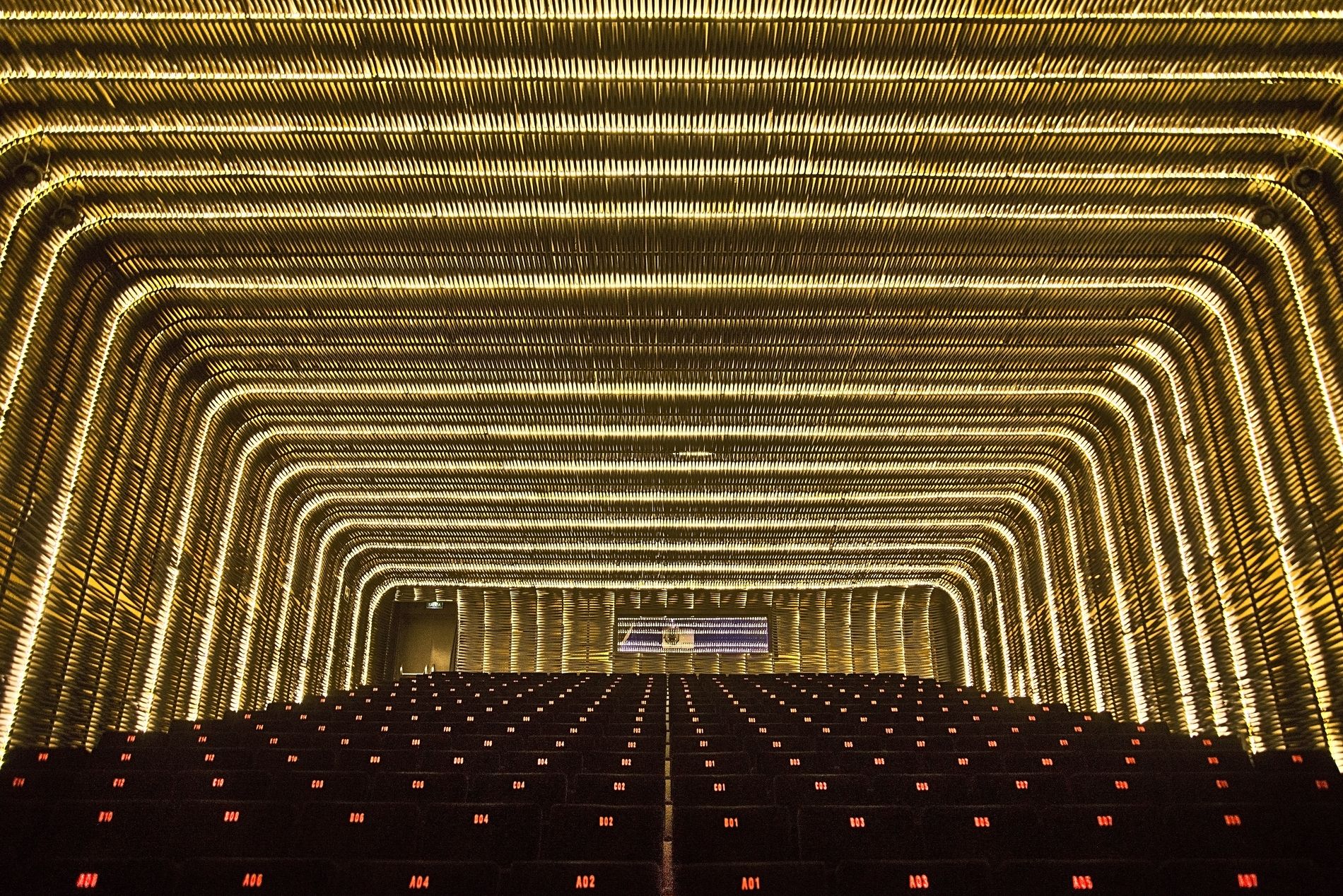
絵画や美術のように、子どもたちに教えるべきだ
これまでにも、さまざまな切り口で映画史についてのドキュメンタリーを作ってきた。映画に関する知識と見方を示してくれる。
「詩や絵画、音楽のように映画も、子どもたちに教えるべきだと思う。教室の講義ばかりが教育ではないし、自分の作品は映画愛を伝えるツールのつもり。映画への知識欲をそそり、啓発にもつながる。今作はアフリカ、アラブ、南米まで網羅していて視野を広げるし、たくさんの種をまくことになる。映画の地平を拡大したい」
「日本映画も大好き」と、取材中も手元の「ゆきゆきて神軍」(87年、原一男監督)、「神々の深き欲望」(68年、今村昌平監督)のDVDを見せてくれた。しかし、今作で引用した日本映画は「万引き家族」(2018年、是枝裕和監督)だけ。

日本映画好きが高じて、腕に「田中絹代」の入れ墨が
「鬼滅の刃」は幻覚体験のよう
「そこは申し訳なく思っている。日本映画も良い作品はたくさんある。他の時代にはもっといいものがあったかもしれないが、最近も面白い。『ドライブ・マイ・カー』は傑作で、濱口竜介監督は映画ばかりでなく映像をすごく研究しているのが分かるし、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』はドラッグ漬けになったような感じだった」
それにしても、映画の鑑賞本数と記憶力に驚かされる。「朝6時に仕事を始めて、午前中に1本、映画を見て息抜き。栄養を補給してもう半日働く。毎週40~50本は上映しているから、尽きることはないよ」。映像記憶は抜群だそうで「この仕事に向いているのかな」。
6月10日から、東京・新宿シネマカリテほかで公開。





