公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。
本木克英日本映画監督協会理事長=内藤絵美撮影
2022.8.25
インタビュー:過去のパワハラを認めつつ、意識改革徹底を 日本映画監督協会、本木克英新理事長
日本映画監督協会は1936年、2・26事件直後に小津安二郎監督らが発起人となって結成された由緒ある団体だ。その9代目の理事長に、本木克英監督が就任した。映画を取り巻く環境は、大きな変化のただ中にある。デジタル化、動画配信サービスの普及。それにセクハラ・パワハラの告発が相次ぎ、撮影現場での労働環境改善に向けた取り組みも進む。映画界は結束が求められ、撮影現場を束ねる監督の集まりである協会にも注目が集まっている。監督協会の今後について、新理事長に聞いた。

若手の声受け 異論押し切り声明発表
――前任の崔洋一監督は9期18年の〝長期政権〟でした。がんを公表し、理事長職から引いた後を受けての就任です。
重責を担ったことに身が引き締まる思いです。私は理事1期、専務理事1期を務めて、崔さんが療養に入ることで、次は本木というムードはありました。これまでの理事長は強烈な個性を放ち、社会的にも存在感があったと思います。私は松竹の商業映画で育ち、職人監督を目指してやってきた。自分で大丈夫なのかという思いはありますが、478人の監督にやれと言われたのだから、自分なりにがんばりたい。
監督協会は表現の自由の擁護と著作権の獲得を2大目標に、半世紀以上取り組んできました。映画監督の待遇や契約の基準を作ってきました。著作権の獲得は実現していませんが、基準を規定してきました。今後も地道に取り組んでいくことに変わりはありません。
――映画監督やプロデューサーからの性被害やパワーハラスメントを告発する週刊誌報道などが相次いでいます。日本映画監督協会は7月28日付で、「ハラスメントの根絶を目指す」との声明を発表しました。これまで協会は、個々の監督は異なる意見を持っているとして、政治的、社会的問題についてあまり立場を鮮明にしてきませんでした。
ハラスメントについては、協会内で長く議論してきました。そもそも監督協会は事業協同組合で、組合員の地位向上を図ることが目的です。団体として声明を出すべきではないという声はありますし、事実関係が明確でない週刊誌報道に反応すべきではないという意見もありました。
それでも、現場を担っている監督から、認識がずれている、一刻も早くハラスメント否定を表明してくれ、意思表示をしないと次の世代が協会に入ってこない、など強い要求がありました。声明発表は、こうした声を受けて半ば異論を押し切るような形で決断しました。協会が先頭を切ってハラスメント根絶に取り組むとは言えなくても、少なくとも今の価値観で見ればハラスメントがあったことを認め、意識改革を含めて取り組むべきだと思います。
セクハラは論外としても、パワハラについては、撮影現場はきれい事じゃ済まないという側面も指摘されました。映画は社会の闇を描いてきたんじゃないのか、と。しかし、作る作品と現場は違います。社会の闇を描いても、作っている現場に闇があってはいけない。その意識改革が必要です。具体策をどうするか、他の職能団体とも連携して考えていきたいです。

独断必要な撮影現場 問題はやり方
――ご自身は松竹の出身で、撮影所時代の撮影現場を見てきました。
自分でハラスメントはしていないにせよ、見過ごしていた後ろめたさを感じています。撮影所での助監督時代、いやだなと思うことはありました。満座の中で、特定のスタッフやキャストを怒鳴って組織をまとめていくようなやり方です。自分でも、声を荒らげてしまうことはありました。暴力は論外ですが、個人を攻撃することがないように、現場での振る舞いには気をつけなくてはならないと思っています。
協会の中にも、自分たちはハラスメントを受け入れて監督になったという人も多い。そういう環境で育ったので、指摘されるまでそういうものだと思っていた。殴る、蹴るに耐えるのが監督への道と思っていたのです。しかし、それは間違いです。
――一方で、大勢で一つの作品を創作する映画の製作現場を引っ張って行くには、民主主義ばかりではできませんね。
個性豊かな集団をまとめて短期間に創作するには、独断的なやり方も時に必要です。個人の才能によるところも大きく、監督はその中で競争しながら生き残ってきました。ただ、その遂行の仕方がハラスメントであってはならない。
映画は観客に自由を与えるものなのに、ハラスメントを意識しすぎると現場が息苦しくなってしまわないかという懸念もあります。でも、そうならないように、普段の行動の中でハラスメントはいけないと、価値観の転換を図るべきだと考えています。意識を変えられない監督は淘汰(とうた)され、いなくなると思っています。

1935年、建設されたばかりの松竹大船撮影所
労働環境改善は長年の課題
――ハラスメントが起きる背景に、撮影現場の厳しい労働条件があるという指摘もあります。
この20年の間に、撮影スケジュールや予算がどんどん厳しくなっていると感じています。観客数が横ばいか微増の中で作られる作品の数が激増した分、映画の規模や予算回収の見込みは縮小しています。大ヒットを狙った大作と小規模作に二分化して、中小規模作は過酷な撮影を強いられてしまう。自分の経験で言えば、2000年代初めに撮った「釣りバカ日誌」シリーズは、地方ロケだけで3週間かけましたが、21年の「大コメ騒動」は全部の撮影期間が16日でした。
そうした状況で、集団で行動するうちにフラストレーションがたまってくる。撮影期間は限定されているので、我慢すればいいと見過ごしたり、権力のある人に対して声をあげられなかったり。不満のはけ口になってしまう人がいても、周囲が慰める程度で終わってしまう。持ち出しが当たり前の自主製作映画と、プロの仕事である商業映画の境目がなくなって、「やりがい搾取」が横行してしまう。
ごく一部の人気監督は別として、映画監督で経済的に豊かな人は少ない。それでも、好きなことをやっているのだから我慢したらいいと思われがちです。文化の担い手として見られていないんです。
膨らむ製作費 理解得られるか
――そうした環境を改善しようと経済産業省が実態調査を進め、昨年4月、報告書をまとめました。契約書の締結や労働時間管理の必要性を指摘し、製作条件を監視する「映像制作適正化機関」の設置を提言しています。
働き方改革の流れが映画界にも及んだかっこうです。報告書をまとめる段階で監督協会も議論に参加しましたが、官庁主導だと報告書を作るだけで実効性を持てるかが問題です。あとは自発的に改善しろと言われても困るという部分もあります。
適正化機関を巡っては、映画界の中でも意見の相違があります。結局は予算の問題で、労働環境改善を図れば予算は増加します。日本映画の良さは、自主映画から大規模映画まで、さまざまな規模と内容の作品が作られている多様性です。適正化を強力に進めると予算は膨らみ、厳しいスケジュールの小さな現場が成立しなくなって、多様性が失われかねません。
また現在、日本映画の資金調達は製作委員会方式が中心で、映画業界以外の出資者が多く集まっています。そうした出資者に、予算拡大への理解を得られるかどうか。製作費はプロデューサー側の問題で、大手映画会社で作る映画製作者連盟が中心になるでしょう。映画会社の認識も変わってきて、やらざるを得ないと考えていると思います。
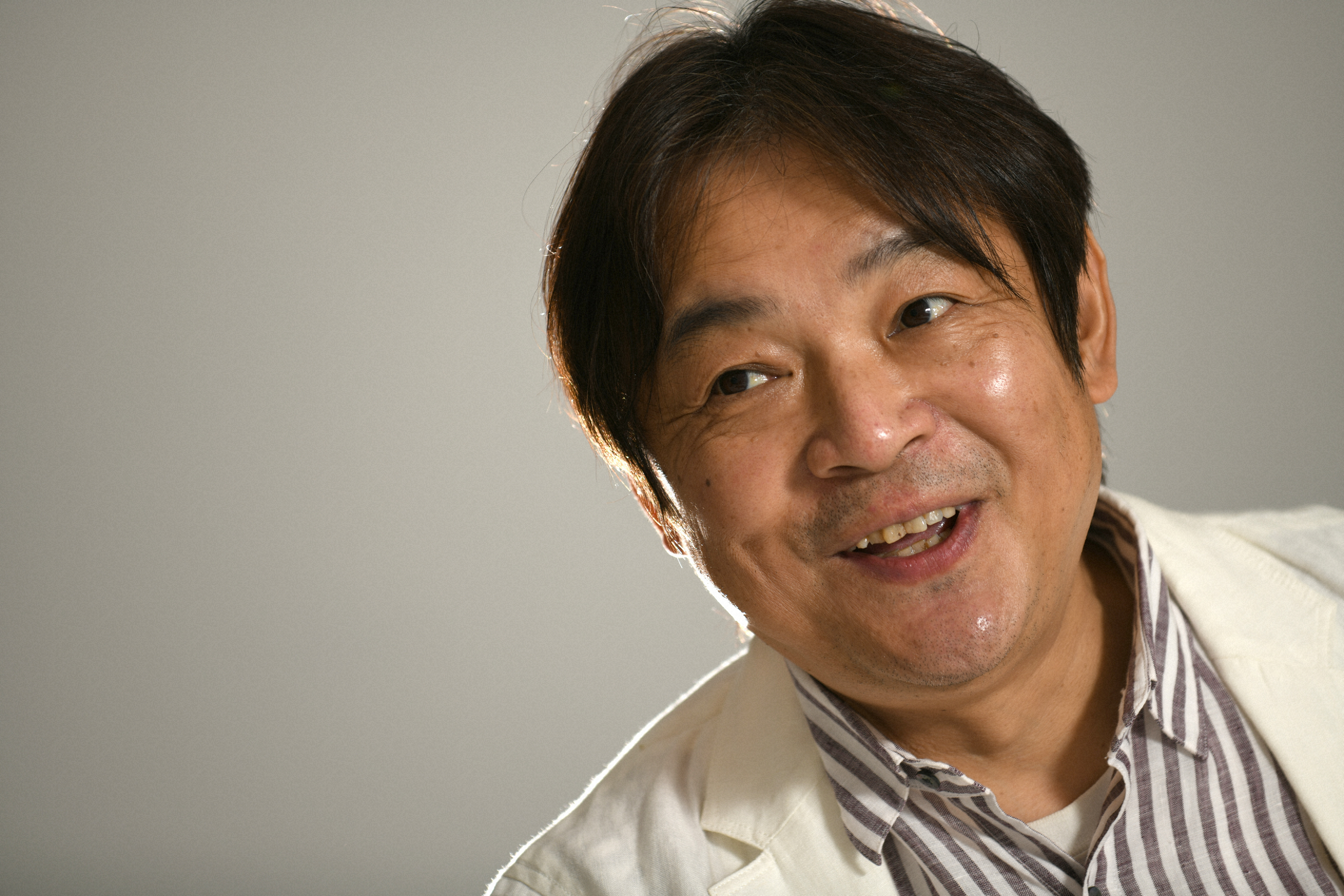
若手監督の明るい未来のために
――一線で活躍する監督たちが、コロナ禍で「ミニシアター・エイド基金」を立ち上げて映画館の具体的支援に乗り出したり、「日本版CNC設立を求める会」として映画界の共助システムを提言したりと、社会的な注目を集めています。しかしいずれも協会員ではありません。一緒に活動することはできないのでしょうか。
影響力のある人たちが問題提起をすることで、花火が上がって耳目を集めますが、具体化をするのは簡単ではありません。実現のために動くのは私たちで、地道に対策を講じたいと考えています。ただ、映画界全体の要求にしないと実現は難しいです。
日本版CNC構想も、興行収入の一部を還元する仕組みはすばらしいものの、実現にはハードルが多い。製作委員会方式が一般化した中で、映像業界以外の出資者に興収還元の理解を得られるか。法律を変えるしかないのでしょう。
「求める会」代表の是枝裕和監督ら有志の方たちともお会いして、入会して中から声を上げてほしいと呼びかけましたが、なかなかうまくいきません。組織の中で行動することに二の足を踏むのでしょうか。「一枚岩でない」と言われるのが残念です。
――戦争中に映画界が統制され、戦意高揚に協力させられた経験からか、映画界は政治と距離を置いてきたようにうかがえます。しかしフランスや韓国の映画界が政治と手を組んで発展してきたのを見ると、監督協会も政治力が必要な時期にきているのではないですか。
映画監督は個人事業主で、その集まりの協会も独立自尊を重んじる気風があります。現在も協会は、行政の補助金は受け取っていません。一方で、政治との関係を深めるべきだという意見もあります。実際、崔・前理事長時代から「文化芸術推進フォーラム」に参加して、他の文化団体とともに文化的環境の整備を政治家に働きかけてきました。コロナ禍では、さまざまな行政からの助成金を含めて、成果もあったと思います。
協会から政治家になる監督が出れば理想かもしれませんが(笑い)、クリエーターの苦境に理解を示す政治家に、もっといてほしいですね。
私は撮影所システムを知っている最後の世代でもあり、その良さを継承していくのも任務だと思っています。今期から理事に、大森立嗣、入江悠両監督ら、活躍中の40~50代の監督が理事に加わりました。若手監督が加入しやすい雰囲気を作りたい。彼らの世代が明るい未来を描けるようになればいいと思っています。
本木克英
もとき・かつひで 1963年12月6日生まれ。大学卒業後、松竹大船撮影所に助監督として入社。98年「てなもんや商社」で監督デビュー。代表作に「釣りバカ日誌」シリーズや「超高速!参勤交代」など。2023年「シャイロックの子供たち」が公開予定。






