毎週公開される新作映画、どれを見るべきか? 見ざるべきか? 毎日新聞に執筆する記者、ライターが一刀両断。褒めてばかりではありません。時には愛あるダメ出しも。複数の筆者が、それぞれの視点から鋭く評します。筆者は、勝田友巳(勝)、高橋諭治(諭)、細谷美香(細)、鈴木隆(鈴)、山口久美子(久)、倉田陶子(倉)、渡辺浩(渡)、木村光則(光)、屋代尚則(屋)、坂本高志(坂)。
シネマの週末
2023.2.17
チャートの裏側:狂騒の時代に愛を込めて
洋画ファンが減少して久しい。洋画のヒット作が激減した新型コロナウイルスのまん延以降というより、もう随分と長い間、そのような実感をもってきた。洋画ファンに関して、明快なデータはない。だが、そのようなことを考えないと、洋画低迷の理由は説明できない。
「バビロン」は、現在の洋画ファンの動向を知る上で注目した作品だった。無声映画からトーキーに至るハリウッド映画の革命期を舞台にした。そこで働く人たちのエネルギー、狂騒ぶりがすさまじい。画面に飛び交う欲望の渦が、毒蛇のようにとぐろを巻いている感じだ。
ただ、見る前と印象は変わった。狂騒ぶりがいささか度を越している。いわゆる、えげつないシーンも多い。だから、観客の好みが分かれる気がした。3日間の興行収入は1億円少し。案の定と言うべきか。洋画ファンが多くいた時代であっても、ヒットは難しかったろう。
とはいえ、本作はそのような常識的な見解を覆す強さをもつ。米国の映画人が描く映画への愛が途方もないからだ。映画の高みへ向かうスリリングかつ綱渡りのような人間模様が、見る者の胸にぐいぐい刺さる。メジャースタジオが、そのたくらみに大胆にも乗っかっている。すごいことだ。傑作とは言えないが、好きな作品なのである。(映画ジャーナリスト・大高宏雄)
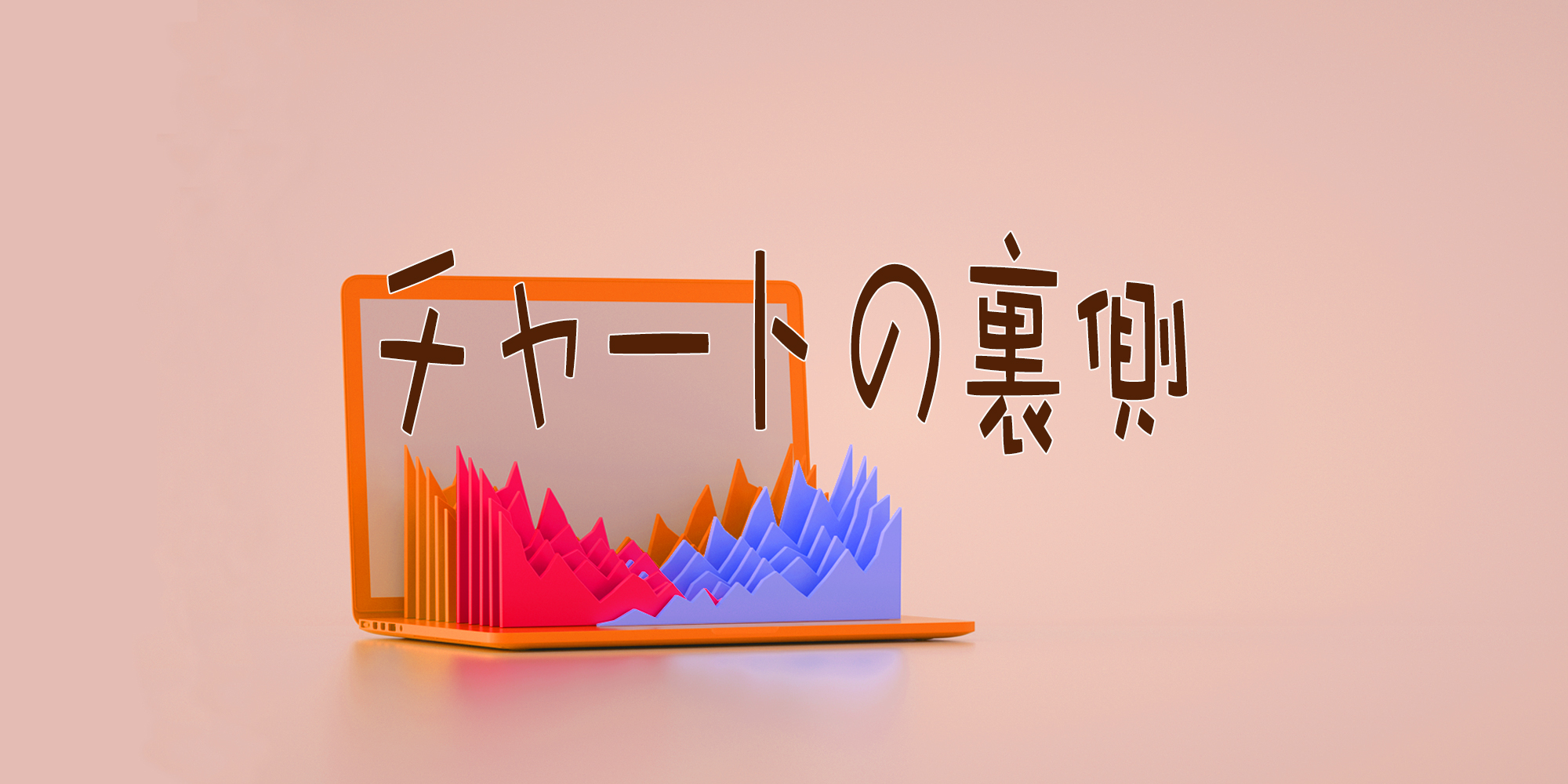
%202022%20Paramount%20Pictures.%20All%20Rights%20Reserved..jpg)




