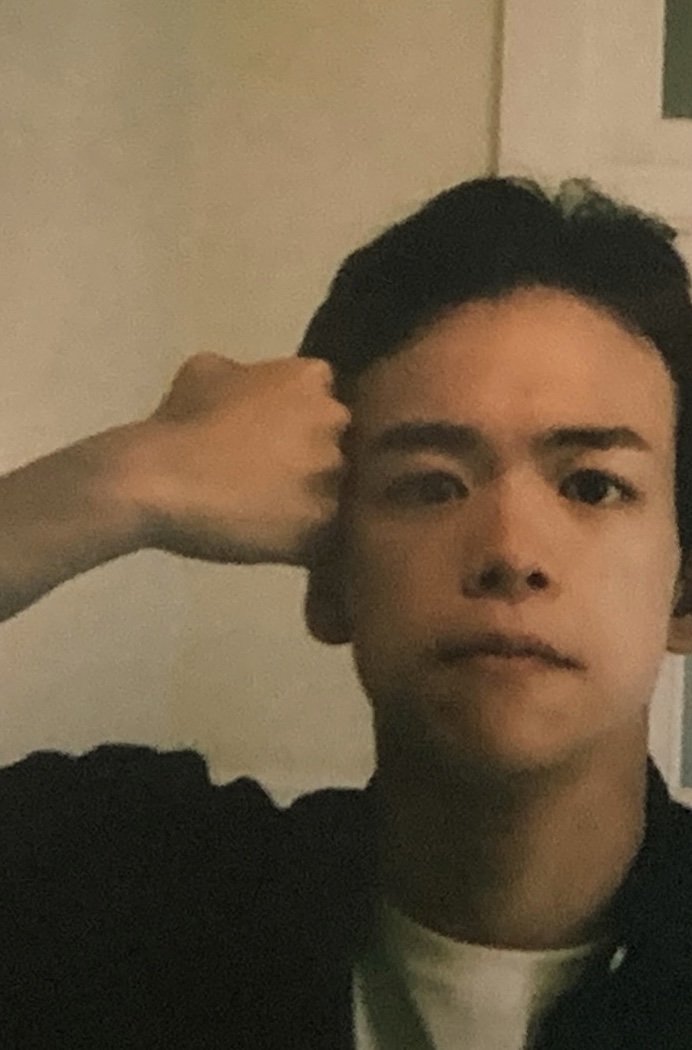毎回、勝手に〝2本立て〟形式で映画を並べてご紹介する。共通項といってもさまざまだが、本連載で作品を結びつけるのは〝ディテール〟である。ある映画を見て、無関係な作品の似ている場面を思い出す──そんな意義のないたのしさを大事にしたい。また、未知の併映作への思いがけぬ熱狂、再見がもたらす新鮮な驚きなど、2本立て特有の幸福な体験を呼び起こしたいという思惑もある。同じ上映に参加する気持ちで、ぜひ組み合わせを試していただけたらうれしい。
「イニシェリン島の精霊」©2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.
2023.3.02
「音楽」が断ち切る人間関係 「イニシェリン島の精霊」:勝手に2本立て
今回は、好きになれなかった映画の話。せっかく見に行っているのだから好きに越したことはないのだし、いやむしろそれをこそ望んでいるのだが、当然そうでないこともままある。ただ、好もうが好むまいが、どのみち見ているあいだ思考はめぐっていくのであり、その点では等価な体験とも言える。事実、たとえ好めなかった映画であっても、その作品を起点とするからこそ生まれる発想というのはありうる。
「突然嫌いになっただけ」
その映画というのが、現在劇場公開中の「イニシェリン島の精霊」(2022年)。じっさいの展開には紆余(うよ)曲折あるが、端的にまとめれば本作は「音楽探究のために親しい人との交際を絶つ話」といっていい。
ただし、主人公は関係を絶たれる側。男ふたりで連れ立って、毎日パブへ行きビールを飲んでいたはずの親友が、あるとき突然絶縁を切り出してくるのだ。何か迷惑をかけた覚えもなく、相手もまた「お前が悪いわけじゃなく、突然嫌いになっただけ」だと言う。そんなことを言われても、自分に落ち度がないなら安心とはならないわけで、主人公はうっとうしがる相手の顔色をうかがいながら、原因を突き止めて関係修復を図ろうとする。ひとまずは、至極まっとうな反応といえよう。
先に書いたとおり、「好きになれなかった」理由はいくつかあるが、本稿はそれに触れる場ではない。演出的にノイズを多く感じてしまったとだけ書いておこう。けれど一方で、1本まるまる絶縁話で引っ張るという着想自体は、依然として魅力があるものに思えるし、じっさい見たくなったのもそこが気になったからだった。だから、今回は絶縁展開=ストーリーの次元にのみ焦点を絞って取り上げる。

退屈なお前と酒を飲んでいたら名曲は書けない
予告では触れられていないが、次第に明らかになる絶縁の理由のひとつは「独りの時間がほしい」という、これまたきわめてまっとうなもの。人生は限られているし、趣味の音楽を突き詰める時間がほしい、だから無駄な人付き合いはやめにしたい、というわけだ。
なぜこのような心境に至ったか説明はない。しかし、男ふたりに明確な年齢差があるのも無縁ではないはずだ。特に年齢が明言されるわけではないが仮に演者と同年齢とするなら、コリン・ファレル演じる主人公は46歳。他方、ブレンダン・グリーソン演じる絶縁を切り出す親友役は67歳。もう若くはない、というか「高齢」にさしかかっている(なんせ舞台は1920年代なのだから、寿命の感覚も現代とは大きく異なるだろう)。毎日バカ騒ぎしている暇はない、そう思ったとて不思議ではない。本人の言によれば、後世に残るような作曲を試みたいとのこと。退屈なお前と酒ばかり飲んでいなければ名曲が書けるのだ、という。

「セッション」©2013WHIPLASH,LLC.ALL RIGHTS RESERVED.
「セッション」 エリートドラマーが恋人を捨てる
煩わしい友人関係を断ち切るというだけなら理解は容易だが、裏の理由が「音楽に打ち込む時間を捻出するため」だというのに驚いた。劇場で見ながら、即座にデイミアン・チャゼル監督作「セッション」(14年)を思い浮かべた──ある意味、同じ話なのだ。
とはいえ、こちらの主人公は関係を断つ側。しかも若い。名門音楽大学でドラマー志望、校内でも一握りの生徒のみ所属が許される一流バンドに所属が決まったばかりで前途洋々の青年だ。彼が断ち切るのは、付き合って間もない恋人である。もちろん理由は音楽探求。デートしている暇はない、というわけだ。
こちらの場合も、引き金をひくのは焦り。年こそ若いが、主人公は成功に取りつかれていて「文なしで早世して名を成したい、元気な金持ちの90歳で忘れ去られるよりも」というセリフまである。学年問わずに優秀な人材のみ集められたバンドに在籍しているのだから、すでに順調といっていいが、それがなおさら強迫観念に拍車をかけることにもなる。別れを切り出すのは、バンドに新ドラマーが加入して立場が脅かされたあと。練習しても練習してもまだ足りない、ならば……という次第で、これ以上無くわかりやすいタイミングといえる。
「時間が必要だ。君と会う余裕なんてない」
面白いのが、そもそも恋人にアプローチをかけたのは主人公のほうであり、関係性も良好な描写がなされていることだろう。もちろん恋愛は、あくまで本作においては限定的要素に過ぎず、時間としてはごく僅かしか描かれていない──行きつけの映画館で働いている相手を初めてデートに誘う場面、お気に入りのピザ屋でデートをする場面、関係断絶までに描かれる交流はたった2場面だけだ。
ただ、出来事のタイミングを考慮すると、のちの展開を含めて納得がいく。初めて相手を誘うのは、前述のエリートバンドに在籍が決まった直後だし、デートでの穏やかな時間は練習初日に絞られたあとのささやかな息抜きとして描かれている。別れを切り出す場面のすこし前も携帯電話に「連絡してね」とメッセージが来て、思わずにんまり。要は、関係性に嫌気がさしていたわけではない。
映画自体が交際描写に時間を割いていないがゆえに、「もっと時間が必要なんだ、君と会う余裕なんてない」という主人公の身勝手な主張は、より一層無理のあるものに感じられる。なにせ、誘うのが上映開始13分時点、デートが35分時点、携帯電話の伝言が43分時点、別れるのが50分時点だから、楽しげなデートから破局まで、上映時間のうえでは15分しかたっていないのだ。
身勝手な欲望 成果を聴かせたい
別れたあとで主人公は2度、元恋人に連絡を取ろうか迷う。1度目は、ある理由から退学処分になり失意の日々のさなか。2度目は、唐突に幸運が舞い込み華々しく返り咲くチャンスを手にしたときだ。彼は、1度目では連絡を取らず、2度目には電話をかけることにする。
自らが出演するコンサートに相手を誘おうとする主人公は、「終わったらピザでも食べながら、また大学のグチでも言い合わないか」と関係修復をもくろんでいるように映る。その積極性は、初めてデートに誘ったときと同様のものだ。順調な状態に身を任せている。けれど、本来なら失意のときに電話をするでも良さそうなものである。挫折体験を話し、謝罪すれば、もしかすると交友を再び始められたかもしれない。けれど、そうはしない。音楽のために切り捨てた相手を、誘うのもまた音楽なのだ。成果を見せたい、そして関係性を犠牲にした価値があったのだと示したい、ということかもしれない。
「イニシェリン島の精霊」にも同様の場面がある。お前さんと一緒に過ごさなかったおかげで、たった数日でこんな曲が書けた……と言って、切り捨てた元友人=主人公にフィドル──バイオリンを思い浮かべていただければよい──を演奏して聴かせるのだ。なぜわざわざそんなことを? 主人公は音楽に造詣が深いわけでもなく、聴いたところで曲の良しあしは分からないだろう。これもまた、自らの選択を正当化するために見える。「今度話しかけてきたら、1回につき1本、自分の指を切り落とす」と宣言までしてはねのけた相手に、律儀に報告する理由はほかにあるまい。

同じく絶縁、異なる印象
関係性というものは双方の合意あって初めて成立するものとはいえ、どちらの映画で描かれるのも身勝手で一方的な振る舞いである。ただ、じつは印象は大きく異なりもする。主人公が、絶縁する側か、される側かというのも要因ではあろうが、関係性を断ち切ってまで選び取った音楽がどれほどの比重で扱われているか、という点も重要な差異だろう。良しあしはともかく「セッション」の主人公は全編練習に徹するが、「イニシェリン島の精霊」では作曲も練習もさほど登場しない。主人公と時間を共にしなくなり、たしかに独りで過ごすことも増えているようだが、依然として昼はパブで酒を飲んでいるし、近所の人々とも会話している。拒絶する対象は主人公だけのようだ。むろん、これは必ずしも作品の欠点というわけでなく、むしろ織り込み済みの違和感なのだろう。
つまるところ、「イニシェリン島の精霊」の主眼は音楽それ自体にはないとみていい。あくまで焦点は断絶状態のほうに当てられていて、セリフでも言及される通り、わざわざ1920年代のアイルランドを舞台に設定することで、男ふたりの関係性が内戦と重ねられてもいる寓話(ぐうわ)なのだ。
だからこそ、というべきか最終的には、まるで手の内を明かすかのように、絶縁を切り出した男は宣言通り指を切り落とす──しかも、楽器の弦を押さえるためには不可欠な手の指をすべて。そのうえ、若者たちが楽器を演奏している酒場で、指を失ったがために演奏へ加わることができず、弾けないフィドルを片手にただ聴いているという様子まで示される。
まるで、本作は音楽を描く映画ではない、と映画自体が証し立てているかのようだ。むしろ、楽器を奏でられなくなってもなお主人公を避け続けるところに、本作が優先した主題を明確に見てとることができるようになっている。作り手の意図を看取したからといって、それが好ましく思えるようになるわけではないのだが、この逡巡(しゅんじゅん)もまた映画体験の一部である。
「セッション」はU-NEXTで配信中。