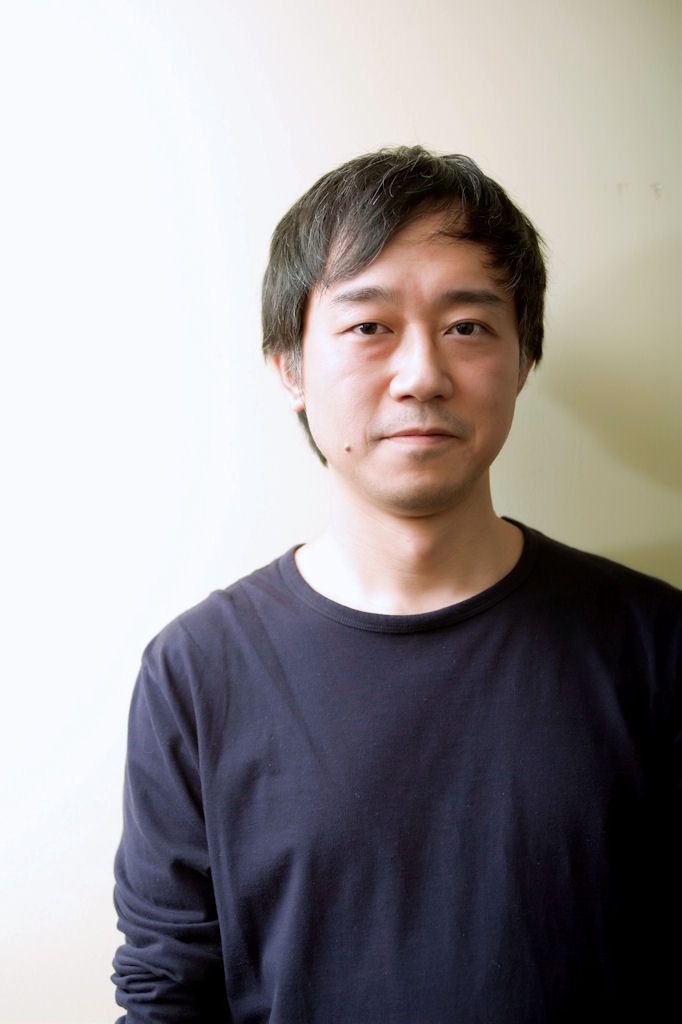いつでもどこでも映画が見られる動画配信サービス。便利だけれど、あまりにも作品数が多すぎて、どれを見たらいいか迷うばかり。目利きの映画ライターが、実り豊かな森の中からお薦めの作品を選びます。案内人は、須永貴子、大野友嘉子、梅山富美子の3人に加え、各ジャンルの精鋭たちが不定期で寄稿します。
「ロスト・ドーター」 Netflixで独占配信中
2022.2.20
オンラインの森「ロスト・ドーター」 女性の罪の意識 サスペンスに
不吉な気配漂わせるニュアンスの表現
2021年のベネチア国際映画祭で最優秀脚本賞を受賞し、全米賞レースでも存在感を放っているNetflixオリジナル映画「ロスト・ドーター」(2021年)は、「ダークナイト」(08年)、「クレイジー・ハート」(09年)などの出演作で知られる女優マギー・ギレンホールの長編監督デビュー作だ。今さら著名俳優が監督業に進出し、優秀なスタッフ&キャストのサポートを得てウェルメードな作品を撮ったとしても驚くべきことではないが、「ロスト・ドーター」の出来栄えは並外れている。イタリアの作家エレナ・フェッランテの同名小説を映画化した人間ドラマであり、見ようによっては実に恐ろしい心理サスペンスである。
マギー・ギレンホールの監督デビュー作
物語は米マサチューセッツ州在住の48歳の文学教授レダ・カルーソ(オリビア・コールマン)が、単身ギリシャの島を訪れるところから始まる。海辺の小さなホテルを予約しておいたレダの目的は、執筆活動のかたわらバカンスを満喫すること。しかし浜辺で幼い娘を連れた女性ニーナ(ダコタ・ジョンソン)の姿を目撃したレダの脳裏に、若くして2児の母親(ジェシー・バックリー)になった20年前のトラウマがよみがえり……。
20代の頃、気鋭の文学研究者だったレダは、キャリアの追求とせわしない育児のはざまでいら立ちを募らせ、あるものを〝捨てる〟という決断を下した。フラッシュバックを導入して今なお罪の意識にさいなまれる中年女性の複雑な内面に迫った本作は、いわば女性の生き方についての考察である。両立困難な育児と仕事のバランス、もしくは母性は絶対的に神聖なのだという固定観念。ところが本作は、そうした世界中の母親たちが悩んでいる問題へのポジティブな対処法やメッセージを示そうとしない。前述したように〝恐ろしい〟映画なのである。

といっても罵声や暴力が飛び交うわけではない。まばゆい陽光が降り注ぐ真夏のリゾート地は、ダークな心理的主題を探求するにはいかにも不似合いな舞台設定だが、ギレンホール監督は緻密な細部の描写、微妙なニュアンスの表現によって画面に不吉な気配を漂わせる。レダが宿泊するホテルの部屋に用意された〝腐った果物〟、彼女の睡眠を妨害する〝灯台の光〟や〝虫〟、さらには頭上から降ってくる大きな〝松ぼっくり〟までもがレダを物理的に傷つける。
極めつきは〝人形〟だ。とある白昼、浜辺でニーナの娘エレーナが行方不明になったとき、レダはエレーナを捜しあてた陰で彼女の大切な人形をこっそり持ち去ってしまう。ここでの人形はレダの現在と過去を結びつけるアイテムでもあるのだが、レダがなぜ意地悪を楽しむかのように人形を盗んだのかという動機に関する具体的な描写はどこにもない。ひょっとすると、レダ自身もその答えを知らないのかもしれない。ほかにもレダがホテル管理人(エド・ハリス)らと何気なく会話している最中、彼女の不審な言動が違和感を生じさせ、緊張を走らせる瞬間がいくつもある。普段は理知的でユーモアのセンスも備えた主人公の病んだ一面が表出し、悲しげで、怪しげで、時に滑稽(こっけい)な人間の不可解さにゾクリとせずにいられない。
撮影監督エレーヌ・ルヴァールの妙手も一役
しかも、こうしたアイデンティティーや感情の揺らぎを、ささやかな映画的サスペンス、サプライズに結実させた技術面もハイレベルだ。すかさず鑑賞後に調べてみたら、レダの記憶に基づく回想シーンをあたかも夢のように編集したのは、トッド・ヘインズ、ジム・ジャームッシュ作品の常連スタッフであるアルフォンソ・ゴンサウベスだった。おまけに、映像に不穏なムードを吹き込んだ撮影監督は、「夏をゆく人々」(14年)、「ペトラは静かに対峙する」(18年)、「17歳の瞳に映る世界」(20年)のエレーヌ・ルヴァールではないか。むろんレダの現在と過去を、ふたりひと役で演じ分けたコールマンとバックリーの貢献度も計り知れない。
そして母性という呪縛にもがき苦しみ、異国の海辺の町をうつろに漂流するレダのひとり旅にも終わりがやってくる。殺人事件が起こるわけでもないのに恐ろしく、奇妙に美しくもあるバカンスムービーの終着点やいかに。そこにそっと添えられた果実の〝オレンジ〟というアイテムが、またもや映画を深遠なまでに謎めかせるのだ。