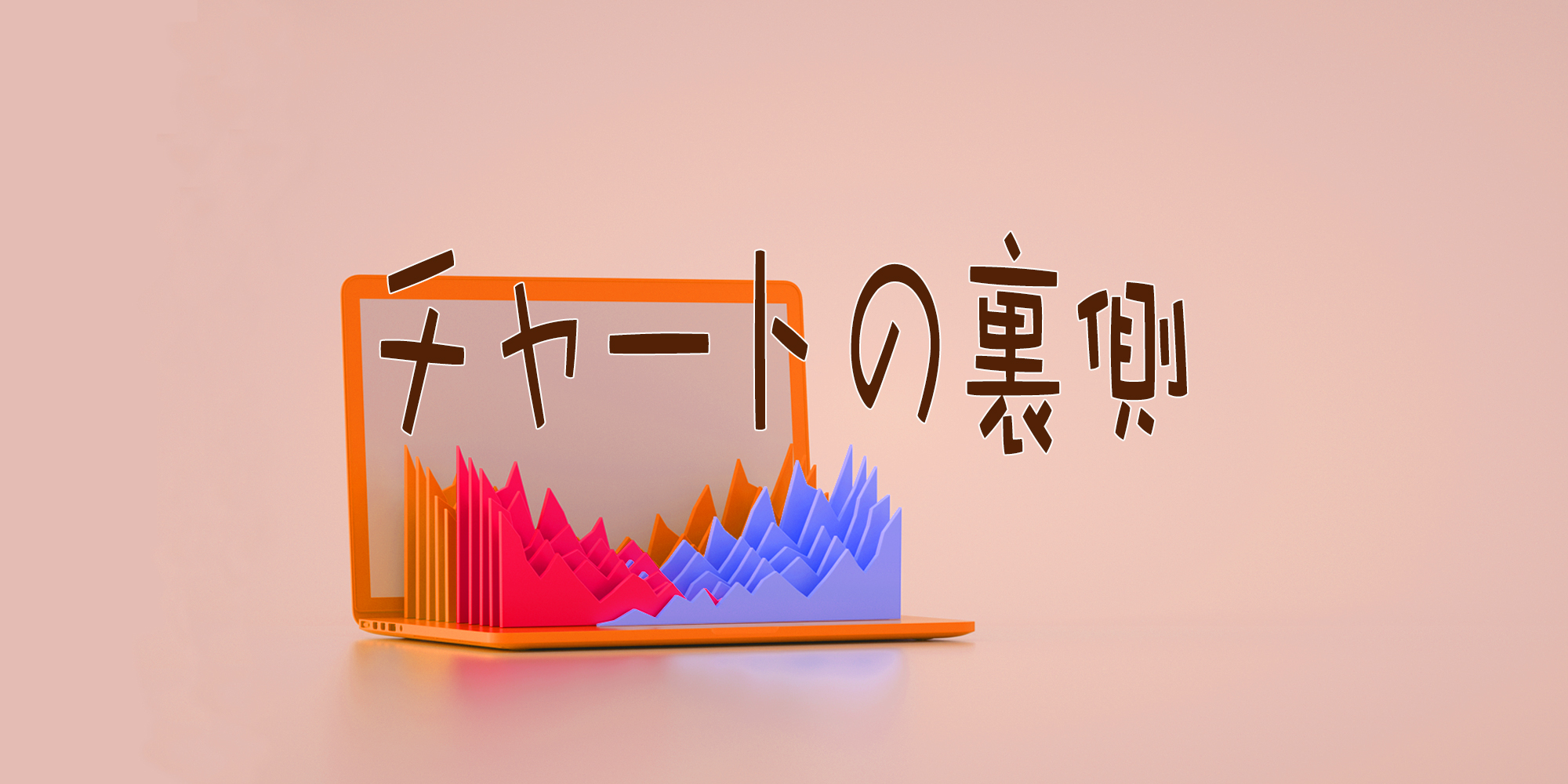毎週公開される新作映画、どれを見るべきか? 見ざるべきか? 毎日新聞に執筆する記者、ライターが一刀両断。褒めてばかりではありません。時には愛あるダメ出しも。複数の筆者が、それぞれの視点から鋭く評します。筆者は、勝田友巳(勝)、高橋諭治(諭)、細谷美香(細)、鈴木隆(鈴)、山口久美子(久)、倉田陶子(倉)、渡辺浩(渡)、木村光則(光)、屋代尚則(屋)、坂本高志(坂)。
シネマの週末
2023.11.10
チャートの裏側:ゴジラ、堂々たる原点回帰
公開初日の3日が、最初の3日間で一番成績が良かった。しかも、製作の東宝系列のシネコンの集客率が、他系列を圧倒した。「ゴジラ−1.0」だ。同日は最初の「ゴジラ」(1954年)が公開された記念すべき日。ゴジラファンの熱い心情があふれた。興行収入は10億円を超えた。
ゴジラは戦争末期から終戦直後に出現する。ゴジラとの対峙(たいじ)は、日本人にとっての新たなる戦争という位置付けがある。自衛隊がない時代。米国も冷戦のさなか、及び腰だ。ここに民間人が登場する。元軍人たち、特攻隊の元飛行士が戦いの中核を担う。恐るべき設定である。
激戦地で生き残った者たちの戦いをどう見るか。戦争時と変わらない日本という国への不信感が、作品の根幹に流れる。ゴジラと戦う主体から、今に通じる日本の防衛体制が皮肉られているようにも見える。その視点は、過度な国防意識につながりかねない危うさも併せ持つ。
伊福部昭のオリジナルテーマ曲に乗ってゴジラが東京・銀座に現れるシーンには震えが来た。日劇が壊される。有楽町駅付近の電車が宙づりになる。ゴジラの破壊は、虚構としての快楽を生む。ゴジラがはらむ政治的、社会的な意味合いと、破壊ぶりの尋常ではない興奮度。両者をまたぐ形で「ゴジラ−1.0」は屹立(きつりつ)する。1作目も同様だった。堂々たる原点回帰である。(映画ジャーナリスト・大高宏雄)