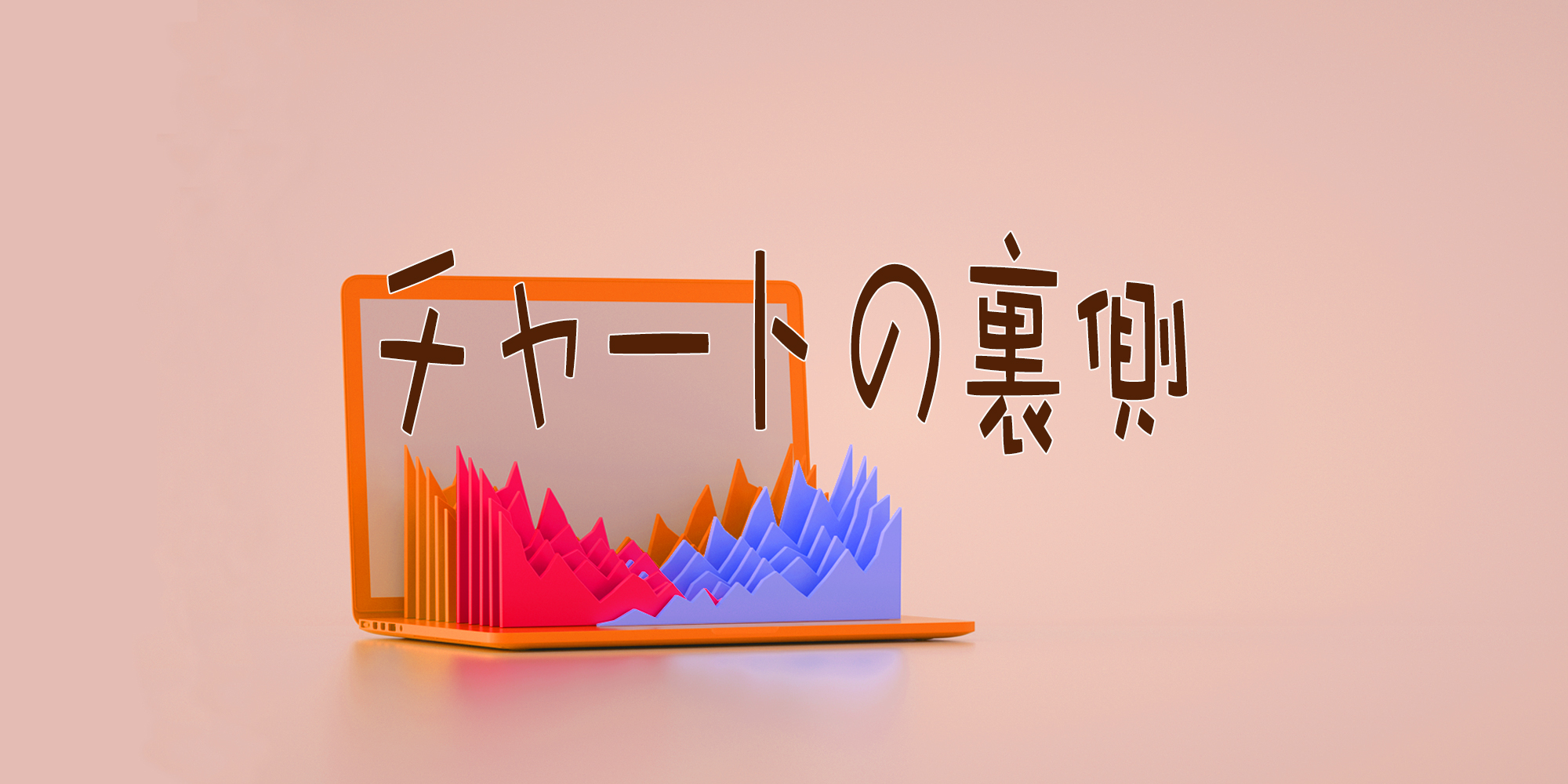毎週公開される新作映画、どれを見るべきか? 見ざるべきか? 毎日新聞に執筆する記者、ライターが一刀両断。褒めてばかりではありません。時には愛あるダメ出しも。複数の筆者が、それぞれの視点から鋭く評します。筆者は、勝田友巳(勝)、高橋諭治(諭)、細谷美香(細)、鈴木隆(鈴)、山口久美子(久)、倉田陶子(倉)、渡辺浩(渡)、木村光則(光)、屋代尚則(屋)、坂本高志(坂)。
シネマの週末
2024.4.05
チャートの裏側:「オッペンハイマー」の米国
公開前、「オッペンハイマー」は「原爆の父」を主人公にしたことで、いろいろ物議を呼んだ。ところが映画を見れば、ある部分が異様にせり上がっているのが実感できた。それは、原爆中心の情報とはいささか異なる。今に通じる米国の国家像が赤裸々に描かれていたのだ。
時制を複雑に交差させ、主人公がたどる道筋の中で、恐るべき獰猛(どうもう)さを帯びた米国という国家が浮かび上がる。ナチス、共産主義を前にしたとき、凶暴さが画面に突き刺さる。そのただ中、日本は甚大な悲劇に見舞われる。原爆を落とすまでの経緯が全くさりげない。言葉を失う。
これは「原爆の父」の伝記映画でありつつ、戦禍を描かない戦争映画にも見える。戦争と対峙(たいじ)した、あるいは戦争を想定に入れた際の米国の強大な国力と、国内では権力を隅々にまで行き渡らせる人海戦術が画面を覆いつくす。その「戦い」が現代につながる恐ろしさをもつ。
声高ではないだけに、作品の底流にある米国への辛辣(しんらつ)で批判的な視座が、じわりじわりと感じられてくる。米国という国家の仕組みの数々が、ダイナミックな映像の連鎖の中から、湯水のようにあふれ出る。事前の情報は、確かに大きな話題を生んだ。鑑賞動機の分かれ目にもなったろう。ただ、話題性に振り回されても、どうかと思う。映画は見ないとわからない。(映画ジャーナリスト・大高宏雄)