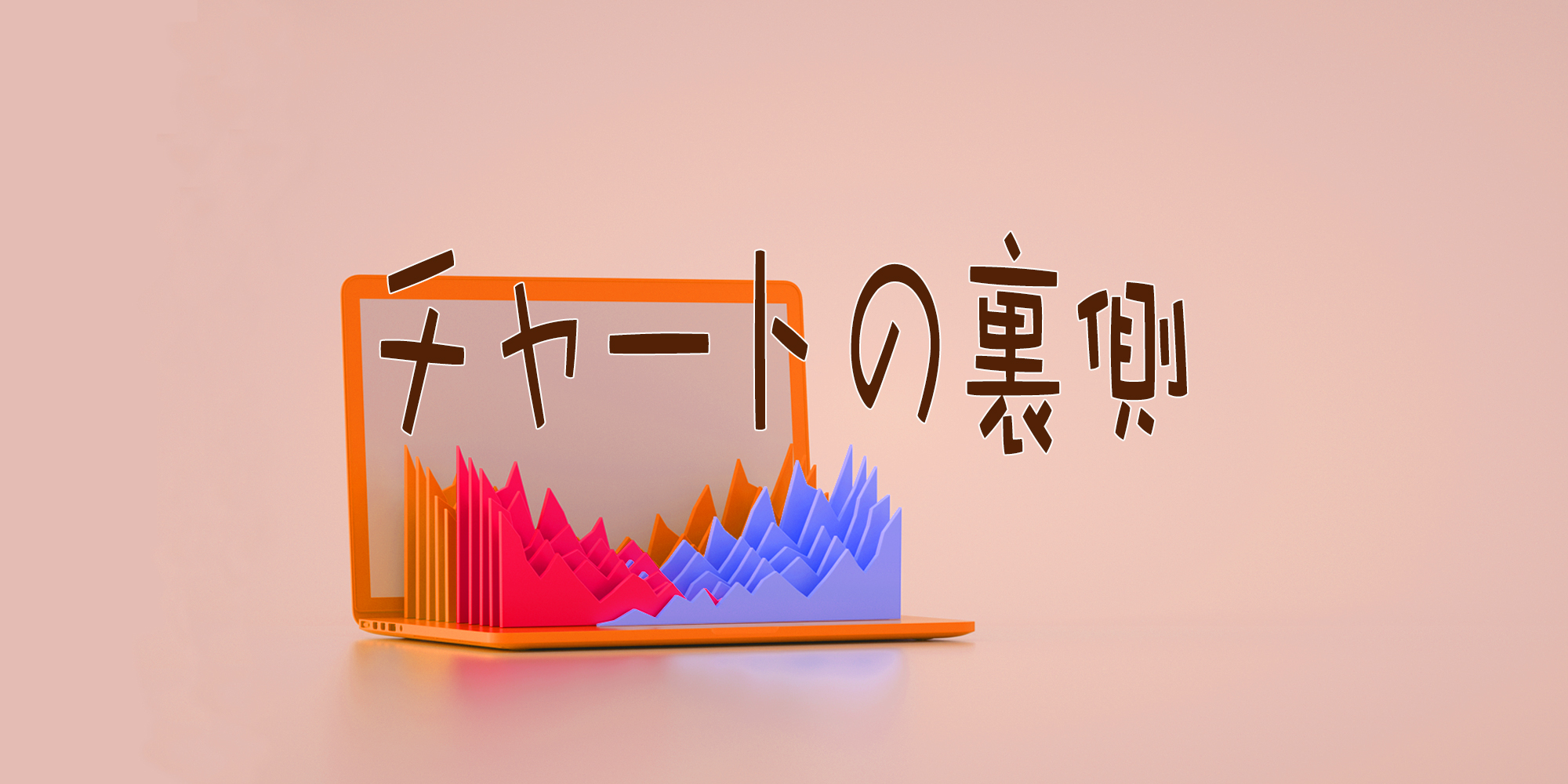毎週公開される新作映画、どれを見るべきか? 見ざるべきか? 毎日新聞に執筆する記者、ライターが一刀両断。褒めてばかりではありません。時には愛あるダメ出しも。複数の筆者が、それぞれの視点から鋭く評します。筆者は、勝田友巳(勝)、高橋諭治(諭)、細谷美香(細)、鈴木隆(鈴)、山口久美子(久)、倉田陶子(倉)、渡辺浩(渡)、木村光則(光)、屋代尚則(屋)、坂本高志(坂)。
シネマの週末
2024.5.17
チャートの裏側:感情移入以上の「没入感」
最近、エンタメ施設などで、「没入感」という言葉がよく使われる。施設のさまざまな仕掛けを介して、訪れた人が体験型の高揚感を味わう。映画でも、その感覚があった。「猿の惑星/キングダム」だ。主人公の猿の側に強く入り込む自身がいた。精神の「没入感」である。
本作は、主人公ノアの堂々たるビルドゥングスロマン(成長譚)だった。これが、「没入感」の大きな理由だ。ノアは、住み慣れた狭い地域のことしか知らない。エコーと呼ばれる人間は、災いをもたらす害虫との認識だ。別の猿軍団の襲撃に遭い、ノアの冒険が始まる。
ノアは実に聡明(そうめい)だ。先人の教えから、歴史や伝承が記された本の価値を知る。自身の部族とは全く無縁の未知の機材に驚く。敵対していたエコーとの共存のあり方に踏み込む。ノアの冒険とは、世界の成り立ち、仕組みを認識していくことだ。世界に対して心が開かれている。
映画の感受の仕方としては、「没入感」より感情移入のほうが一般的だろう。だが、本作はちょっと趣が違う。感情移入以上の高揚感があった。ノアから聡明さを生み出しているものこそ、ピュアな魂に他ならないからである。今という時代、この魂のあり方がどれほど大切なことか。直接的な体験型だけが「没入感」をもたらすのではない。精神の通い合いである。(映画ジャーナリスト・大高宏雄)