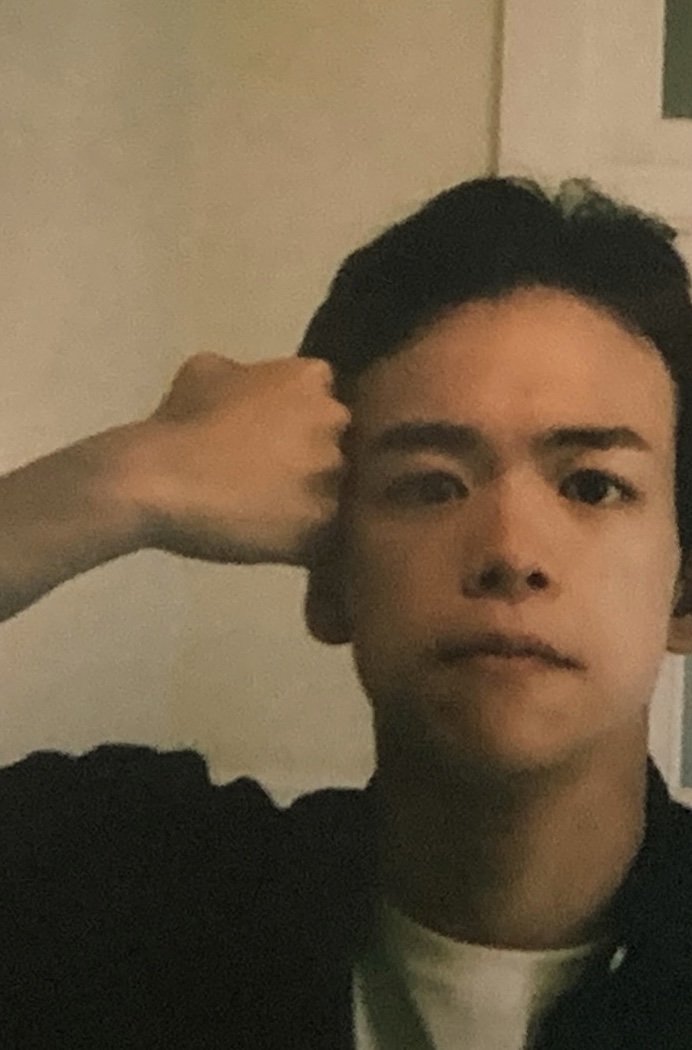毎回、勝手に〝2本立て〟形式で映画を並べてご紹介する。共通項といってもさまざまだが、本連載で作品を結びつけるのは〝ディテール〟である。ある映画を見て、無関係な作品の似ている場面を思い出す──そんな意義のないたのしさを大事にしたい。また、未知の併映作への思いがけぬ熱狂、再見がもたらす新鮮な驚きなど、2本立て特有の幸福な体験を呼び起こしたいという思惑もある。同じ上映に参加する気持ちで、ぜひ組み合わせを試していただけたらうれしい。
さらば愛しきアウトロー © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved
2022.3.13
勝手に2本立て:「さらば愛しきアウトロー」 脱獄はやめられない
ある映画を見て、無関係な作品の似ている場面を思い出す。未知の併映作への思いがけぬ熱狂、再見がもたらす新鮮な驚き。2本立て特有の幸福な体験を求めて、勝手に映画を結びつけて紹介します。かなめは〝ディテール〟。意外な組み合わせをお試しあれ。
自分の世代の映画作家 デビッド・ロウリー
以前、尊敬している人から「『自分の世代の映画作家』と思える好きな作り手はいますか」と言われたことがある。たしか2018年の春だったと思う。情けなくも、当時の私には答えられなかった。映画が好きで、毎日なにかしら見ていたはずだが、なにも頭に浮かんでこなかったのだ。現役で活躍している思い入れのある作り手は何人かいたが、彼らは遅くとも1990年代には頭角を現していた監督たちで、97年生まれの私にとって「自分の世代の」というには違和感があった。
けれど、いまなら間違いなく答えられる。デビッド・ロウリーこそがそうである。いま思えば、あのとき答えられなかったのはむしろ良かった。なぜなら、同年の冬に――本国から1年以上遅れて――公開されたロウリーの「A GHOST STORY/ア・ゴースト・ストーリー」(17年)にほれ込むことになったからだ。優れた作り手の登場に驚くこと、思わぬ傑作にうれしくなることは時折あるが、ここまでの衝撃はほかにない。
ロウリーの名前自体は、わりあい早くから記憶にとどめてはいた。前述の衝撃から更に4年前、彼の長編第2作「セインツ 約束の果て」(13年)をすでに見ていたからだ。忘れもしない、シネマート新宿の〝狭いほう〟――定員60人ほどのスクリーン2――にて、最前列でかぶりつくように。ただ、パンフレットすら作られておらず、当時はあくまで無名の新人監督という認識に過ぎなかった。
脱獄、脱獄、また脱獄の2本
さて、前置きが長くなったが、今回ご紹介する「さらば愛しきアウトロー」(18年)はそんなロウリーの長編第5作で、前述の「セインツ」が呼び寄せた縁がまわりまわって結実した企画である。というのも、ロウリーの才能が最初に見いだされたサンダンス映画祭は、もともと78年に俳優ロバート・レッドフォードが立ち上げたものであり、実際に「セインツ」を見て気に入ったレッドフォードによって本作の企画は動きだしたのだという。実在の老齢銀行強盗フォレスト・タッカーを材に採っているゆえ、ネタバレもなにもなかろうと、あえて終盤の展開に(のみ)触れさせていただくが(まっさらな状態で楽しみたいという方は、まず見てみてほしい)、驚かされたのは、映画も終わりにさしかかったころに現れるモンタージュである。
とうとう御用となり収監中の身であるタッカー(レッドフォード)は、面会に現れた恋人(シシー・スペイセク)に数枚の紙切れを手渡す――そこには、生涯で16回もの脱獄歴が記されている。その途端、場面は切り替わり、めくるめく脱獄の変遷が流れるように描かれる〝プリズン・ブレーク・モンタージュ〟――カナ表記にするとなんだか気恥ずかしいが、監督本人の言――が始まるのだ。この作品自体は、マイケル・マンの諸作も大いに参考にしたという〝強盗映画〟であり、決して〝脱獄映画〟ではないはずだが、このわずか数分がもたらす高揚は、脱獄映画特有の感触があった。
多くの場合、映画で描かれる脱獄は一度である。しかし時に、一度きりの脱獄を精緻に突き詰めて描写するのではなく、劇中で何度となく脱獄を繰り返す例もある。中島貞夫の「脱獄広島殺人囚」(74年)がそれだ。1回の脱獄に費やされる時間はきわめて短い。なにせ、上映時間はたった97分なのに、脱獄が4回も起こるのだから、1回あたり平均24分ほどということになる。それゆえ、多くの脱獄映画に通底する、強じんな意志で気が遠くなるような地道な作業を貫徹するさまを見届ける……という緊迫とは無縁で、わりとトントン拍子に何度もムショを後にする主演の松方弘樹に、われわれは拍子抜けしつつも心地よいおかしさを味わうことになるのだが、あまりに頻繁に脱獄と逮捕を往復する作劇に体が慣れ始めると、感覚が反転する。要は、脱獄に解放感を覚えなくなるのだ。題名に明らかなように本作が〝脱獄映画〟なのは間違いないので、いささか矛盾しているようなのだが、次第に脱獄場面が逮捕のための布石/下準備のようなものとして機能していることが分かってくる。そうなると、見ているわれわれの心中は常にこのようなものになる――「今回は、いつ、どこで捕まるのか?」。破獄し、シャバをさまよう松方の姿を追いながら、もしやここでか、さすがに違うか、そろそろか、いやまだのようだ、などと勝手に思いを巡らせることになるのである。

脱獄広島殺人囚 ©東映
現実は映画より奇なり?
単に、習慣化された脱獄行為が幾度も描かれるという共通項で並べてみた2本だが、続けて見ると鏡像のようなラストに驚かされる。画面から遠ざかるレッドフォードの背中と、画面へ向かって歩いてくる松方の姿……向きは全く逆だが、共に描かれない〝先〟を予感させ、まるで彼らがいまも〝習慣〟のさなかにあるのだと告げているようだ。きっといずれ捕まり、性懲りもなく何度でも逃げ続けるのであろう。脱獄のループから逃れられない彼らは、ある意味でルーティンにとらわれた囚人ともいえ、それがどこか哀愁を漂わせもしているのだが、この記事を書くため製作背景について調べていて驚いた。「さらば愛しきアウトロー」が実在の老強盗を題材としていることはすでに書いたとおりだが、「脱獄広島殺人囚」にもモデルがいたのである。そして、そのモデルとなった脱獄王は後年脱獄をやめたというのだ。実際の彼は、刑務所内に恋人ができたため「こっちのほうがいい」と結論づけたらしい――まさにフィクションを凌駕(りょうが)する現実。この事実を反映してもそれはそれで面白いものになったろうが、そうはせず、あくまで習慣的脱獄のはざまで物語を終えることを選び取ったがゆえに、失われなかった良さもあることがわかる。
「さらば愛しきアウトロー」「脱獄広島殺人囚」とも、U-NEXTにて見放題で配信中