ハラハラドキドキ、謎とスリルで魅惑するミステリー&サスペンス映画の世界。古今東西の名作の収集家、映画ライターの高橋諭治がキーワードから探ります。
テナント/恐怖を借りた男 (C) 1976 Marianne Productions. All Rights Reserved. TM, (R) & (C) 2015 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.
2022.5.31
謎とスリルのアンソロジー「テナント/恐怖を借りた男」もう誰も信じられない
キーワード「人間不信」
異常心理映画の巨匠ロマン・ポランスキーの劇場未公開作
映画には、作り手自身の物の考え方や実体験が大なり小なり反映されるものだ。その点においてロマン・ポランスキーほど、作品と実人生を重ね合わせて語られるフィルムメーカーは他にいないだろう。
1933年、ユダヤ系ポーランド人の家系に生まれたポランスキーは、第二次世界大戦中にナチス・ドイツのホロコーストに巻き込まれ、両親を強制収容所に送られた揚げ句、自らも流転のサバイバル生活を強いられた。ヨーロッパとハリウッドで数多くの名作を世に送り出したポランスキーの特異な作風は、この幼少期の悲惨なトラウマに根ざしているとされる。
ホロコーストの悲劇に真正面から向き合った代表作「戦場のピアニスト」(2002年)は言うに及ばず、ある混乱した状況の中で周囲から孤立した主人公が破滅的な運命をたどっていくというプロットは、多くのポランスキー作品に共通している。とりわけ顕著なのは、筆者が勝手に〝人間不信3部作〟と呼んでいる「反撥」(65年)、「ローズマリーの赤ちゃん」(68年)、「テナント/恐怖を借りた男」(76年)だ。今回の本コラムでは、日本では劇場未公開となったサイコ・スリラー「テナント/恐怖を借りた男」を掘り下げたい。
%201976%20Marianne%20Productions.%20All%20Rights%20Reserved.%20TM%2C%20(R)%20%26%20(C)%202015%20BY%20PARAMOUNT%20PICTURES.%20ALL%20RIGHTS%20RESERVED..jpg)
いわく付きアパートで孤立し、被害妄想にとらわれる異邦人の悪夢
パリの建築事務所で働くポーランド人のトレルコフスキー(ポランスキー)が、とある古めかしいアパートの賃貸契約を希望する。ところが無愛想な管理人(シェリー・ウィンタース)に案内されたのは、前の住人のシモーヌという若い女性が窓から投身自殺を図ったいわく付きの部屋だった。
まもなく入院中のシモーヌが他界したことで、トレルコフスキーは部屋を借りることができたが、階下に住む年老いた大家(メルビン・ダグラス)や古株の住人たちから相次いで理不尽なクレームを受けるはめに。じわじわと精神的に追いつめられたトレルコフスキーは誰も信じられなくなり、現実と悪夢のはざまでもがき苦しんでいく……。
原作はローラン・トポールの小説「幻の下宿人」。当初は「回転」(61年)、「華麗なるギャツビー」(74年)などで知られるジャック・クレイトンがメガホンを取る予定だったが、ポランスキーがこの企画に興味を示したことで監督が交代。さらにポランスキーが主演の兼任を買って出たことで、なおさら彼〝らしさ〟が濃縮された異常心理ドラマとなった。
トレルコフスキーは内向的で気が弱い男だ。そんなトレルコフスキーが意地悪な大家や住人からイチャモンをつけられる前半は、一種の〝隣人トラブルもの〟のように進行していく。ところが部屋の壁にぽっかりと開いた穴から人間の歯が見つかったり、アパートの向かいの棟のトイレに立っている何者かが夜な夜なこちらを凝視していたりと、奇怪な出来事が続発。こうした怪談じみた展開によって、かねて外国人ゆえに疎外感を感じていたトレルコフスキーは、隣人たちの悪意にさいなまれ、自分がよってたかって迫害されているという被害妄想をふくらませていくのだ。
%201976%20Marianne%20Productions.%20All%20Rights%20Reserved.%20TM%2C%20(R)%20%26%20(C)%202015%20BY%20PARAMOUNT%20PICTURES.%20ALL%20RIGHTS%20RESERVED..jpg)
あの手この手で執拗に映像化されたカフカ的な不条理
隣人への不信から始まる本作は「ローズマリーの赤ちゃん」と極めて似た筋立てなのだが、ノリノリで自作自演に挑んだポランスキーは、トレルコフスキーが前住人のシモーヌの境遇に我が身を重ね、身も心も彼女になりきっていく様を倒錯的な女装シーンも交えて怪演した。
もともとポランスキーは「吸血鬼」(67年)や「チャイナタウン」(74年)で個性派俳優ぶりを披露していたが、本作では滑稽(こっけい)なほど生々しく人間の不安ともろさを体現。最終的に本作は、オカルト風のオチがついた「ローズマリーの赤ちゃん」とは異なり、最後まですべては主人公の強迫観念と妄想の産物だったという解釈が可能な作品となった。スベン・ニクビストの不安定に揺れるカメラワーク、フィリップ・サルドの不穏なムードを醸し出す音楽も、ポランスキーが志向したカフカ的な不条理感を増幅させる。
トレルコフスキーがシモーヌの友人ステラ(イザベル・アジャーニ)と映画館に入るシーンも忘れがたい。なぜかステラは「燃えよドラゴン」(73年)を見ながら激しく欲情し、トレルコフスキーも彼女の体をまさぐるのだが、その後、彼はステラを肉体的に愛することができない。この奇妙なエピソードからは、トレルコフスキーの内なる性的な抑圧が読み取れる。さらにアパートの近くのカフェのマスターが、ゴロワーズの愛煙家であるトレルコフスキーにシモーヌが吸っていたマルボロを執拗(しつよう)に勧める逸話もブラックなユーモアをまきちらす。
最新作「オフィサー・アンド・スパイ」でも鬼才の〝らしさ〟は健在!
ポランスキーの長編9本目にあたる本作は、「チャイナタウン」(74年)と「テス」(79年)という2本の傑作の間に作られたが、それ以降もポランスキーは一貫した視点で映画を撮り続けている。80代半ばにして発表した最新作「オフィサー・アンド・スパイ」(2019年、日本では22年6月3日公開)は、19世紀末のフランスを震撼(しんかん)させた有名な冤罪(えんざい)事件の映画化。ここでも真実を探ろうとした主人公の陸軍中佐ピカール(ジャン・デュジャルダン)が国家権力に迫害され、なすすべもなく孤立していく姿が冷徹なサスペンス演出で描かれている。ホラーやスリラーのみならず、人間ドラマだろうと、歴史劇だろうと、ポランスキーの映画には常に人間不信の暗い影が差している。

NBCユニバーサル・エンターテイメントからDVD発売中。1572円

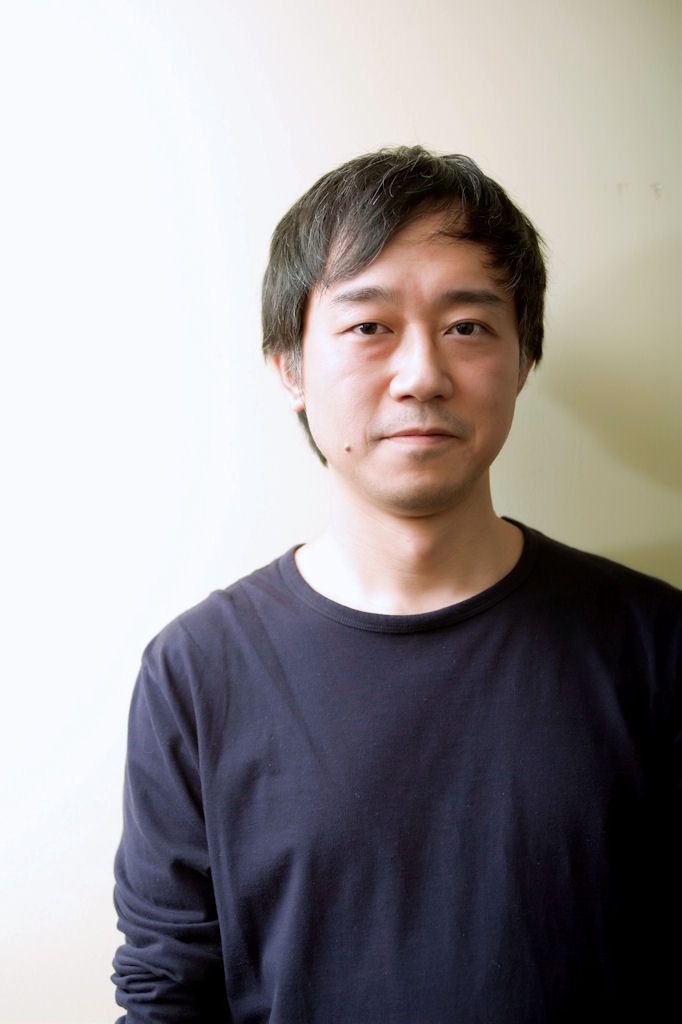
%201976%20Marianne%20Productions.%20All%20Rights%20Reserved.%20TM%2C%20(R)%20%26%20(C)%202015%20BY%20PARAMOUNT%20PICTURES.%20ALL%20RIGHTS%20RESERVED..jpg)




