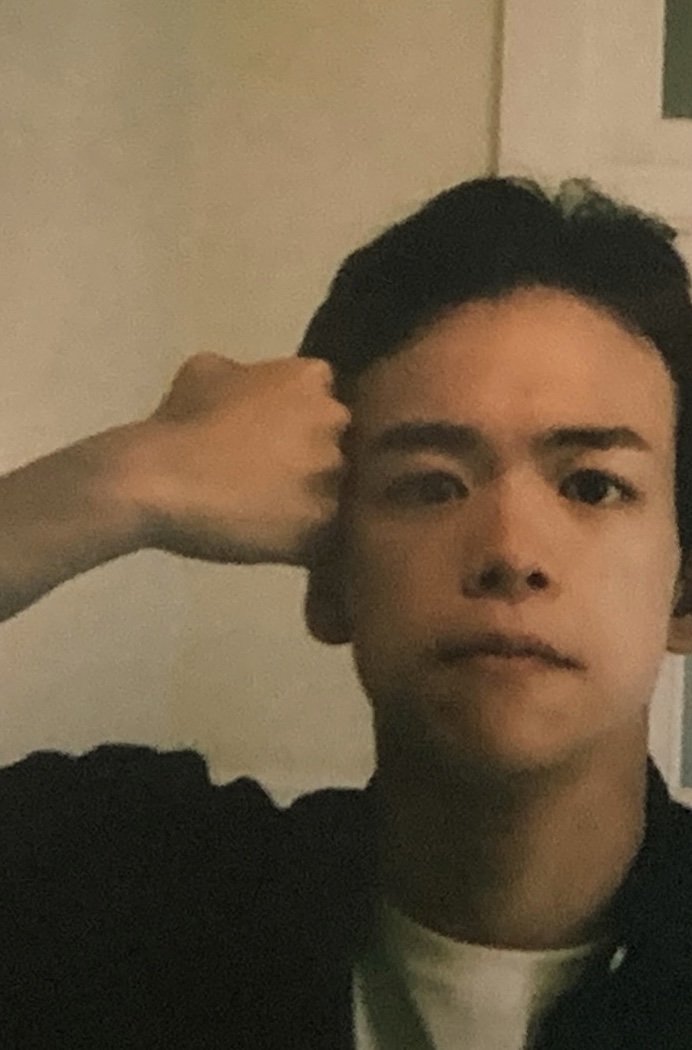いつでもどこでも映画が見られる動画配信サービス。便利だけれど、あまりにも作品数が多すぎて、どれを見たらいいか迷うばかり。目利きの映画ライターが、実り豊かな森の中からお薦めの作品を選びます。案内人は、須永貴子、大野友嘉子、梅山富美子の3人に加え、各ジャンルの精鋭たちが不定期で寄稿します。
「忍びの家 House of Ninjas」より © 2024 Netflix,Inc.
2024.2.24
賀来賢人が主演・製作 超人忍者のアクションと家族 「忍びの家」:オンラインの森
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言のさなか、仕事がストップした俳優・賀来賢人は、ドラマ「死にたい夜にかぎって」(2020年)で協働した監督・村尾嘉昭とのZoom飲みの席で「時間があるのだから何か作ろう」と思い立つ。ミーティングを重ねて選び取られた題材は「忍者」と「家族」。
同年秋に俳優・脚本家の今井隆文の手を借りて仕上げた20ページの企画書がNetflixに持ち込まれ、半年後には日本文化に精通した米国人監督デイブ・ボイルによって120ページに拡張、ゴーサインを勝ち取る。主演兼共同エグゼクティブプロデューサーとしても賀来が携わるかたちで製作が進められ、撮影は主に22年夏から翌年3月に半年以上かけて行われた。完成までに3年半を要した配信中のシリーズ「忍びの家 House of Ninjas」(全8話)である。
服部半蔵の末裔一家
内容を紹介する前に、タイトルに目を留めてみよう。英題は「House of Ninjas」なのに日本語題は「忍びの家」。しかも、第5話にはこんなセリフもある。「(忍者ではなく)〝忍び〟だ。何も知らん愚かな連中が忍者と呼ぶのさ」。どうやら作り手は「Ninja」の語が連想させる「ニンジャ映画」とは距離を取りたいらしい。キテレツ日本描写の一環としての「ニンジャ」ではなく、現代に生きるリアル志向の忍者、否「忍び」を描こうとする意志が感じられるのだ。
というわけで、本作で描かれるのは現代日本に生きる忍者、服部半蔵の末裔(まつえい)である俵一家の物語である。賀来が主演として次男・晴(ハル)を演じているが、真の主役は「家族」だ。

忍者家業から足を洗ったものの
第1話は、夜のコンテナヤードと船上で、数人の忍者による激闘で始まる。セリフはわずかで無駄な説明は一切ない。めまぐるしい開幕部分の終盤に映される水に沈む人影と、名前を呼ぶ叫びから、おぼろげに何者かの死が想定される。画面は、巨大な屋敷、壁に掛けられた忍装束4着、重々しく扉を閉じる人物のシルエット、と続いて──ここでタイトル。
タイトルシークエンス(少し007調に思える)を挟んで映し出されるのは、ありふれた日常の風景である。自動販売機補充の仕事に従事する晴は、深夜の牛丼屋で見かける常連の女性客が気になっている。父・壮一(江口洋介)は、酒蔵の経営難に頭を抱えている。母・陽子(木村多江)は専業主婦。長女・凪(蒔田彩珠)は大学生、三男・陸(番家天嵩)は小学生。祖母・タキ(宮本信子)は縁側で黒猫をなでている。しかし仏壇の遺影に長男・岳(高良健吾)の顔が見えて、ようやく察しがつく。冒頭の忍者は彼らで、長男の死によって忍者家業から足を洗ったのだ、と。
不審な船舶転覆事故をきっかけに国家秘密組織「忍者管理局」が彼らの現役復帰を命じ、晴は抵抗しながらも闘いに巻き込まれていく。俵一家と敵対する忍びの一族との因縁が明かされ、陰謀が進行する一方で、家族それぞれが抱えた問題も8話の中で一つ一つ展開されていく。忍者活劇の妙味を出しつつ、じっくりと一家全員の移ろいを見せてゆくのである。

ガジェットも銃も使わず、武器は肉体と忍術
ところで忍者は、現実的に描けば描くほど、スパイに近づいてしまう。荒唐無稽(むけい)な忍術を封じれば、必然的に展開は尾行や潜入などの隠密行動に偏ることになるからだ。しかし本作では、だからこそ「忍者は忍者」であること、「スパイになっては、絶対にいけない」ことが目指されてもいたという。
その結果だろう、「007」や「ミッション:インポッシブル」に登場するような最新技術によるガジェットは登場せず、それどころか銃すら用いない。高い壁はカギ縄で上り、敵は体術か刀で倒し、困ったときは煙幕に頼る。リアルな描写を心掛けていながら、撃てば済むという状況で銃を描かずにおく選択は、ともすれば説得力を失うことになりかねないが、入念な体作りとリハーサルによって作り込まれた体技がそうと感じさせない。主演の賀来は、撮影半年前からトレーニングを始めたというが、その肉体を見せびらかすような場面がほぼないのも好感が持てる。

肉、酒、セックス厳禁 忍びはつらいよ
放っておけばおのずとスパイに近づいていってしまう題材をどう描くか、という課題に対する工夫のなかで、最もユニークなのは忍者特有のルールを強調した点かもしれない。忍者は、肉を食べてはいけない(匂いで見つかってしまうから)、酒を飲んではいけない、恋人を作ってはいけない、セックスをしてはいけない……という、地味ながらつらそうな、実際に存在していた(ボイル監督談)鉄の掟(おきて)だ。劇中でも、律義にそれぞれのルールに対応する小さな葛藤や諦めが描かれる。
忍者になると誓った末弟は好物のハンバーガーを禁じられ、同級生の男子に告白された長女は「規則だから」断らねばならないし、父は妻の帰りが遅くともヤケ酒を飲むことができない。唯一、主人公がルールを承知していながら、えいやとばかりに接吻(せっぷん)したりするのもおかしい。長男の不在を絶えず中心に抱える重々しい物語になりそうななかで、こうした独自の発想が貴重な笑いどころとして随所で「軽さ」の支えになっている。

筋金入りの日本びいき 監督デイブ・ボイル
最後に、監督のデイブ・ボイルについて紹介しておこう。19歳のときモルモン教の宣教師として赴任し、日本人コミュニティーでボランティア活動に携わるなかで日本語を学び、のちにアメリカに帰国すると大学で改めて日本語を専攻した筋金入りで、本作の現場も日本語で取り仕切った(!)という。
長編初監督作は06年の「Big Dreams Little Tokyo」で、ポスターを眺めると日本公開されていないのに「ビッグ・ドリームズ・リトル・東京」「ボイル監督作品」の文字が見えるあたりも愉快な日本題材のコメディー映画。同作はボイル自身が主演も務めており、日本語も披露しているので、気になる方は調べてみてほしい(監督が自身のVimeoアカウントで公開している)。
その後の作品も日本要素は途切れず続き、09年には在米日本人家族を描いた「ホワイト・オン・ライス」(日本盤DVDあり)、日系アメリカ人ミュージシャンのゴウ・ナカムラを主演に迎えた「Surrogate Valentine」(11年)と「Daylight Savings」(12年)を経て、14年には藤谷文子と北村一輝がサンフランシスコで出会う犯罪映画「Man from Reno」(Amazon Prime にて配信あり)を撮りあげた。通して見てゆくと「コメディーには向いていないと気付いた」と告白するボイルの、喜劇からシリアスな題材へと興味を移していく変遷が面白いのだが、むしろシリアスさのなかに喜劇性を織り込むようになったようにも見え、最新作「忍びの家」もその結実と言えるかもしれない。
「忍びの家House of Ninjas」はNetflixで独占配信中。