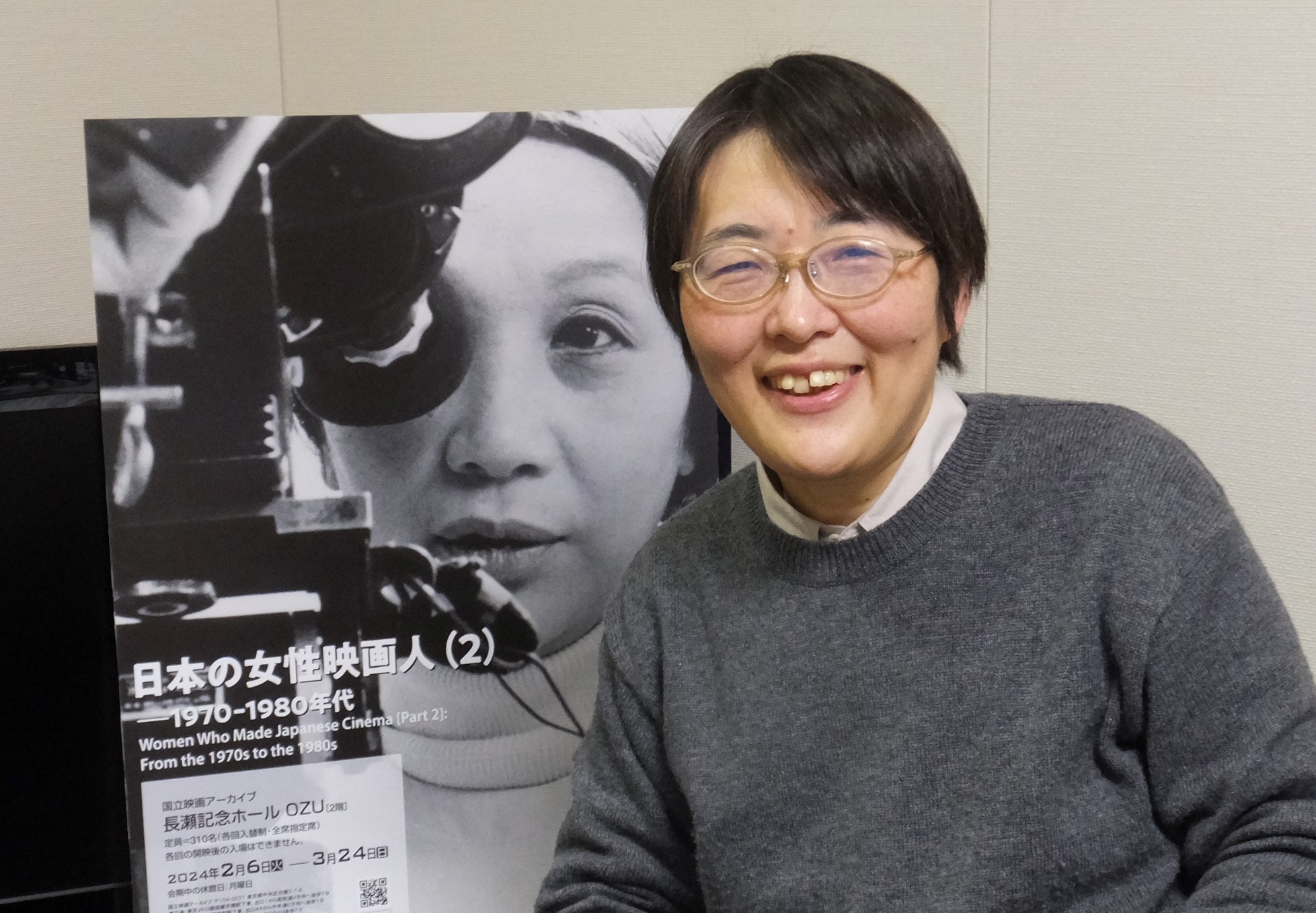「男性映画」とは言わないのに「女性映画」、なんかヘン。しかし長年男性支配が続いていた映画製作現場にも、最近は女性スタッフが増え、女性監督の活躍も目立ち始めてきました。長く男性に支配されてきた映画界で、女性がどう息づいてきたのか、女性の視点や感性で映画や社会を見たらどうなるか。毎日新聞映画記者の鈴木隆が、さまざまな女性映画人やその仕事を検証します。映画の新たな側面が、見えてきそうです。
「日本の女性映画人(2)1970-1980年代」について語る森宗厚子・国立映画アーカイブ特定研究員=鈴木隆撮影
2024.2.17
揺れる映画界で翼を広げ 台頭した女性たち「新たな視点で作品見る楽しさを」 「日本の女性映画人(2)1970-1980年代」を読み解く
東京・京橋の国立映画アーカイブで開催中の特集上映「日本の女性映画人(2)1970-1980年代」。日本の映画界で女性映画人がはたしてきた功績を検証する大型企画の第2弾で、47プログラム74作品が上映中だ(3月24日まで)。撮影所体制が揺らぐ中で監督、脚本、技術スタッフ、プロデュースなど多彩な分野で女性の進出が顕著になり、映画界に変革をもたらした時代。日本映画史全体を問い直そうとする特集の意図は明確だ。特集上映の企画担当者、森宗厚子・特定研究員の解説とともに考えたい。

国立映画アーカイブ「日本の女性映画人(2)1970―1980年代」
森宗厚子・日本映画アーカイブ特定研究員 体系的な考察と正当な評価を
2023年の同時期に開催した「日本の女性映画人(1)無声映画期から1960年代まで」に続く企画である。#Metoo運動以降、映画界と女性とのかかわりへの関心も高まったが、女性映画人の足跡、役割を体系的かつ網羅的に研究、考察し、正当に評価する書籍、特集上映などが少なかったことも背景にある。
第1弾では、日本初の女性監督の坂根田鶴子や女優から監督になった田中絹代をはじめ、無声映画期から定着した結髪、トーキー以降進出したスクリプター、脚本、美術、文化・記録映画など多彩な分野で仕事を始めたパイオニア的な女性映画人、職域を多く取り上げた。しかしこの時期は「女性映画人の仕事が軽んじられ、可視化されていなかった時代でもあった」という。女性映画人=女性監督、せいぜい女性脚本家といった図式もあり、これまで評価されてこなかった映画のジャンル、職種をクローズアップするのも目的の一つになっている。
観客にも目配りした。「女性映画祭などの観客、参加者の大半が女性で関心の広がりも限定された過去の傾向」を踏まえ、「男性ファンの関心の高い作品も意識して、戦争映画や特撮ものも取り込んだ。女性問題をテーマにした作品に限定せず、映画として面白いものをプログラミングした」と話した。

「遠い一本の道」日本の女性映画人=国立映画アーカイブ提供
左幸子、宮城まり子、栗崎碧……女優が独立プロ設立
上映作品の中から、特に注目すべき作品や女性映画人を具体的に見ていこう。70年代になると従来の撮影所体制が大きく揺らぎ始める。撮影所体制の衰退期、停滞期に映画業界全体が変革を迫られ、女性は60年代以前とは別の形で進出していった。
独立プロの映画が盛んに撮られるのと並行して、女優がプロダクションを作り自らプロデューサー、監督になって撮りたいものをのびのびと撮った。田中絹代が監督をしていた時代と異なり、撮影所の路線などに関係なく自身の世界を構築した。大手映画会社を去った大島渚や吉田喜重両監督らによる独立プロ製作が隆盛だった背景もあったという。
左幸子は国鉄労組の協力で保線作業員の家族のドラマ「遠い一本の道」(77年)を作り、宮城まり子は自らが設立した肢体不自由児などの養護施設「ねむの木学園」を舞台に「ねむの木の詩がきこえる」(77年)など4作を製作。社会的なテーマや運動に根差した題材で脚光を浴びた。また、栗崎碧も人形浄瑠璃を映画化した「曽根崎心中」(81年)を監督し、いずれも高い評価を受けた。

「ねむの木の詩がきこえる」日本の女性映画人=国立映画アーカイブ提供
撮影所の超一流スタッフが結集
この3人の作品にはさらに大きな特徴があった。「作品の撮影や美術、照明などのスタッフに日本映画界の重鎮の名前が並び、当時の映画界の実情が浮かび上がってきた」というのだ。宮城作品の撮影は、川島雄三監督、豊田四郎監督作品などを多く手がけた岡崎宏三が担当した。宮城監督の依頼を受け、子供たちを同情的な目で見るのではなく、ソフトフォーカスで天使のようにかわいらしく撮り上げた。「ねむの木の詩がきこえる」には照明のベテラン下村一夫も参加し、技術面でも高度なテクニックを駆使した。
「遠い一本の道」ではドキュメンタリー映画の重鎮である瀬川順一撮影監督が参加。「曽根崎心中」では撮影の宮川一夫、美術の内藤昭と大映の大ベテラン、80年代以降の黒澤明作品の照明を担当した佐野武治も加わり超一流の技術スタッフがそろった。
「女優出身の監督の作品に撮影所を知りつくし高度な技術を持つスタッフが組んだスタイルで、レベルの高い独創的な作品を生み出した。日本映画の興行が厳しく、テレビに押されていた時代でもあるが、ベテランの究極的な技術が十分に発揮されたともいえる」と話した。撮影所の衰退などでベテランが腕を振るう現場が限られていた時期に、ユニークな企画に参加して才能を発揮した。
青春、犯罪、アクション……ジャンルも多彩な脚本
60年代までの女性脚本家としてすぐに名前が挙がるのは水木洋子であり田中澄江だろう。当時量産された文芸映画で実力をいかんなく発揮していた。70年代に入ると文芸映画の勢いは衰えたものの、青春映画や犯罪、アクションもの、時代劇など多彩なジャンルに女性脚本家の活躍の場が広がった。「女性監督が撮影所から独立した一方、女性脚本家は変動する撮影所の中で、娯楽映画を中心に活躍の場を広げた。対比的だ。既存の脚本家がテレビに移ったこともあって、女性の新進脚本家が台頭した」
「その人は女教師」(70年)の宮内婦貴子、「二十歳の原点」(73年)、「泥の河」(81年)の重森孝子らは若者向け映画を多く手がけた。日活のスクリプターから脚本家に転じた服部佳(服部佳子名義も)は、「新座頭市物語 笠間の血祭り」(73年)など時代劇で才能を開花させた。青春映画としても評価された「沖田総司」(74年)でフレッシュな沖田を創り上げた大野靖子は、テレビでデビューして映画に進出、大河ドラマや大作映画にもかかわった。
高山由紀子は「メカゴジラの逆襲」(75年)で、シリーズ初の女性脚本家になった。多彩な作品を書き、監督デビューも果たしている。女性脚本家が描く映画の幅は一気に拡大した。鹿水晶子や木村智美は日活ロマンポルノを多作し、筒井ともみ、那須真知子らも盛んに脚本を執筆した。女性脚本家の現代に至る足場が、この時代に築かれていった。

「 黒い雨」=国立映画アーカイブ提供
ピンク映画を才能のゆりかごに 国映・佐藤啓子
製作では、国映の佐藤啓子(クレジットは朝倉大介名義)に注目だ。ピンク映画の製作・配給・興行まで手がける会社で、磯村一路、周防正行両監督の初期の作品を上映。佐藤は若手監督の将来性に懸け、作家性の強い映画作りを尊重した。周防監督や瀬々敬久監督ら現在の日本映画界を背負う多くの監督たちを輩出した。「国映で50年以上にわたり1000本を超す成人映画を作り、若手に好きなように撮らせ、育てた功績はすごいの一言」と森宗も称賛する。
今村プロダクションで今村昌平監督作品をプロデューサーとして支えた飯野久の「黒い雨」(89年)も上映する。女性プロデューサーが監督と実生活でもパートナーであることも多かったが、飯野は職業人として携わった。「飯野さんは女性のプロデューサーが監督の家族ではなく、一つの仕事として、プロとして評価された先駆者でもある」として、その影響、貢献をたたえた。プロデューサーでは他に、原一男監督のパートナーでもある小林佐智子、岡本みね子、高野悦子、大林恭子、女優でもある原田美枝子らを取り上げる。
ドキュメンタリーでは羽田澄子監督とほぼ同時期に岩波映画製作所で活躍し、自主性を育てる幼児教育、地域医療や高齢者福祉に取り組んだ時枝俊江監督の作品を特集する。
異なる視点で映画史の再構築を
時代の流れの中で、映画界の状況を伝えるような人や作品を抽出した。「日本映画史上の作品として振り返る時に、毎日映画コンクールやキネマ旬報(の受賞作、受賞者)をたどって映画を知り、楽しむパターンもあるが、公開当時の評価にとらわれず女性映画人が手がけたものという視点でとらえ直すのも興味深い」。従来の日本映画史には欠けていた視点で映画を見る面白さを提唱する。
「女性映画人への視点は、既存の日本映画史を異なる角度から再構築することにつながる」と考えている。70~80年代の女性映画人の軌跡を追うことは、現代の日本映画界や作品を見る上で多大なヒントを与えてくれることも付け加えておきたい。いささか気が早いが、次の(?)〝90年代以降の女性映画人〟にも期待が膨らむ。