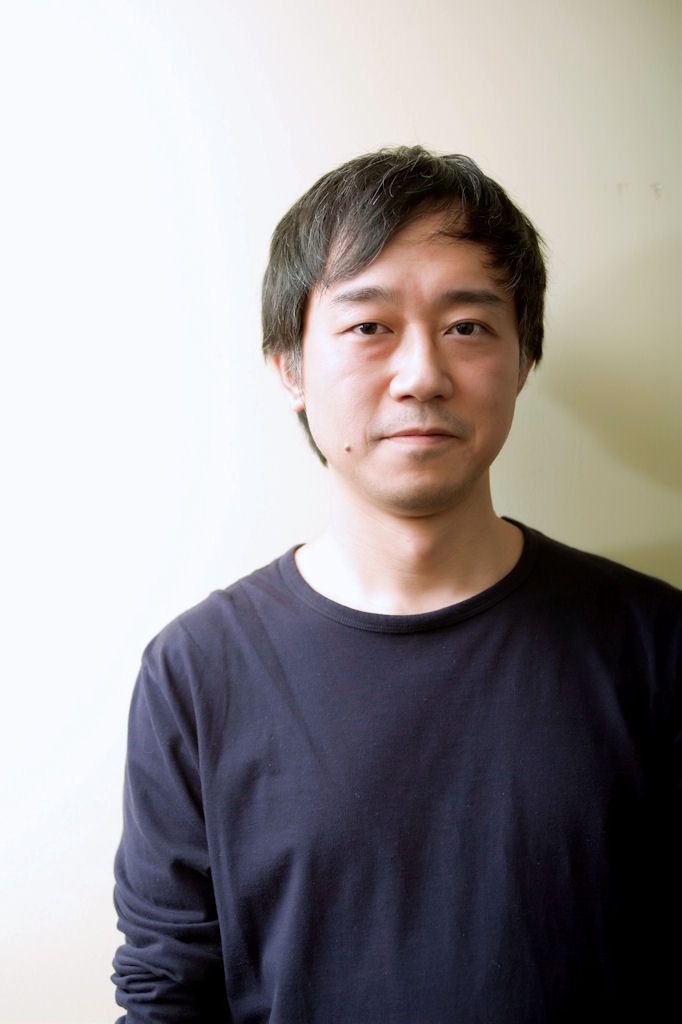ハラハラドキドキ、謎とスリルで魅惑するミステリー&サスペンス映画の世界。古今東西の名作の収集家、映画ライターの高橋諭治がキーワードから探ります。
「ラン・ラビット・ラン」© Sarah Enticknap Netflix
2023.7.25
〝不思議の国〟より恐ろしい アリスと白ウサギ「ラン・ラビット・ラン」:謎とスリルのアンソロジー
劇中に〝アリス〟という少女が登場し、〝白ウサギ〟をきっかけに世にも奇妙な物語が転がり出す。そう聞けば、誰もが「不思議の国のアリス」を想起するだろう。ところがオーストラリア発のNetflixオリジナル映画「ラン・ラビット・ラン」(2023年)には〝アリス〟も〝白ウサギ〟も出てくるのに、ルイス・キャロルの名作の映画化ではない。「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」など数多くのTVシリーズの演出を手がけてきたダイナ・リード監督が、同国の作家ハンナ・ケントのオリジナル脚本を基に撮り上げた恐怖劇である。

キーワード「逃れられない過去」
不妊治療医のシングルマザー、サラ(セーラ・スヌーク)が、一人娘ミア(リリー・ラトーレ)の7歳の誕生日パーティーを催す。その日、母子が暮らす一軒家には、どこからともなく1匹の白ウサギがさまよい込んできた。すると、翌日からミアがおかしな挙動を見せ始める。紙でこしらえたウサギのお面をかぶるようになり、一度も対面したことのない祖母のジョーン(グレタ・スカッキ)に「会いたい」と駄々をこねたかと思えば、なぜか「私はアリスよ」と言い出すのだった……。
ここまでの序盤だけでは、ストーリーの核心がどこにあるのか皆目見当がつかない。前回の本連載では「恐ろしい子供たち」をキーワードに、「ティン&ティナ -双子の祈り-」(23年)というスペイン映画を紹介したが、このオーストラリア映画も「恐ろしい子供」にまつわる話なのだろうか。

失踪した妹の名を名乗る7歳の娘
実はそうではない。いささかスローテンポで思わせぶりな映像世界を辛抱強く見進めていくと、恐怖の根源は娘のミアではなく、母親サラの〝心の中〟に隠されていることがわかってくる。ミアが突然口にした「アリス」は、幼い頃に失踪を遂げたサラの妹の名前だ。アリスの失踪をめぐってサラは母親ジョーンとの関係がギクシャクし、今は介護施設に収容されているジョーンとは長らく音信不通のまま。ごく最近、心の支えだった父アルバートを亡くした喪失感にもさいなまれているサラは、その後もミアの奇行に翻弄(ほんろう)され、封印していた自らのおぞましい過去と向き合うことになる。
アリス失踪事件の真実は終盤のフラッシュバックで映像化されるのだが、本作には最後まで解き明かされないいくつかの謎がちりばめられている。「私はアリスよ」と執拗(しつよう)に主張するミアの豹変(ひょうへん)は、まるで失踪時に同じ7歳だったアリスの霊が憑依(ひょうい)したかのようだが、ストーリー上は曖昧なままだ。さらに、序盤に母子のもとにやってきた白ウサギは、その後もしばしば意味ありげに画面に映し出されるが、ただそこに存在するだけで傍観者のように何もしない。

母親を追い詰める逃れられない過去
やがて後半、サラがミアを伴って忌まわしい生家を訪れると、前半から神経症的な演技を見せていた主演女優セーラ・スヌークのハイテンションな怪演がさく裂する。シングルマザーの孤独と不安、そして少女時代から引きずる罪の意識が混然一体となり、〝逃れられない過去〟が容赦なくサラを追いつめていく。
前述したように、ストーリーの核心がなかなか見えてこない本作は、オカルトものなのか、はたまたダークファンタジーなのか、ジャンルの区別すらしがたい作品だ。しかし現実と妄想、悪夢の境目が失われ、サラの内なる狂気がほとばしる後半はサイコホラーへとぐいぐい傾斜し、全編にわたって緻密な映像設計が施されていることに気づかされる。

希望の光なき物語
序盤から不穏な風が吹きつけ、異様なまでに暗く陰鬱なビジュアルのトーンは、サラの不安定な潜在意識を投影したものだろう。ワイドショットや俯瞰(ふかん)で撮られたオーストラリアの荒野、川、森などの風景も不吉なムードを醸し出し、そこにはサラがたぐり寄せるべき希望の光などどこにも見当たらない。
シングルマザーの精神不安をテーマにしたオーストラリアの恐怖映画といえば、ジェニファー・ケント監督の鮮烈な長編デビュー作「ババドック ~暗闇の魔物~」(14年)が思い起こされるが、ダイナ・リード監督はそれとはまったく異なる視点と様式の異常心理劇を完成させた。そして〝アリス〟と〝白ウサギ〟をフィーチャーした本作には、不気味な〝穴〟のイメージも盛り込まれている。人間の心というものの底知れない闇の深さをほのめかすそれは、ひょっとすると「不思議の国のアリス」にインスパイアされたサイコロジカルなメタファーなのだろうか。そんな想像もかき立てるオージーホラーなのだった。
「ラン・ラビット・ラン」はNetflixで独占配信中。