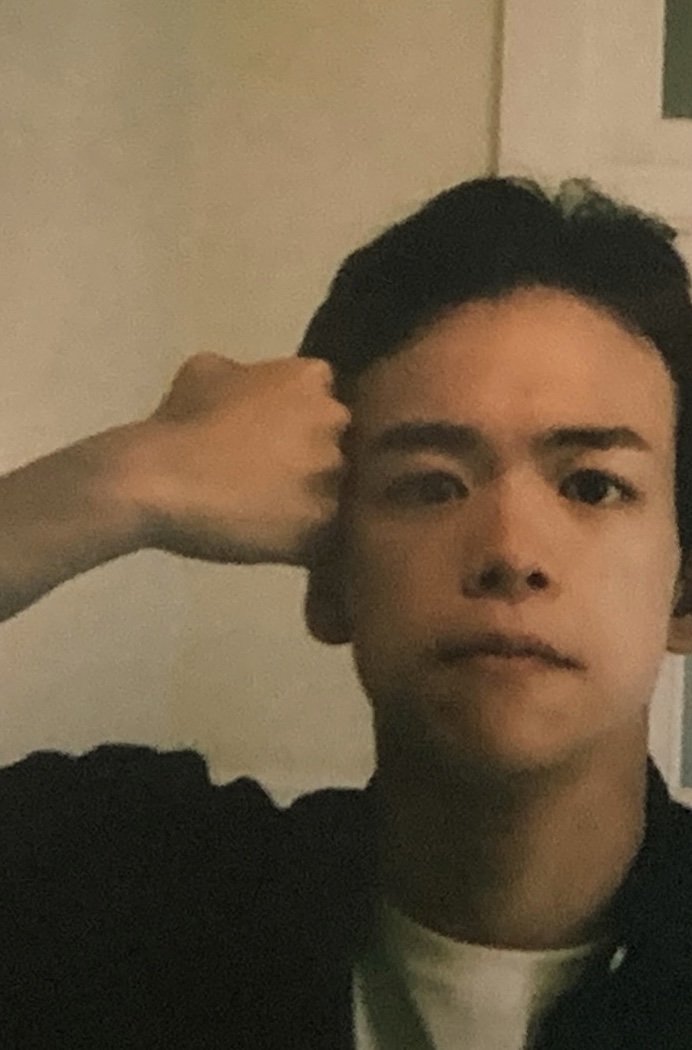毎回、勝手に〝2本立て〟形式で映画を並べてご紹介する。共通項といってもさまざまだが、本連載で作品を結びつけるのは〝ディテール〟である。ある映画を見て、無関係な作品の似ている場面を思い出す──そんな意義のないたのしさを大事にしたい。また、未知の併映作への思いがけぬ熱狂、再見がもたらす新鮮な驚きなど、2本立て特有の幸福な体験を呼び起こしたいという思惑もある。同じ上映に参加する気持ちで、ぜひ組み合わせを試していただけたらうれしい。
フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊 © 2022 20th Century Studios and TFD Productions LLC.
2022.5.01
勝手に2本立て:「フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊」 窓からひゅっと突然に
記憶にこびりつく唐突な行動
いささか不謹慎かもしれないが、映画における人体の〝落下〟に惹(ひ)かれてしまう。むろん、人体の落下といってもさまざまある──偶然なのか意図的なのか、どこから、どのように落ちるのか。ただ、どの落下にも共通しているのは、足が地を離れて身体が虚空に放たれた瞬間、もはや後戻りは利かず、終着点が分かっているその落下を、われわれはなすすべなく見つめ続けなければならないということだ。
バリエーション豊かな落下場面のなかでも、個人的にとりわけ鮮烈なのは、窓から突然、人物が飛び降りてしまうという状況である。同じ窓でも、市川崑の「穴」(1957年)における船越英二のように助走をつけ窓を突き破っての跳躍ならまだ心の準備もできようが、つい今しがたまで窓際で静かにたたずんでいた人物が画面下方へたちまち姿を消す──それはあまりに唐突で、予期せぬ行動ゆえ、驚く準備すらもできぬまま、あっけにとられるほかない。場面を見終えた刹那(せつな)、すでに人物が窓から飛び降りてしまったのだという事態は把握できているはずであるのに、どこか「いま、何が起きたんだ」という思考が湧き起こり、いやおうなく場面の記憶が脳裏にこびりつく。
ウェス・アンダーソン監督の第10作
ある架空雑誌の最終号に焦点を当て、三つの掲載記事をオムニバスふうに映像化してみせるウェス・アンダーソンの長編第10作「フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊」(2021年)を見たときに、そんな思いもよらぬ瞬間が訪れるとは、例によってまったく予想できなかった。
名を伏せても、たちどころに誰の作品か分かってしまう……そんな形式主義的スタイルをこれまで貫徹してきたアンダーソンにあって、本作は豊かな例外的〝逸脱〟までも内包しているという点で、新境地といって差し支えない一作なのだが、作品そのものに触れる余裕はないので、まだの方はぜひ見てほしい。
肝心の投身は、五月革命をほうふつとさせる60年代学生運動の顚末(てんまつ)が語られる第2部「宣言書の改訂」で起こるが、それは徴兵ののち脱走兵となった若者が5年後に書いた戯曲の一幕としてであり、あくまで一挿話、物語に直接的な影響を及ぼすことはない。
夜の兵舎で若き兵士たちが語らう──もし戦争が終わったら、どうする? 彼らはひとりひとり、自嘲気味に将来の予想図を描いて披露していく。家業を継ぐ者、放浪を決めている者など、生き方はさまざまだが、一様ににじむのは諦観だ。
あっけないがゆえに考え続けてしまう
そもそも、ぶじに帰れる保証はない。全員にはたして将来が用意されているかどうか。あくまで目先の過酷な現実=戦争から目をそらすための、なかば現実逃避としての寝しなの会話。そんななかで最後に促されて口を開くのが、眼鏡の青年モリゾである。周囲の言によれば「地球化学の教授」を目指していたらしい聡明(そうめい)な彼は、いまや完全に絶望の淵にいる。2段ベッドの上段に腰掛けていた彼は、壁面の窓を開け、眼鏡を外して、ためらうことなく、ひゅるりと飛び降りる。
この場面はあまりにあっけない。前述の通り挿話にすぎないから、青年が飛び降り、兵士仲間たちが窓から下を見下ろし「動かない」とうろたえたあと、話は〝本筋〟に戻ってしまう。しかし、むしろそれゆえに場面から解放されず、考え続けてしまうのだろう。
引き続き画面を見つめながら、窓から飛び降りる眼鏡の子供という共通項から思い浮かべたのは「左利きの女」(77年)だった。監督はペーター・ハントケ、数年前にノーベル文学賞を受賞したことも記憶に新しい作家だが、映画好きにはビム・ベンダース監督作の脚本としてなじまれているかもしれない。この映画は、ベンダースが製作し、みずからのなじみのスタッフをそのまま貸し出し、盟友に撮らせた初監督作である。

「左利きの女」 © 1977 Reverse Angle Library Gmbh
「左利きの女」飛び降りたのは誰だ
「啓示を受けた」という理由で、ある女が夫を捨てる。ふたりには子供がひとり。男は出ていき、家には女=母と子供がふたりで暮らすことになる。飛び降りるのはこの子供だ。特段、前触れもなければ、動機もわからない。
あたりが闇に包まれているなか、画面は2階建ての家を映している。1階の窓辺には手すりにもたれて外をうかがうシルエット、そしてすぐ上の2階窓ではブラインドが開いて人物が窓格子に足をかけ、そろりと飛び降りる。あまりに周囲が暗いので室内光で潰れて両名の顔は見えない……あれ、なにかがおかしくはないか。
落ちたの、誰だ? 筋書きは家庭不和、じっさい主要人物は基本的に家族3人(しかも住んでいるのは2階建ての家)とくれば、落下する小柄なシルエットに子供の存在を当てはめるのも致し方なかろうが、このたび見直したことでつじつまが合わないことに気がついた。落ちたのは、子どもでなかったのだ。
もともと落下場面直後にピンピンした姿で子供が登場するのが不思議だった──2階から飛び降りて、そう無傷で済むものではあるまい──が、初見時は「きっと、夫婦不和に挟まれた不安心象の表現なのだろう」と身勝手に合点したらしい。何も見えていなかったのだ。しかし目を凝らせば、そもそもこの家が主人公たちのものでないことは、窓の形状、格子の模様などから明白なものとなる。誰が落ちたのかはわからない。
ハリウッド文法を逸脱した編集
しかも興味深いのが、この場面の存在を忘れたころの終盤に、ほとんど同じショットが登場することだ。辺りは闇、2階建て、上下階の窓際には人影があり、姿勢まで全く同じ。唯一異なるのは、この家の前を主人公の女が通り過ぎる描写があること、そして2階の人物が飛び降りないことだが、人物の様子などが明らかに先立つショットと共通しているので、思うに、もともとは〝この後〟飛び降りるというショットだったのではないか。それが編集で分割され、前後関係が無視されて、のちの落下が中盤に、落下前が終盤に配置されたのではないか。あくまで想像に過ぎないが、こんな気づきもまた再見の効用である。
本作の編集はきわめて特異で、いわゆるハリウッド映画文法から隔たった確固たるスタイルを持っている。ショットとショットが円滑につながらない、断絶と分離が印象づけられるカッティングである。これもまたひとつの〝逸脱〟であり、「フレンチ・ディスパッチ」の記憶と戯れながらほのかに響き合うだろう。
「フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊 」はU-NEXTで配信中。「左利きの女」は、U-NEXTで見放題配信中。