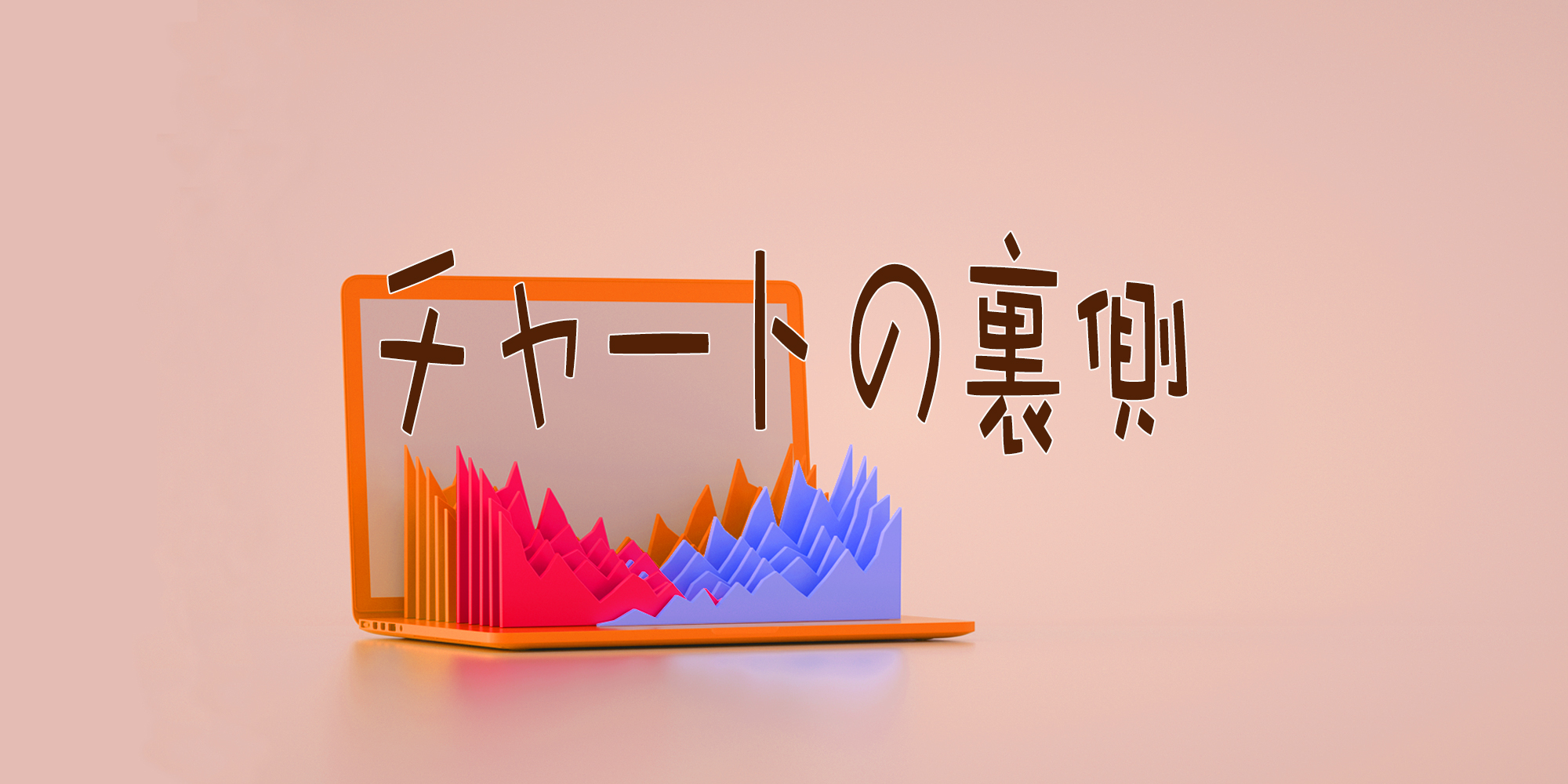公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。
「366日」©︎2025映画「366⽇」製作委員会
2025.2.10
2週連続で前週超え、公開4週目で1位! 「366日」驚きのヒットの背景にある〝古めかしさ〟と〝共感度〟
ここ最近、意表をつく邦画ヒットが増えてきた。個人的に「サプライズヒット」と呼んでいる。今年に入って公開された作品では、有名な楽曲をモチーフにした「366日」が、その一本だ。公開が進むにつれて、動員が上向いていった。落ちが少ない作品はときどきあるのだが、動員が上がっていく作品はめったにない。それも、その期間が結構長い。かつて、米アカデミー賞で作品賞などを受賞した公開中の作品の数字が上がっていくことはあったが、それはもはや過去の話である。
公開5日目、初日上回る興収
興行の推移を、ちょっと整理してみよう。「366日」の公開は2025年1月10日。その週末(10~12日)の興行ランキング(入場人員)では第6位と、同時公開の新作「劇映画 孤独のグルメ」に先を越された。明らかに様子が変わったのは、14日火曜日だ。何と公開初日、10日の興行収入を上回ったのである。めったにあることではない。2週目(17~19日)が、またすごかった。1週目の約135%の興収になったのである。19日の時点で、「劇映画 孤独のグルメ」の興収を超え、5億6000万円を記録した。
快進撃は続く。3週目の週末(24~26日)では、2週目の約119%の興収になった。2週連続で、前の週末成績を超えたわけだ。27日には、早くも10億円を突破してしまった。4週目(1月31日~2月2日)には、さらに異変が起きた。3週目の93%の興収となり、伸び率は落ちたものの、興行ランキング(入場人員)では第1位を獲得してしまった。公開4週目での大快挙である。2日時点の興収は、13億7000万円まで伸びた。20億円到達がほぼ確定したとのことである。
以上のような推移から、「366日」のまれな興行の伸びは、映画を見た人がその良さをSNSなどで発信して、それが広く伝わり、興行に跳ね返ったことがわかる。もはや、その広がり方はここで指摘するまでもないが、注目してほしいことがある。この作品は、宣伝などからでは、最近結構目立つ若者の恋愛ものと、それほど違った印象がなかったことだ。オリジナルだが、かつてテレビドラマにも、映画とは内容が全く違う同名の「366日」があった。その印象を映画「366日」と混同した向きもあり、スタート時の興行の足かせになったのではないかと言う映画関係者もいた。
観客が興行側の見立てを超えて「発見」
映画では、上映の規模というものが大事だ。1日に何回上映され、どのくらいの座席数をもつスクリーンで上映されるか。「366日」は大作ではない。「普通の恋愛もの」といった体裁が、興行側の映画の「規模感」を限定的にした面もあったかもしれない。そのような点を踏まえると、この作品のクチコミの広がり方というのは、他作品にも増して、観客の熱量の度合いが強い。アニメーションのキャラクターや実写映画の俳優などを推す「推し活」といった形ではなく、純粋に作品に感動しての発信力と見える。まさに、観客が「発見」した作品と呼んでいいのではないか。
「普通の恋愛もの」なら、クチコミがここまで広がることはなかっただろう。では、「普通の恋愛もの」と一線を画したのはどの点だったのか。それは、恋愛ものという定型から逸脱しないままに、ありえないような世界、いわば「禁断の世界」に飛躍できたことが大きい気がした。2人の男女の恋愛の当事者はもとより、周りにいる人たちも含めて、皆心根が優しい。相手のことを思う。人のことを思う。その描写が、ちょっと尋常ではないほど登場人物たちに徹底されていて、それが映画の中心軸になっている。感動は大方、そこから引き起こされる。
若い人たちは今、さまざまな領域にわたる殺伐たる時代風潮の暴風に、非常に敏感になっていると感じる。本作には、そのような厳しい時代、世界をひととき忘れさせる涼風のような、心が洗われるような精神が積み込まれていたのかもしれない。「366日」は、若い人たちの心の奥底にあるピュアな心持ちをつかまえ、導き出し、スクリーンに投影してくれたようにも思えてきた。深く、複雑な観客の受容のメカニズム(興行のダイナミズム)が、本作にはぎっしりと詰まっていると言うべきだろう。

クチコミ基盤が常態に
ここで少し話を変えて、「366日」と比較してみるためにも、冒頭で述べた「サプライズヒット」の作品を挙げてみよう。一昨年からでは、「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」(32億2000万円、「真生版」含む)、「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」(45億4000万円)、「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」(116億4000万円)、「変な家」(50億7000万円)、「ラストマイル」(59億6000万円)、「はたらく細胞」(60億円超見込み)などが並ぶ(以上、公開順)。今羅列すれば、違和感はないかもしれないが、公開前では、先のような成績は全く予想されていなかった。本当に、驚きの数字なのである。
すべての作品に共通するのが、見た人がネットやSNSなどで発信し、その好反応に動かされた多くの人たちが映画館に足を運ぶというパターンだろう。もちろん、伝播(でんぱ)の形は作品ごとに違うし、情報の受け取り方も千差万別だ。別の要素から、映画館を訪れた人たちも多いことだろう。そこを押さえつつ、ここ数年の多くのヒットのパターンが、クチコミを基盤にしているのは間違いない。
知らない世界に見いだした切実さ
その上で、ある共通点も見いだすことができる。若い層の集客が多いヒット作品のなかに、古く感じられる舞台設定の作品が散見されることだ。若い観客からすれば、初めて接するかのような時代の話にも見えるが、それが逆に新鮮に映ったとも言える。横溝正史的な戦後のおどろおどろしい世界を描く「鬼太郎誕生」と、戦中の特攻隊員とタイムスリップした女子高校生の恋愛を描く「あの花が咲く丘で」は、その典型的な作品に見えた。戦中と戦後。当たり前だが、若い世代が全く知らない世界だ。
もちろん、自分たちが知らない古めかしさだけでは若い層は飛びつかない。古い時代設定のなかで、自分たちに思い入れがあり、切実さが感じられる内容の作品だから関心を持つ。「未知=異世界」と、「思い入れ、切実さ=現世界」の混在ぶりが、作品の広がり方としてある。複合的な構造こそが、若い観客の気持ちを捉えたと言えようか。
「サプライズヒット」には、いくつかの理由がある。共通点がある場合もあれば、ない場合もある。一つ言えるとすれば、いずれも時代と大きなかかわりをもっているということだろう。大激変する時代には、それにふさわしい作品が登場する。「サプライズヒット」も、それに準じる。そして今や、観客が映画を「発見」する時代にもなってきた。ネット、SNS環境が、それを促す強力なツールだとして、その先はどうなるのか。その「発見」を見越して、AIが、観客の受容のメカニズムにまで入り込み、映画を作り出してくるのか。「サプライズヒット」は、すでに「学習」されているだろう。人間の英知は、それを超えなくてはならない。いやはや、大変な結論になってしまった。