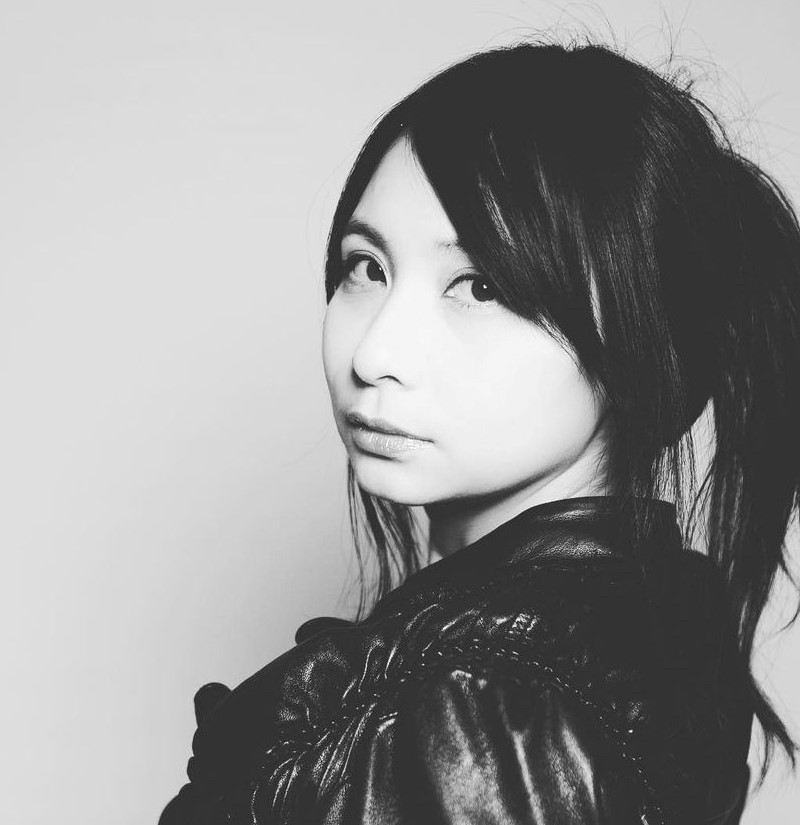公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。
取材に答える山下敦弘監督 撮影:下元優子
2024.5.30
生田斗真のイメージをうまく利用?!「告白 コンフェッション」山下敦弘監督インタビュー
死を覚悟した親友の最後の告白を聞いてしまった男と、言ってしまった男の一夜の攻防をたっぷりと詳細に描いた「告白 コンフェッション」。生田斗真、ヤン・イクチュンの日韓主演の2人がほぼ出ずっぱりの〝 怪演〟を見せるワンシチュエーションの密室劇である。「カラオケ行こ!」「化け猫あんずちゃん」と新作の公開が続く山下敦弘監督は「キャストたちの魅力をどう引き出すか、そこに特化した作品」と語った。
浅井とジヨンは親友で大学山岳部のOB。16年前、大学の卒業登山中に行方不明となり事故死とされた同級生・西田さゆりの十七回忌の慰霊登山中に、猛吹雪で遭難してしまう。脚に大けがをしたジヨンは死を確信し、16年前に自分がさゆりを殺害したと浅井に告白する。ジヨンは長く背負ってきた苦しみから解放され安堵するが、その直後、眼前に山小屋が出現し2人は命を取り留める。山小屋の中で救助隊の到着を待つ2人の間に異様で気まずい空気が流れ始める。
ヤン・イクチュンにひかれて
これまでといささかスタイルの異なる作品になった。6年前に企画の話が山下監督のもとにきた。「何年か越しで自分発信の『ハード・コア』(2018年)を終えて疲れている時だった。『マイ・バック・ページ』(11年)の後に燃え尽き症候群のようになっていた時の『苦役列車』(12年)のよう。新しいジャンルというより、次も映画が作れるという思い。もう一つ、原作の面白さに加え、プロデューサーからヤン・イクチュンさんで撮りたいという話にひかれた」
ワンシチュエーションの密室劇の経験はなく「あとで苦しむことになるが、『息もできない』やほかの作品でもイクチュンさんの存在は魅力的だった」。「リンダ リンダ リンダ」(05年)に出演したペ・ドゥナなどを通じて、韓国の俳優のポテンシャルの高さや刺激を実感していた。イクチュンにもいつか自作に出演してほしいと思っていた。

©2024 福本伸行・かわぐちかいじ/講談社/『告白 コンフェッション』製作委員会
映画作りのリスタート
密室劇を見るのは以前から好きだった。「この映画のあり方自体が、サム・ライミ監督の『死霊のはらわた』みたいな、ワンアイデア、ワンシチュエーションを膨らませてデビューする新人監督の感覚」だったという。「もう一回、リスタートする感じも魅力だった。ワンシチュエーションで予算はないが熱量とアイデアだけで1本作る。そんな映画作りへのあこがれと今までやったことのない作風」に前のめりになった。
韓国人と日本人は原作にはない設定だったが「それ以外は密室で、展開や仕掛けで見せていく作品。今の時代の話とかを考えるプレッシャーもなかった」という。「サム・ライミ監督やジョン・カーペンターの『遊星からの物体X』を参考にしたが、刺激はもらったものの全然違うものになった」と笑顔で話した。
違うものとは何だったのか。「キャストたちをどう描くか、描けるかが僕の持ち味でもあると再認識した。自分たちなりの映画になったという気がしている。僕自身はB級ホラーと思っているが、人によってはサスペンスという人もいる。余白のある作品になった」と納得した表情で振り返った。
生田のイメージをうまく利用?!
生田とイクチュンの二人芝居が続くため、役者の動きや表情、空気感が作品を支配した。密室サスペンスものはたくさんあるし、登場人物の背景も俳優に話をしたという。「生田さんは途中から高山病で目が見えにくくなる。どの程度見えるかはその都度、細かく相談して決めていった」という。「生田斗真のイメージや印象とかを浅井というキャラクターに反映した。浅井自体が人間臭くなったし、原作とも少し異なる感じになった」
生田のイメージを改めて聞いてみた。「一言でいうとさわやかで、人に対してあまり壁を作らず、おおらかな感じ。そういうイメージをうまく利用できたし、本人も楽しんで演じてくれたところもあったと思う。この作品の面白さを十分に分かってくれたし、おかしさも出してくれた」と満足げに話した。

生田に相対するイクチュンはどうだったのか。「芝居への向き合い方や集中力がすごかった。こちらにも緊張感が伝わるほど迫力があった。ただ、普段は本当に柔らかくて穏やか、優しい人。映画とは全然違う。そのギャップが怖いほどだった」と頰を緩めた。生田、イクチュンの演技を「楽しみながら撮影していた」と話した。
モンスターのジヨンにもおかしみ
山下監督が描く人物はさまざまだが、どこか人間のおかしみを感じさせてくれる作品が多い。それは、この作品のようなスリラー調のものでも変わらない。「原作の福本伸行さんのテイストもギャグがあって笑える。映画でもおかしさを含めていい題材。例えば、ジヨンは途中からモンスターになっていくキャラクターだが、どこか切なかったり、おかしかったりするのを意図的に演じてもらった」

2人が追いかけまわすときの武器もスコップやナイフなどが中心で、それ以上過激なものは使っていない。「原作も同じ世界観だったので、あるものでどう生き延びるか、攻防を繰り返してもらった」。ピッケルとかも候補に挙がったが「強力過ぎる」と却下された半面、山小屋によくあるノートに書く時の鉛筆を使って武器にするなど細かい工夫が随所にみられる。
初の本格的な密室劇を撮り終えてどう感じたか。「武器もそうだが自由度はある程度制限されている。映画としては縛りになるが、逆にいろいろなものを組み合わせ、足したり引いたりする面白さ、時々起きる奇跡も感じた。片方が韓国人ということすらも自由度を膨らませてくれた」という。
誰と作るかを大切にしたい
コロナ禍が明けた影響もあり、新作の公開が続く。「受け身ではあるが、自分がまいた種をたまたま拾ってくれる人がいる。僕の場合は、何を作るかもあるが、誰と作るかが一番重要なこと」というのが、目下の監督としてのスタンスのようだ。とはいえ、山下監督がどう作ってくれるか見たい、という人は列をなしているのが現状だ。「もちろん、自分から撮りたい映画もあるし。ある日突然違ったところから話をくれる人もいる。それを楽しみながら作っています」