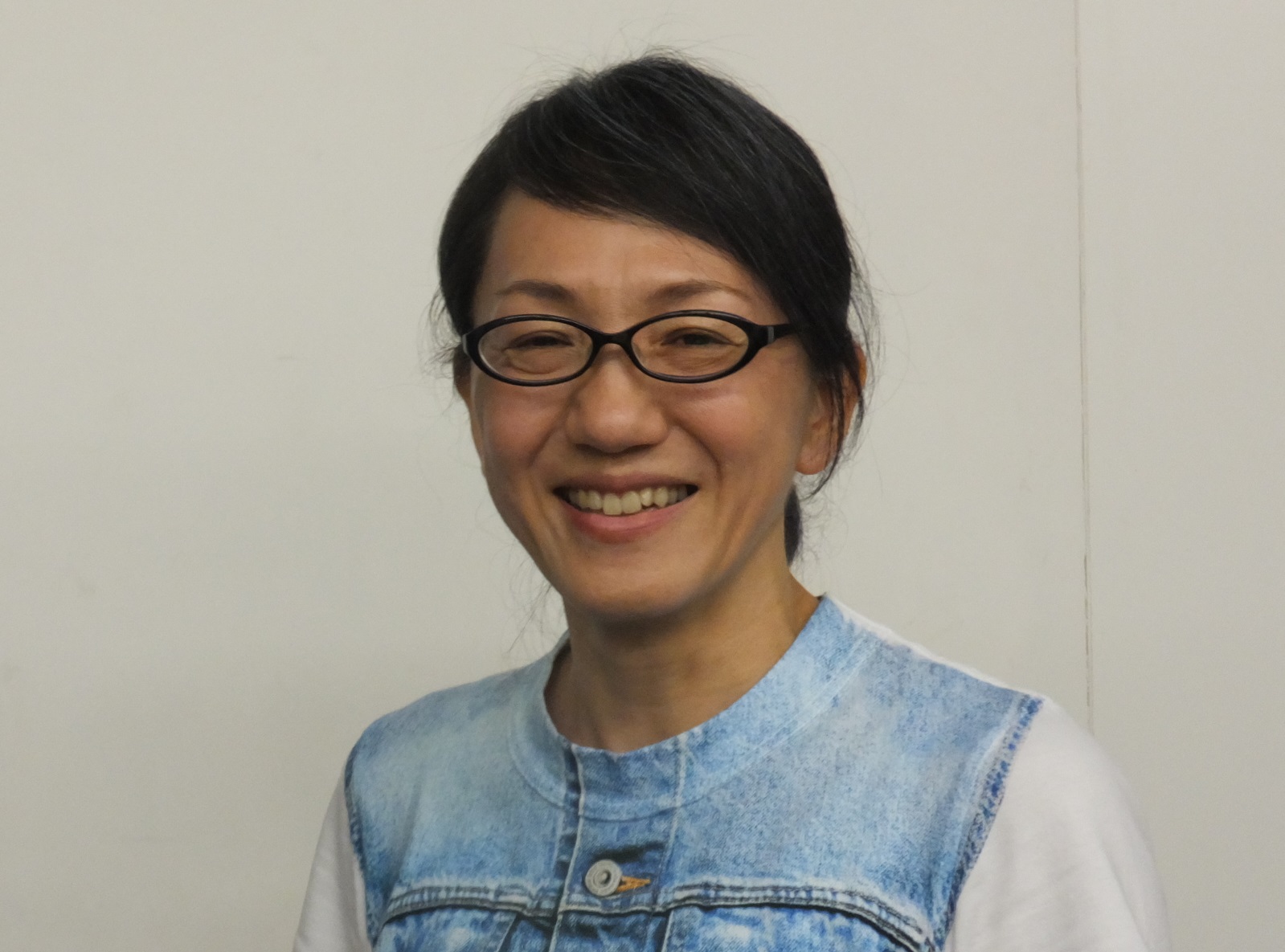公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。
「波紋」の荻上直子監督=鈴木隆撮影
2023.6.23
これってほんとに「女性活躍社会」ですか? 荻上直子監督がブラックコメディー「波紋」に込めた思い
「彼らが本気で編むときは、」(2017年)、「川っぺりムコリッタ」(22年)の荻上直子監督の新作である。新興宗教、震災、親の介護、障害者差別といった、現代社会が抱える問題に翻弄(ほんろう)されながらも、懸命に生きる一人の中年女性を鮮烈に描いた。「かもめ食堂」(06年)や「めがね」(07年)とは明らかに一線を画す意欲作。これまであまり題材にされてこなかった保守的な中年女性の作品でもある。オリジナル脚本も書いた荻上監督は「最初からブラックコメディーのつもりで作った。大いに笑ってください」と話した。
失踪後11年、突然帰宅した夫が「自分はがん」
夫が突然失踪して11年。息子も家を出て、依子は新興宗教を信仰し枯れ山水の庭を作り、更年期障害を抱えながらも一人で穏やかに暮らしていた。そこに、がんになったと夫が戻ってくる。高額の治療費を助けてほしいと言い、遠方で就職していた息子も聴覚に障害のある女性を家に連れてくる。依子は宗教にすがり、理性も感情も抑えつけようとする。
荻上監督は自宅近くにあった大きな施設にすてきな服を着た奥様たちが大勢出入りしているのを見て、何だろうと調べ始めた。「宗教施設だった。よりどころにしないと生きていけない人が、こんなにたくさんいるのか」。自分と同じくらいの年代の女性も多かった。

専業主婦は依存ではないのか
「私には専業主婦への差別意識みたいなものが少しあって、自立するとか働くとかせずに、なぜその場所に通うのか知りたかった。満たされないものがあるのか。それは何か。夫や子供に依存しているからではないか」とのめりこんでいった。
荻上監督の周囲にも専業主婦はいるし、男友達にも妻は家に入ってほしいと考える人はいた。

荻上監督「私はもっと嫌なヤツ」前面に
「宗教にはまる女性を主人公にしようと考えた。でも、私には共感できない、理解できない部分がたくさんあった。主人公に独り立ちしてほしい」と脚本を書き始めた。元々「かもめ食堂」以来、〝料理の上手ないい人〟みたいなイメージが自分に付きまとっているのが不満だった。
「もっと嫌なヤツだし意地悪だし、邪悪な部分もあって、それを全面的に出してみよう」という考えもあり、「(自分には)分からない人たちだったので悩みながら脚本を作っていった」。ファミレスで脚本執筆などの仕事をしている荻上監督の近くの席で、5人の女性が「今更仕事するなんて悔しいじゃない」などと言っているのを聞きながら、「かなりの多数派かもしれない」と考えていた。

筒井真理子に「主演と思わないで」
作品の中心は依子の視点だ。依子は夫や息子に依存して生きてきたが、同時に「自分はこうあるべきだ」という考え方を強く持っていた。「枯れ山水の庭にもそれが表れているし、毎日これをしないといけない、人にはやさしくしないといけないと、自分で決めたことにがんじがらめになっている。多くの人に同じような部分があり、そういう人は宗教にも入り込みやすい」
依子を演じた筒井真理子に求めたのは「主演と思わないでほしい」ということ。主演だと思って「気張ってほしくない」と伝えた。「依子はゆらゆらと揺れていてほしい。主演だからと力が入ると、夫に対しても新興宗教のリーダー(キムラ緑子)らに対しても、一方通行になってしまう気がした。依子は(他の人に)影響されて生きてきた人だから」。依子は「相談相手でしがらみの少ないスーパーの同僚(木野花)のアドバイスと、新興宗教のリーダーの教えの間を行き来して生きている」。
「筒井さんは勉強家で脚本を読み込んでくる人」。揺れている依子をいい意味でとらえてくれたという。依子は性根の悪い女性ではない。どこにでもいそうなタイプ。「筒井さんが持っているやさしさとうまく重なった」

家を捨てて生きていく可能性
女性が自立していく女性映画はあるが、依子は自立とは最も遠い所にいるような存在だ。フェミニズム的な映画とも全く違う。「依子は夫や子供、家に依存して生きてきた。世代にもよるが、この国の多くの女性たちもきっとそう」。いわゆる古いタイプの女性である。「私自身は一貫して女性も働くべきだと思っているが、こうした女性は日本にはまだまだ多い。今こういう映画を作っていくべきだと考えたし、見た人に現状への疑問を感じてほしかった」
映画の終幕はその願いを具体化した。依子はフラメンコを踊りながら、家の庭から通りへと出て行くのだ。依子の自立への可能性を示唆している。「依存から脱して一歩踏み出すことに結び付けたかった。家を捨てて生きていくという思いを込めた」
足元を見れば、税金対策でパートの労働時間を制限して働く女性は山ほどいるのが現実だ。「バカなルールがいまだにあるからだ。いくら『女性が活躍する社会』と言ってもこうした制度、人たちが減っていかないと、この国の男女格差、女性差別はなくならない」。自立とは無縁の女性を主人公にした背景に、現実的な観点があった。

自身の体験背景に「新興宗教=悪ではない」
依子を精神的に支えるのは宗教だ。宗教にすがり「緑命水」の力を信じている。昨今の映画で取り上げる新興宗教はインチキ臭さを前面に出しているが、本作では詐欺まがいではあっても、それほど悪いものとは見せていない。「信仰自体は決していけないことではないし、新興宗教がすべて悪いものではないはず。集まるのはいい人ばかりだし、炊き出しなど良いこともしている。依子も救われている」
こうした荻上監督の考えの背景には、自身の体験があった。「全寮制の宗教とは関係ない高校だったが、創立者の理念に沿ってみんな教えを守っていた。真剣に世の中の役に立とうという人たちを見てきたので、新興宗教だからといっておかしな集団という紋切り型で描くことはしなかった」。荻上監督自身は理念や教えに傾倒したわけではないが、新興宗教=悪や犯罪、というイメージとは距離をおいたという。
依子は年相応にさまざまな問題に向き合う。「介護はこの世代の人が直面していることだし、障害のある息子の彼女もしたたかな女の子にした。障害者の女性がみんな弱くて守ってあげなければいけないわけではないと思った」。生きていれば問題は山ほどあって、普段から考えていたことをそのまま依子にぶつけた。

「役に立つ人間」気持ち悪い
荻上監督自身は夫も子供もいてママ友もいる。「女であることの理不尽さは、日常にたくさんある。不快に思うことばかり。食事の世話や家事は当たり前と疑問に思わなかったりするが、考えてみると、なぜ私がやっているのだろうと」。母であり女性であることのプレッシャーを「私でも感じた」。
最後に今までと異なる作風の映画に挑んだ感想を聞いた。「自分の意地悪な部分や、仕返ししたり根に持ったりといったネガティブな一面を出した作品。もっともっと出してもよかった。もちろん女性だけにあるわけではないけど」と歯切れのいい言葉が返ってきた。その上で今、気になっているのは、〝役に立たない〟人間について。
「子供が、『役に立つ人間になりたい』なんて言っているのを聞くと気持ちが悪くなってくる。そういうことを言わせている世の中も嫌」
全国で公開中。
写真は 「波紋」©2022 映画「波紋」フィルムパートナーズ