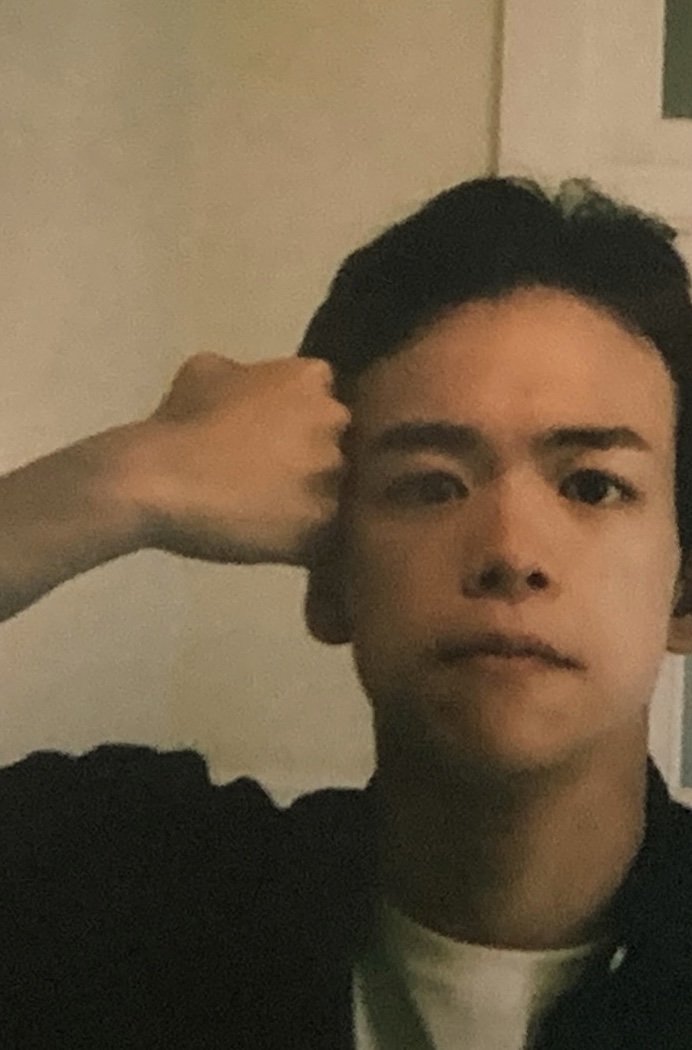毎回、勝手に〝2本立て〟形式で映画を並べてご紹介する。共通項といってもさまざまだが、本連載で作品を結びつけるのは〝ディテール〟である。ある映画を見て、無関係な作品の似ている場面を思い出す──そんな意義のないたのしさを大事にしたい。また、未知の併映作への思いがけぬ熱狂、再見がもたらす新鮮な驚きなど、2本立て特有の幸福な体験を呼び起こしたいという思惑もある。同じ上映に参加する気持ちで、ぜひ組み合わせを試していただけたらうれしい。
「ミッション:インポッシブル/デッドレコニングPARTONE」 ©2023 PARAMOUNT PICTURES
2023.8.06
「デッドレコニング」のアクションを際立たせた小道具がつなぐ小津安二郎:勝手に2本立て
ときたま、古い映画雑誌──たとえばインターネット普及以前のもの──をぱらぱらとめくっていると驚いてしまうことがある。そこには、当然のように「ただの酷評」が頻繁に掲載されているのだ。そういうとき、1997年生まれの私は「そうか、かつてはそうだったのだな」と思わずにいられない。
それに比べると、映画媒体で単なる酷評を目にする機会はずいぶん減ったような気がする。インターネットを立ち上げれば、鑑賞者による忌憚(きたん)ない賛否があふれていて幾らでも読むことができるのだから、わざわざネガティブな表明をする必要もなかろうということかもしれないが、一介の映画好きとしては、どこか寂しくもある。映画そのものが好みでなくとも、思い巡らすこと自体が楽しいこともあるからだ。好きになれなかった映画を、積極的に取り上げているのはそのためである。
ノレなかった「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」
目下公開中の「ミッション:インポッシブル/デッドレコニングPART ONE」(2023年)もまさにそんな作品で、期待に反して全くノレなかった。公開から半月がたった今ならば、展開に言及しつつ隅で苦言を呈していても許されよう。
ある時期まで「監督連続登板がない」という特徴が貫かれていた本シリーズにおいて7作目である本作は、例外的に連続登板が実現しているクリストファー・マッカリー監督による3本目。彼が初めてシリーズを監督したのは5作目の「ローグ・ネイション」(15年)で、それまでと異なる風合い、面白さに打ちのめされた公開時の驚きは今でも思い出せる。だから、特例の続投が決まった際も大いに納得したものだった。

牽引力あった「ローグ・ネイション」
「ローグ・ネイション」で良かったのは、主演トム・クルーズに引けを取らない、脇役/敵役の存在感。そして、これまで以上に肉体的過酷さが強調されたアクション。あるいは、映画史上(と乱暴に言い切ってしまいたい)最速のひとつに違いないバイクチェース。全編通して、強引なまでの牽引(けんいん)力が、状況の窮地を際だたせ、まさに「インポッシブル(不可能)」をどう打開するか、という緊迫を持続させていた。
だからこそ、映像ソフトに特典として収録されている音声解説を見たときは愕然(がくぜん)とした。撮影しているさい、厳密な脚本が存在しなかったというのである。そのじつ、目まぐるしく予想を裏切る展開、アクション偏重の姿勢は、編集のたまものだったのだ。

アクションの合間に便宜的筋書き
現場では、見せ場を撮影しているのに細かな設定が確定していない、何のために登場人物がアクションしているのか役者も把握していない状態で、展開を考えながら、完成形が見えぬまま綱渡りの作品製作をしていたらしい。自主映画、低予算映画ならまだしも、このような超大作で暗中模索など正気の沙汰ではない。
監督の証言に耳を傾けると、さすがにこのときは致し方なくそうしたのだという経緯も分かるのだが、離れ業がなまじ成功してしまったためか、まず先行する見せ場=アクションのアイデアありき、間隙(かんげき)は便宜的筋書きで埋めるというアプローチがどうやら根付いてしまったらしい。

つなぎでしかない会話場面
それゆえか「デッドレコニング」においては、本来は単なる製作事情でしかなかった(見ていて分からなければ何の問題もない)はずのところ、物語があからさまな形骸化をみせている。アクションのためのアクションが敷き詰められ、決して短くはない上映時間を満たすばかりなのだ。会話場面は、(上映時間が2時間半を超えているにもかかわらず)驚くほど少ない。文字通り「つなぎ」でしかないわけだ。
また、それは良いにしても全編が見せ場という状態が招いてしまうのは、予告編の網羅性である。興味を駆り立て、鑑賞意欲を誘おうとするアクション映画の予告編は、派手な見せ場の素材を中心に数分を構成する。ほんらいは、派手な見せ場があるていど予告編で使われてしまっていても、あまり問題はない。本編を見なければ、その場面がどのような流れのなかに位置づけられているか分からないからだ。しかも多くの場合、本編には予告に用いられていないアクション場面が多く残っている。

予告編で見た場面ばかり
けれど、本作は違う。全編を通して、それぞれが大がかりな分、ここぞという見せ場は限られている。規模が特に大きいものは、①ローマでのカーチェース、②バイクでの跳躍、③暴走列車内での攻防くらいだろう。そして、そのどれもが予告編で使われている。
予告編で見覚えのある場面ばかりで構築された本編を見ていて、浮かび上がるのは、皮肉なことに(予告編で明示されない)ずさんな筋書きのほうである。そして展開と不可分に結びついていないからこそ、体を張った過激でぜいたくなアクションシーンもまた、引き延ばされた蛇足に思えてくる。いつまでも決着のつかない攻防を、延々と見せられるのだから。

「あそこは良かった」手錠のカーチェース
ここまで文句を書き連ねたが、不思議なことに、じつは好ましい映画の全体像よりも、好めなかった映画の「でも、あそこは良かったよね」という場面のほうが印象に残るということが少なくない。
たとえば今回なら、中盤のローマ市街におけるカーチェースがそれにあたる。いつまでも追っ手を振り切れずに続く長い執拗(しつよう)なチェースという点では、前作「フォールアウト」(18年)にもパリ市街を延々と走り続けるバイクチェースがあり、印象自体も本作とそれほど遠からぬものではあった。しかし、本作ならではの新趣向もあって、そこがいい。今度は車で、しかも小さい(「ミニミニ大作戦」を想像していただければよい)。乗るのはトム・クルーズと新登場ヒロイン(女スリという小悪人設定が、肥大したスケールの本作にあって新鮮である)。しかも、ふたりは手錠でつながれた状態なのだ。

不自由が生むドタバタ喜劇
お互いに、片手が相手の片手とつながっているから、自由がきくのはもう片方の手のみで、片手での運転はどこか滑稽(こっけい)だし危なっかしい。だからといって無理やりに両手を使って運転しようとすれば、助手席の相手はグイと引っ張られることになる。進行するチェース自体も凝ってはいるが、それ以上に手錠という小道具の着想によって生まれた運転の不自由と車内のドタバタこそが、場面の魅力と言える。
だから、チェース中で最もおかしいのは、手錠(の制約)が最も有効活用された、運転を代わる瞬間ということになる。手錠さえなければ、車内でさっと場所を替えることはたやすいのだが、ふたりは手錠でつながれているからそうはいかないのである。つながったまま、片方のドアから、ふたりで一度外へ出て、地上で左右を入れ替えて、もう一度車内に戻るしかない。このまどろっこしさ! しかも、ここまで苦労して座席を替えておきながら、すぐあとには車が盛大に横転、車内でもみくちゃになるうち、気づけば元の位置に戻ってしまっているあたりの徒労感がまた愉快だ。

逮捕、監禁、ベッドシーン……つながれた2人
豊かな手錠の面白みに触発されて、記憶の底をかきまわして、映画内の手錠描写を掘り起こしてみる。手錠といえば、逮捕はいうまでもなく、監禁や護送、ときにはエロチックなベッドシーンまで広範に用いられるため、端から挙げはじめればきりがないが、ふたりを手錠ひとつでつなぐ映画に限れば、だいぶ絞れてくる。
さて、どれを「2本立て」としてつなげるべきだろうか。映画と手錠の縁は古く、すでにサイレント映画に使用例が見出せる。たとえば、エリッヒ・フォン・シュトロハイム監督作「グリード」(1924年)が有名どころだろう。また、トーキー時代に転じれば、アルフレッド・ヒッチコック「三十九夜」(35年)などの傑作もある。
ただ、前者は8時間あったオリジナル版が監督の意向を無視して短縮した版しか残っていない(それでも破格の作品であるが)からはばかられるし、後者はかねてヒッチコックの影響を公言するマッカリーが「デッドレコニング」で参照しているのは明らかで、本連載は影響関係を避けることにしているので選ぶことができない。その名もずばり「手錠のままの脱獄」(58年)という作品もあるが、さすがにこれを選んでは芸がない。

ブロンソンもデ・ニーロも、福山雅治も
以降もずんずん映画史を進んでみよう。80年代には「ノー・マーシイ」と「必殺マグナム」(ともに86年)という2作が公開されている。どちらも個人的に偏愛している好編なのだが、ちょっと地味なので今回はパス。また、大好きな「ミッドナイト・ラン」(88年)を思い出して「これだ!」と決まりかけたが、いざ見返してみたら手錠で2者がつながれている場面はわずかであった。どうやらポスターに刷り込まれた印象だったらしい。
諦めて近作に思いをはせれば、クエンティン・タランティーノ「ヘイトフル・エイト」(2015年)やジョン・ウー「マンハント」(17年)が浮かんでくるものの、残念ながら両作とも好みではないのだった。

サイレント時代の小津のノワール「非常線の女」
ということで、悩み抜いたすえに選んだ印象的な手錠映画は小津安二郎「非常線の女」(1933年)。「東京物語」を筆頭に広く記憶されている「日本的」印象が築かれる前、アメリカ映画に多大な影響を受けた無声映画期の和製ノワールだ。ちょうど90年前の作品で、今年は小津の生誕120年。これも何かの縁だろう、というわけである(並べて見比べてみると、心なしかタイプライターの描写も似ているように見えてくる)。
本作においても、手錠でつながれている時間は決して長くはない。いや、それどころかほんの数秒である。しかもその場面が位置しているのはラストもラストで、もはや細かく記述する字数も残されていないから、あえて説明はすまい。カシャンと(無声映画なので音はないのだが)手錠がかけられる感動的瞬間を、ぜひ実際にご覧いただきたい。
「非常線の女」はU-NEXTで配信中。