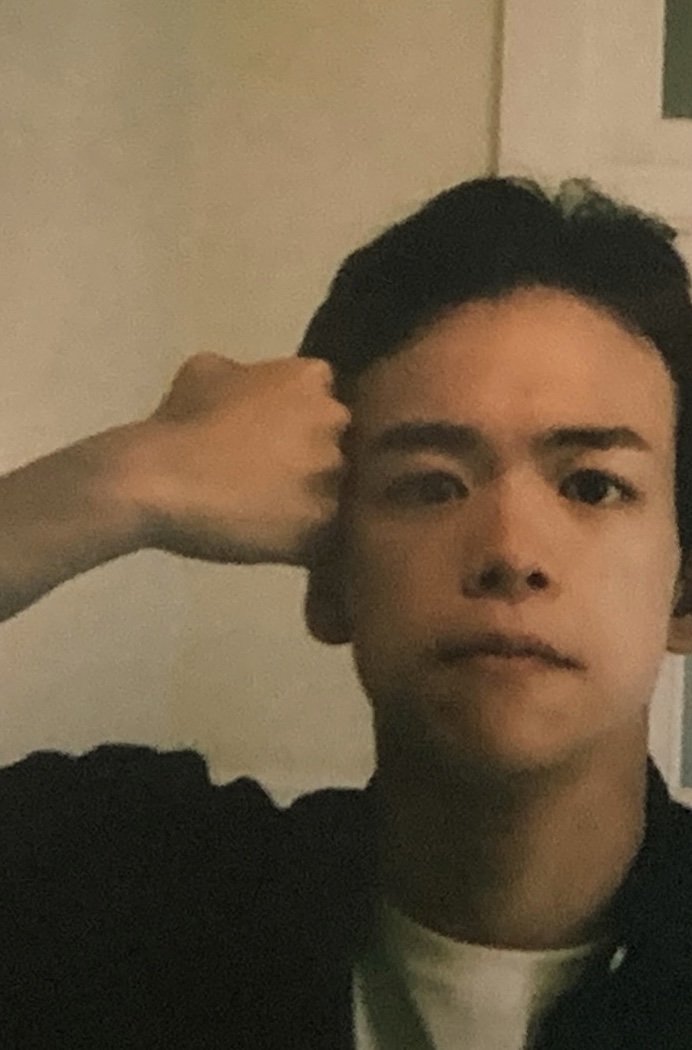毎回、勝手に〝2本立て〟形式で映画を並べてご紹介する。共通項といってもさまざまだが、本連載で作品を結びつけるのは〝ディテール〟である。ある映画を見て、無関係な作品の似ている場面を思い出す──そんな意義のないたのしさを大事にしたい。また、未知の併映作への思いがけぬ熱狂、再見がもたらす新鮮な驚きなど、2本立て特有の幸福な体験を呼び起こしたいという思惑もある。同じ上映に参加する気持ちで、ぜひ組み合わせを試していただけたらうれしい。
「地獄の警備員」©株式会社 ディ・モールト ベネ
2022.9.11
残業、ダメ絶対。オフィスの悪夢 「地獄の警備員」:勝手に2本立て
学生の時分、深夜の品川で映画を見ていた。特段、珍しい作品を見に来たというわけでもなく、ありふれた新作映画の1本である。当時は、公開初日の朝一番の回ではなく前日深夜0時から始まる上映回を見に行くことが楽しみで、この日もまさにそうだった。いち早く見ることができる優越感もさることながら、一般的に多くの人が就寝に充てている時間を〝活用〟している感覚が心地よかったのだ。また、見終えた後は終電の時刻を過ぎているため、始発まですることがなく、インターネットカフェを利用できるような懐事情ではないこともあり、習慣としていた新宿までの散歩も格別だった。
深夜のビル街で感じた孤立無援の恐怖
この夜も、映画を見終えるといつものように新宿を目指したのだが、品川から向かうのはこのときが初めてで、たちまち道に迷った。ときおり遭遇する工事現場とコンビニ、通過する清掃車、それ以外は暗く沈んだオフィスビルの群れ。携帯電話の電源も切れ、最初こそ方向は正しいはずだったが、次第にどこを歩いているかすら分からなくなった。結局、3時間以上さまよった揚げ句、新宿駅にはとてもたどり着けず、始発時刻に出発地点=品川駅になんとか帰り着くのが精いっぱいで、消化不良な散歩欲を抱えて帰路に就いた。
この夜、不思議だったのは、真っ暗闇なオフィス街にあって、ときおりビルのなかに電気がついている部屋があることだ。また、ごくたまにスーツ姿の人も歩いていた。もちろん、冷静に考えれば残業なのだろうことは予想がつくし、ままあることなのだろうが、そのときは数時間あてどなくビルの隙間(すきま)を歩いていたからか、こんな時間に人間が居残っているという状況の非現実さばかりが際だって感じられた。何かあったらどうするのだろうか。少なくとも、朝までは孤立無援ではないか。
前置きが長くなったが、まれにそんな恐怖を描く映画があり、見ているあいだ、この夜のことを思い出さずにいられない。
警備員より職場が怖い「地獄の警備員」
黒沢清監督作「地獄の警備員」(1992年)もそのひとつ。題名の通り、えたいの知れぬ警備員──当時映画初出演の松重豊が演ずる──が深夜残業者を襲うのだ。物語は基本的に美術品売買の商社に入社した女性=主人公の視点から語られ、謎の警備員がなぜか自分に執着しているらしい……という予感に始まり、次第に警備員の行動がエスカレートしていくことで殺戮(さつりく)の一夜へと至るのだが、むしろ幾度か見たあと印象に残るのは〝警備員〟より〝地獄〟のほうだろう。「地獄の警備員」という題名を見ると、「地獄」という語句は「警備員」の恐ろしさを引き立てるための選択のように思える(じっさい、そうなのだろう)が、そのじつ「地獄」とは職場のことではないのか。
本作の警備員は確かに怖い。開幕早々、過去に殺人を犯している元力士という設定が明らかになるが、姿を現すのは長身痩身(そうしん)の松重で、設定と身体の差異がえたいの知れなさを引き立てる。しかし、そのいっぽうで主人公への並々ならぬ執着が描かれるとはいえ、あまりの殺人マシンぶりは、どこか現実離れした印象でもある。結局のところ、彼の恐ろしさは暴力の次元にのみあるといっていい。
そう考えるとき、他方やたら執念深く描写されるオフィスの生態が浮かび上がる。「パワハラ」「セクハラ」と語句に還元してしまえばそれまでだが、いずれも実態は千差万別、そのときどきで異なる生々しさ、おぞましさがあり、本作はその具体性の表出に注力しているのだ。警備員をめぐる本筋の合間で差し挟まれるいささか滑稽(こっけい)とも言える場面群ではあるが、いずれもまったく笑えない。
主人公を呼び止め、個室へと招き寄せて「見ているだけでいいから」と唐突に自慰を見せつけようとしたり(主人公はその場から急いで逃れるが、直後に別種の恐怖体験を味わうため、この件についての回収はなされず、より一層の居心地の悪さを見る者に植え付ける)、部下の男性社員(彼もまたあからさまな不適切行為に手を染めることはないものの、露骨な下心が表情に張り付き、日常的に粘着行動をする忘れがたい登場人物である)を促して先に帰宅させ、残業中の主人公が1人居残っている階へ向かおうとしたりする上司の男――彼がどのような目に遭うかを見れば、職場の不愉快さが本作のひとつの核=テーマとして、意図的かつ周到に描写されていることがわかる。生命の危機など訪れなくとも、オフィスは常に「地獄」なのである。

「P2」© 2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.
地下駐車場限定のアイデアとアクション「P2」
アメリカでも事情(?)は変わらない。フランク・カルフン監督作「P2」(2007年)でも、深夜残業中の女性社員が警備員に襲われることになる。設定は少々似ているが「地獄の警備員」と決定的に異なるのは、本作が〝一夜〟に専念していることだろう。
夜、主人公がようやく残業を終えてオフィスを出、会社を後にしようとすると、どこも出口が閉まっていて、出られない。幸い、親切な夜間駐在の警備員がいて、助けてくれそうな気配なのだが、もちろんそんな展開にはならず、彼こそが閉鎖状況を仕掛けた張本人なのである。
タイトルの「P2」とはビル内地下にある複数階構造の駐車場──警備員室もまた、この一角に位置している──のことで、本作はほぼ全編がこのフロアで展開することになるのだが、序盤の身も凍る監禁場面を除けば、残りすべてがひたすら逃走と対峙(たいじ)に懸けられていて、この感動的なまでのストイックさが魅力。
警備員が敵であるからこその監視カメラ、駐車場だからこその車、地下だからこその電波遮断状態──シチュエーションが固定されているからこそ、それを受け皿として、状況を活用した多様なアイデアを盛り込み、アクションに転化して矢継ぎ早に連ねていく。だからこそ、限定的空間を舞台としていながら物足りなさを感じさせない、むしろ〝ワンアイデア〟を起点とした可能性の広がりを証明する結果になっている。また、こちらはちゃんと警備員がじっとり気味悪い人物造形となっていてすばらしい。
両作ともに、最後は退社で終わる。長い悪夢の一夜をくぐり抜けた彼女らは、今後決して残業することはないだろう。そもそもロクなものではないのだ。定時に帰路に就くのが一番である。
「地獄の警備員」「P2」ともにU-NEXTにて見放題で配信中。