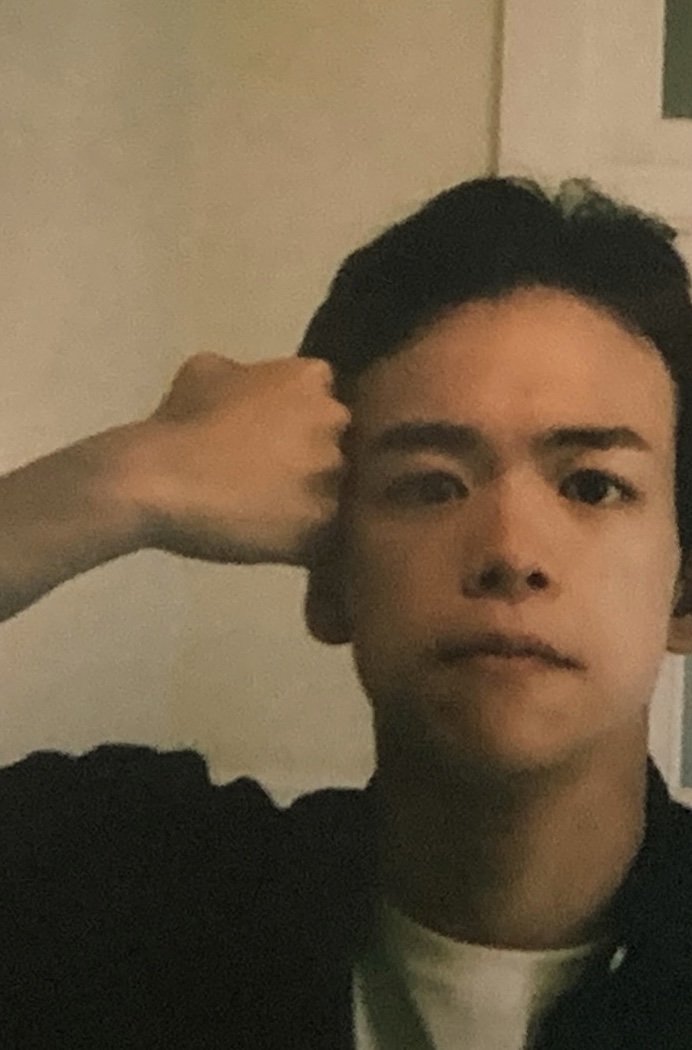毎回、勝手に〝2本立て〟形式で映画を並べてご紹介する。共通項といってもさまざまだが、本連載で作品を結びつけるのは〝ディテール〟である。ある映画を見て、無関係な作品の似ている場面を思い出す──そんな意義のないたのしさを大事にしたい。また、未知の併映作への思いがけぬ熱狂、再見がもたらす新鮮な驚きなど、2本立て特有の幸福な体験を呼び起こしたいという思惑もある。同じ上映に参加する気持ちで、ぜひ組み合わせを試していただけたらうれしい。
「劇映画 孤独のグルメ」©2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会
2025.1.23
韓国でファンテヘジャンクを食す井之頭五郎とホッピーの意外な飲み方:勝手に2本立て
映画化を知ったときも驚いたが、松重豊が監督・共同脚本・主演と知ったときはもっと驚いた……「劇映画 孤独のグルメ」である。見る前からどんな映画になるだろうかと想像を膨らませていたのだが、いざ見てみると予想以上に変わった映画でもあった。というのも、随所に「テレビと同じことをやっても仕方ない」という意気込みがあふれているようなのだ。
ドラマパートとお店紹介 主従逆転の「劇映画」
それは、題名に冠されている「劇映画」という語句の選択にもあらわれているかもしれない。「劇場版 孤独のグルメ」でも「映画 孤独のグルメ」でもないところに。じっさい本作は、ドラマパートと店舗紹介部分の主従関係がテレビ版と逆転している意味で、まさに「劇映画」なのである。
なかでも後半に登場するラーメン店「さんせりて」は、その志向の最たるものだろう。そもそも店自体が架空である(ゆえに紹介は成立しない)し、肝心のラーメンを食べる見せ場には定番のモノローグも流れない。そもそも店内が異様に、過剰に暗いのだ。まるでテレビでは許されない画面の暗さを限界まで試みているかのように。

「劇映画 孤独のグルメ」©2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会
フランス、五島列島、韓国……
とはいえ、そうはいっても「松重豊が演じる井之頭五郎が足を運んだ地で食事する」という骨子は変わらない。上述の通り、架空の店も登場するのだが、きちんと実在の店舗も紹介される。映画版らしくワールドワイドに、約2時間かけてフランス、五島列島、韓国を巡り、それぞれの場所で食事が描かれることになる。
やはり今回の映画版の面白さは、海外が舞台であることだろう。これまでのテレビシリーズにも出張回はあり、ときおり異国での食事を目にすることができたが、それを数カ国分まとめて見ることができるわけである。
不慣れな国と不慣れな言葉という状況が、単なる食事場面に一層のおかしみを付加するのだろうか。松重豊が真顔で「しるぶぷれ」などと言うだけで笑えてしまうし、メニュー選択もいつも以上に不確定要素の多いものとなる。そもそもメニューが読めなかったり、読めたところで何の料理かわからなかったり、といった事態がささやかなハラハラを生むのだ。

読めないメニューの注文方法
とくにその要素が顕著なのが、韓国での食事場面だろう。空腹に耐えかねて近くの食堂に入店したものの、ハングル表記のためメニューを読むことができない主人公は、店員に読み上げてもらうことにする。聞き覚えのある単語のメニューを注文する、という賭けだ。
知っていた単語は「へジャンク」で、スープという意味。少し前に、この単語を教わる場面があるから、観客であるわれわれもメニューが読み上げられるとき、この言葉を知っている。頼むことにしたのは、「ファンテへジャンク」。このとき主人公も観客も、「ファンテ」が何かはわからない。けれど、食べ始めてすぐにこの言葉の意味も教わることになる。
本作は、知らない料理を頼んだり、食べ方を教えてもらったり(あるいは、わからないまま食べたり)する手探りの楽しさが、全編に満ちている映画なのだ。思えばテレビシリーズ「孤独のグルメ」に感じていた魅力も、この感覚だったかもしれない。

「これはどうやって食べるのか?」を追体験
テレビシリーズの舞台は日本国内であることがほとんどではあるが、初めて入る店で、聞き覚えのない料理を勢いで頼んでみた時に感じる、「これは、どうやって食べるものなのだろう」という感覚の追体験が、多くのエピソードに用意されている。主人公は、お店の人に教わったり、周りのお客さんを参考にしたり、はたまた我流で食べたりする。その手探りで食べすすめる流れの楽しさ。
われわれは、番組を見ながら、わからなさに共感し(すでにその店や料理を知っていても、それはそれで楽しめる)、そのあと実際に足を運んでみた場合は(または、ほかの店で似た料理を食べるときも)完全に無知な状態ではなく、番組を参考に食べることができるようになっている。写真だけではつかみにくい、内観や雰囲気も明確に感じ取ることができ、ちょっとした予行練習のようだ。

映画やテレビに教わったビリヤニ、ボルシチ
「劇映画 孤独のグルメ」を見ていて考えさせられたのは、「いろいろなものを教えてくれる存在」としての映画やテレビの在り方であった。いまでこそ常識と感じる物事も、映画やテレビで知ったことが無数にあることを久々に思い出したのである。
振り返れば私自身、日本以外に国や言葉があることを感覚的に理解したのは映画やドラマによってであった気がするし、料理に限ってもビリヤニやボルシチなどは映画で見るまで聞いたこともなかったはずだ。どちらも今では好物だが、たしか最初は映画の記憶にひかれて食べに行ったのではなかったか。

「ワイルド・スピード/ジェットブレイク」© 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.
「ワイルド・スピード」日本での名場面
今回の映画でも、そしてテレビ版でも、たびたび主人公は知らない料理の食べ方を教わるのだが、そんな場面を見ていると「これは、さすがに教わらないとわからないだろうな」と思うことがある。なので、いささか駆け足ではあるけれども、「教わらないとわからない」飲食物が出てきた映画をもう一本ご紹介して今回は筆をおくことにしたい。
それは、「ワイルド・スピード/ジェットブレイク」に出てくるホッピーである。多くの居酒屋に常備されており、飲んだことのある方も少なくないであろう、あのホッピーだ。もちろん、なじみのあるわれわれは「教わらないとわからない」わけがないのであるが、そんな「当たり前」こそ、説明書きがなかったりするぶん、旅行者にとってはわからなかったりするのである。ホッピーが出てくるのは、もちろん日本の場面だ。作戦の一環で日本を訪れ、屋台で腹ごしらえをすることにした女性人物ふたりが注文するのがラーメンとホッピー。
ここで、われわれが違和感を覚えるのは、向かい合ったふたりが自分のラーメンをつつきながら、まるでコロナビールのようにホッピーを瓶から直接ゴクゴク飲んでいること。ああ、違うんだよ、それは焼酎の割り飲料で……。でも、たしかに説明がないとわからないよなあ、ホッピーセットの仕組みは……。と、なること間違いなしの、ある意味では「リアル」なのかもしれない名場面。
調べて知った事実 すべて承知の上?
「ワイルド・スピード/ジェットブレイク」は、すご腕ドライバー集団が世界を股にかけて活躍する、人気カーアクション映画シリーズの第9作で、作品自体はいちげんさんに親切な作りとは言いがたいものの、気になった方はぜひ、この場面だけでも試しに見てみていただきたい。
余談だが、この映画を見てから試してみたところ、意外なことに、ホッピーはそのまま飲んでも結構おいしいのだった。じつはホッピーの公式サイトを訪ねてみると、「冷やしてそのまま飲めばアルコール度数約0.8%低アルコール飲料に」という提案がなされてもいるのだが、これまで不覚にも知らなかった私にとって「ジェットブレイク」は、「孤独のグルメ」同様、新たな飲み方の発見としても役立ったわけである。
あのふたりは、じつは全て承知のうえで、あえて瓶から飲んでいたのかもしれない。