映画の魅力は細部に宿る。どうせ見るならより多くの発見を引き出し、よりお得に楽しみたい。「仕事と人生に効く 教養としての映画」(PHP研究所)の著者、映画研究者=批評家の伊藤弘了さんが、作品の隅々に目を凝らし、耳を澄ませて、その魅力を「よくばり」に読み解きます。
©gettyimages
2022.11.01
「春はあげぽよ」とジャーゴン 映画分析「超」入門:よくばり映画鑑賞術
「春は揚げ物」というフレーズをSNSで目にしたとき、うまいことを言うものだと感心させられた。「春はあげぽよ」というフレーズにも同様の趣がある。
言葉にはそれを用いる集団の文化が折り畳まれて内包されている。たとえば「春はあけぼの」を単に外国語に直訳してもその含意は伝えきれないだろう。多くの日本人は、これが清少納言の「枕草子」の冒頭であることを知っているし、あとに続く文章も何となく覚えている。
文化を内包する専門用語
「春はあけぼの」という表現を目にすれば、そこに書かれている文字情報以上のものを連想することができる。だからこそ、わたしたちは「春は揚げ物」や「春はあげぽよ」をおもしろがれるのである。
ジャーゴンもまた言語の一部であり、言語と同じように文化を内包している。そもそも「ジャーゴン」という言葉自体、注釈なしで使えるほどに一般的ではないかもしれない。専門用語、あるいは、特定の業界やグループ内だけで通用する特殊な言葉を指す。
その言葉の意味を知っている人同士であれば結束感を強めることができるが、知らない人は疎外感を覚えることになる。知らない人に対してジャーゴンを連発することは、その人が意味を解さない外国語でひたすら語りかけるようなものだ。はなからコミュニケーションを取る意思がないと思われても仕方ない。
より深く、より遠くに向かうために
ジャーゴンは嫌われる。
多くの人は楽しく映画を見たいのであって、たとえば劇中にいくつか「イマジナリーライン」を無視した「切り返し」があっても、それが単に撮影・編集上の齟齬(そご)からくる「180度規則」の綻(ほころ)びなのか、それとも「古典的ハリウッド映画」の「コンティニュイティー編集(インビジブル編集)」に対する自覚的な異議申し立てなのかを議論したいとは思わないだろう。
ジャーゴンにまみれた文章というのは、たとえば上記のようなものである。
一般に、研究者や批評家、評論家は「ジャーゴン」を駆使する人種だと思われている。馴染(なじ)みのない用語や概念や理論を、さもみなが知っていて当然のような顔をして使われても、何を言っているかわからないし、理解する価値がある内容なのかさえわからない。世間からその存在を煙たがられるのもむべなるかなである。映画研究者や映画批評家、映画評論家も例外ではない。
それではなぜ研究者たちはジャーゴンを使うのか。頭がいい人間だと思われたいからだろうか。そういうケースがないとは言わないが、本質的な理由ではない。ジャーゴンを使うのは、その方が効率がいいからである。先ほど外国語の例を出したが、異なる言語の話者が通訳を介在させて意思疎通を図るよりも、同じ言語を話すもの同士で直接話をした方が手っ取り早い(外国語や通訳の価値をおとしめたいわけではないので、あしからず)。基本情報を手早く共有することによって、元の意味をずらしたり、議論をより深く、より遠くに向かわせたりすることができるようになる。
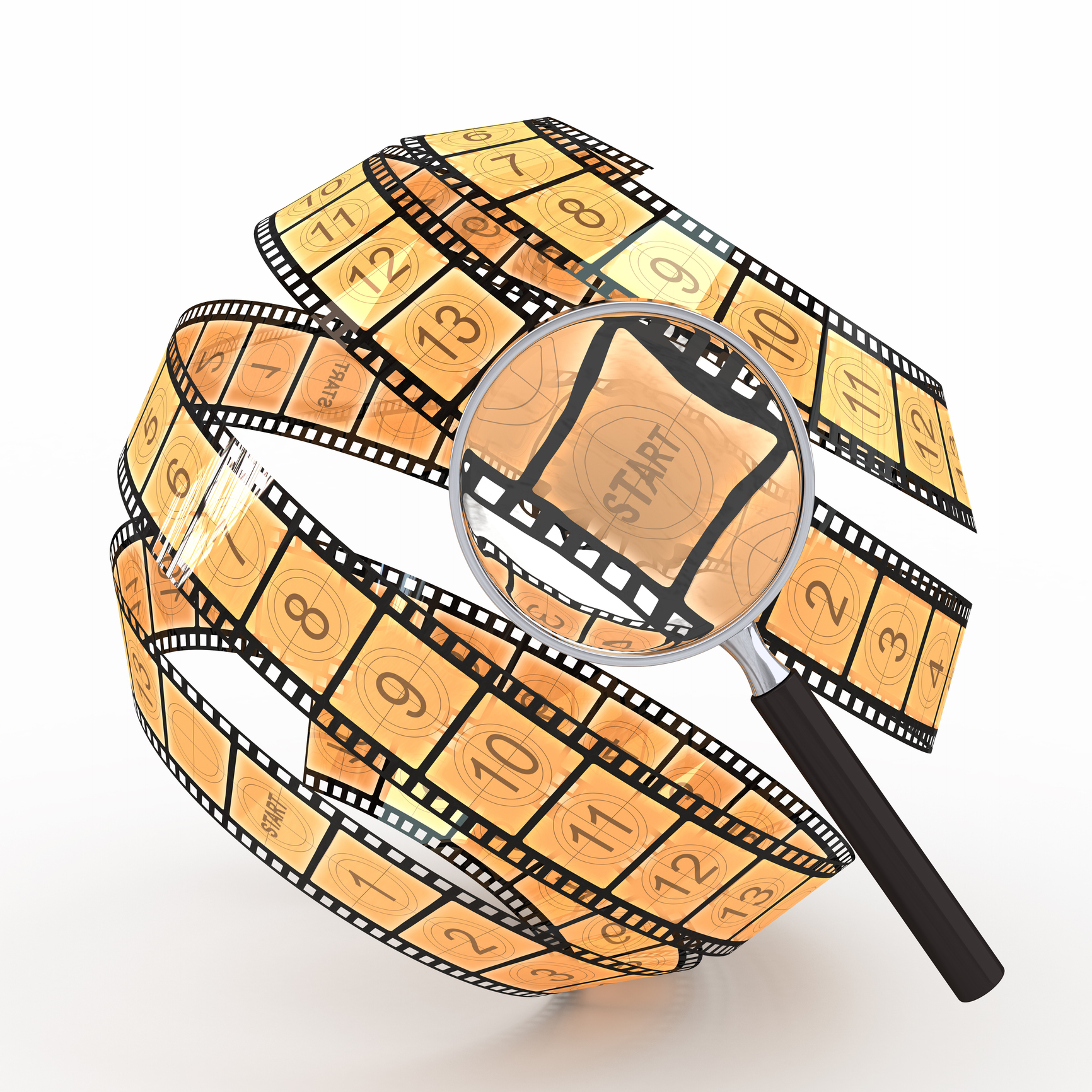
ファム・ファタールとフィルム・ノワール
たとえば「ファム・ファタール」という言葉がある。フランス語(femme fatale)由来の言葉で、映画や文学を含む物語全般、ときには現実世界の事象に対しても用いられる。日本語ではしばしば「運命の女」と表現される。いわゆる「男を惑わし、破滅に導くような魔性の女」を指す。そういったキャラクター類型自体は多くの人にとって馴染みのあるものだろう。
ただし、映画研究や批評の文脈において「ファム・ファタール」という言葉は単に「魔性の女」「悪女」を言い換えただけのものではない。「ファム・ファタール」は「フィルム・ノワール」という映画ジャンルと密接な関わりを持つ概念である。
「フィルム・ノワール」(film noir)もまたフランス語由来の言葉である。ある種の犯罪映画のことを指し、「暗黒映画」と訳されもする。ジャンルはある共通の特徴を備えた作品を一くくりにするために用いられる。「フィルム・ノワール」とは、都会を舞台にした犯罪絡みの映画であり、孤独でシニカルな男性を主人公に持ち、「ファム・ファタール」に相当する女性キャラクターが登場する。画面は明暗のコントラストを強く意識したモノクロで、しばしば雨にぬれている。また技法的にはボイスオーバー(男性主人公のモノローグ)が多用される。結末は暗いものであることが多い。
亡命ユダヤ人の似姿
「フィルム・ノワール」の製作には多くの亡命ユダヤ人が携わっている。運命に翻弄(ほんろう)される登場人物たちは、ナチスの迫害を逃れてヨーロッパからハリウッドに渡ってきた彼らの似姿でもある。映画全体に漂う暗さもまたその反映であると言えるし、犯罪映画としての「フィルム・ノワール」がギャング映画の流れを汲(く)むこととも関係している。
1930年代に導入された「プロダクションコード」と呼ばれるハリウッドの自主検閲規定によって、犯罪者を英雄的に描くことが禁じられた。したがって、ギャング映画の主人公たちは劇中でどれほど華々しい活躍を見せても、最終的に死を与えられることになったのである。また、極端な照明は20年代に隆盛した「ドイツ表現主義」の名残と見なすことができる。
狭義のジャンルとしての「フィルム・ノワール」は「黒い罠」(オーソン・ウェルズ監督、58年)をもって終焉(しゅうえん)したとされることが多いが、それ以降も共通するスタイルを備えた映画は作られ続けており、そうした作品は「フィルム・ノワール」との関係で語られることになる。たとえば映画研究者=批評家の加藤幹郎は、SF映画の金字塔として知られる「ブレードランナー」(リドリー・スコット監督、82年)が「フィルム・ノワール」の要素を持ち合わせていることに着目し、緻密な分析をおこなって、この作品を映画史のなかにしかるべく位置づけようと試みている。

映画を味わい尽くす助けとして
「フィルム・ノワール」という用語には、少なくともこれだけの情報量が含まれている(反論や異論の余地はあるにせよ、現代の映画研究者や批評家ならまず間違いなく共有している内容である)。だから用語を知っているもの同士のあいだでは「あの作品はフィルム・ノワールっぽい」という感想だけで多くのことが了解されるし、「ファム・ファタールが登場する」と言えば、作品自体がジャンルとしての「フィルム・ノワール」と何らかの関わりを持っていることを示唆できる。「フィルム・ノワール」から派生した「ネオ・ノワール」と呼ばれる一群の作品があったり、ある種の性描写を売りにする映画が「エロス・ノワール」という惹句(じゃっく)を用いたりする例もある。
こうした用語の意味や背景を押さえておくと、映画批評が読みやすくなるだけでなく、映画体験の質自体も上がる。用語を通して、他の作品との位置関係が見えてくるので、個々の映画を点として鑑賞するだけではなく、ほかの映画とのあいだに線を引くことができるようになるからだ。そのようにして体系的な鑑賞体験を積み重ねていけば、新しい映画を見たときにそれを自分なりに位置づけられるようになる。また、テーマや設定、技法のレベルまで、映画を見る際に注目するポイントが増えていくので、作品に対する解像度がおのずと高くなるのである。
今回は導入編ということでやや抽象的な内容になってしまったが、今後、具体的な作品の分析を通して「ジャーゴン」の持つ効用を解説していきたいと考えている。もちろん、読者にそうした用語をさかしらに振り回してもらうためではない。それが映画をよくばりに味わい尽くすためのひとつの方法だと信じているからである。
【関連記事】
・「偶然」を「運命」に変えるベアリング「アキラとあきら」に仕掛けられた反復:よくばり映画鑑賞術
・巨星落つ――さらば、ゴダールよ、あるいは、こんにちは、ゴダール:よくばり映画鑑賞術
・漫画から映画へ華麗なる変容 芦田愛菜の全力疾走が示すもの「メタモルフォーゼの縁側」:よくばり映画鑑賞術






