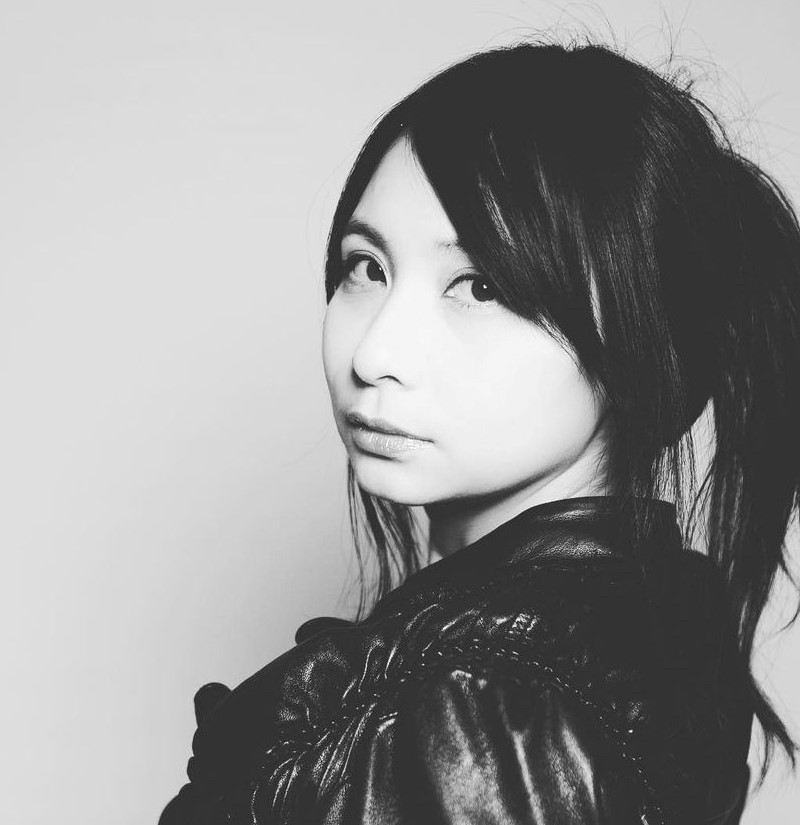公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。
「かくしごと」の関根光才監督=下元優子撮影
2024.6.19
「杏さんなら深掘りしてくれる」直感信じて託した「かくしごと」 関根光才監督
「かくしごと」で主演した杏は、ドラマなどのイメージを一新。理屈を超えた愛とうそで子供を守る母親を演じ、新たな〝代表作〟とした。関根光才監督は「生きてるだけで、愛。」(2018年)で鮮烈な長編監督デビューを飾った映像クリエーター。これが長編第2作だ。本作では虐待や認知症といった現代社会のリアルな課題を背景に置き、「ある事象をどう解釈するかを考えて創るのが好き」と語る。
他人を自分の子供と偽って……
絵本作家の千紗子は、ある事情から長年連絡を絶っていた父孝蔵が認知症になったため、渋々故郷に戻り介護を始める。旧友の久江と会った帰宅途中に、久江が運転する車が少年をはねてしまう。記憶を失ってしまった少年の体に、千紗子は虐待の痕を見つけた。さらなる被害から守ろうと、少年にも周囲にも自分が母親だとうそをつき、父と3人で暮らし始める。初めはぎこちなかったが少しずつ心を通わせあい、新しい家族の形を育んでいたが……。
女性主人公を追いかける点では「生きてるだけで、愛。」と共通する。しかも、女性が起こす行動が「狂気じみていて感情的」な点も似ているが「あくまで偶然」と話す。「『生きてるだけで、愛。』は自分も俳優たちももっと若かったが、この作品は家庭や子供を持って、喪失を味わった人の物語」を淡々と表現したという。
原作は北國浩二の小説「噓」だが、どこにひかれたのか。企画が始まったのは16年。児童虐待の事件が頻繁に報じられていた頃だったという。「自分でも理由が分からないのだが、そうした記事を読むと震えるような気持になった。世の中に悲しいことはたくさんあるが、虐待はとりわけ目をそむけたくなるほど衝撃的で、ドキッとしていた」。といっても自身に虐待を受けた経験があるわけではない。
もう一つは、祖父が認知症になり亡くなったこと。「認知症への理解があまりない頃で、本など読んで知っていたらもっと理解してあげられた、という思いが残っていた」。二つのトピックが合わさり「千紗子という女性の視点に、より強く関心を持った」と話した。

©2024「かくしごと」製作委員会
とっぴな行動でも視点を変えれば理解できる
千紗子のとった行動はとっぴで、理解する人は少ないだろう。関根監督はこう解釈し、説明する。「彼女の視点を追いかけながら物語を見ると、普段なら理解できないことも理解できてしまう。彼女や周囲の人物に嫌悪感を持つ人もいると思うが、自分ではどこかで同調してしまうところがあった」。とはいえ物語の入り口で、自分が母親とうそをつき他人の子を育てる行為への違和感はぬぐい切れない。
「結果だけ見ると理解できないし、犯罪だと考えて反発し、嫌い、壁を作る人もいるだろう。ただ、千紗子の立場、事情を少しでも共有できれば理解できる。そう考え、観客を信頼して作った」。関根監督は俳優の演技のメソッドを例に続ける。「役者は、演じる人物に共通点を見つけ出すとよく言われる。役を生きるということにもつながる。それに近い」。この作品でいうと「千紗子のことはよくわからないが、千紗子が感じるファクターを少しでも感じることができれば、そこを入り口に気持ちも入っていける」
作品を具体的に見ていこう。記憶をなくしていく父と、取り戻すかもしれない子供を並べた。「記憶は原始的体験や家族にひもづいていて、それがトリガー(きっかけ)になって忘れていたことを思い出す場合もある。一方で、認知症は子供に戻っていく側面がある。〝記憶〟と〝子供〟がクロスオーバーする」。一方で、映画のラストは原作と大幅に異なる。衝撃的なクライマックスではあるが「映画の中で結論を出すのは良くない」と考えた。「解釈に余韻を残したいと思い、構成的にベストのショットが撮れた」と満足げに話した。中身は明かせないが「俳優はプレッシャーのかかる演技だったはず」と付け加えた。

「分からない」ほとんどなかった
作品の成否を分けたのは、千紗子を演じた杏である。これまで、こうしたテイストの作品は少なく、テレビドラマのイメージが強かった。「杏さんならやってくれる」。直感だったという。「自身の中の千紗子らしさを理解し、深掘りしてくれる」と思った。本人からは「この人のこと、結構わかる。今の自分ならやれるかもしれない」と伝えられたという。
役者にとって、優れた脚本や監督、共演者とタイミングよく出会うことは、そうそうない。それをつかみ取った時に「代表作」が生まれる。関根監督も「杏さんばかり見ていた」と、作品を託していた。「杏さんから『ここは分からない』という問いかけはほとんどなかった」という。
傷痕は美しい 修復の必要性
千紗子の生きざまは作品のテーマと深くかかわっている。関根監督は「今の時代、いろいろな要因から逼迫(ひっぱく)した状況に追い込まれている人は多い。傷つきやすくてもそれをさらけ出せず、〝かくしごと〟にしてしまうことも多々あるのではないか」と根幹に触れていく。「表現者の一人として、修復の必要性を考えてきた。(陶磁器の)金継ぎのように。傷があるものを再生させ、その傷を隠すのではなく美しいと見る視点が大切だと思う」。千紗子ばかりではない。登場人物は誰もがそうした傷やかくしごとを持っている。「うそとはニュアンスが違う。かくしごとの意味をより深く感じてほしい」
俳優の感情も大切にしてきた。例えば、少年を演じた中須翔真の現場では、その場で日常的に「こういう時にこのセリフを言って、おかしくないですか。違和感があれば、そのセリフはやめましょう」と話したという。

団塊ジュニアが得られなかった家族
母性の映画という見方もできる。関根監督は1976年生まれ、2人の子供がいる。自分たちの世代特有のものもあるという。「団塊世代の子供で、仕事にまい進してきた親の下で、子供は勝手に育つという風潮があった。同世代の人と話すと、薄いネグレクトのようなものを感じる。大人になって、(その反動もあって)異様に家族関係を大切にする人が増えたと思う。自分たちが得られなかったものを何とかしたかったのだと見ていた」
個人差はあっても、この映画を製作する背景として関根監督が考えてきたことだった。「子供をきちんと見て育てるのは当たり前だから、社会現象として特段取り沙汰されたり、語られたりすることはないかもしれないが、親と子の関係性は自分が子供の頃とかなり違うと考えてきた」。この映画でそれを伝えようとは思っていないとしつつも「世代が持っている喪失感や空気、結局得られなかったものを描いているのかもしれない」と話した。