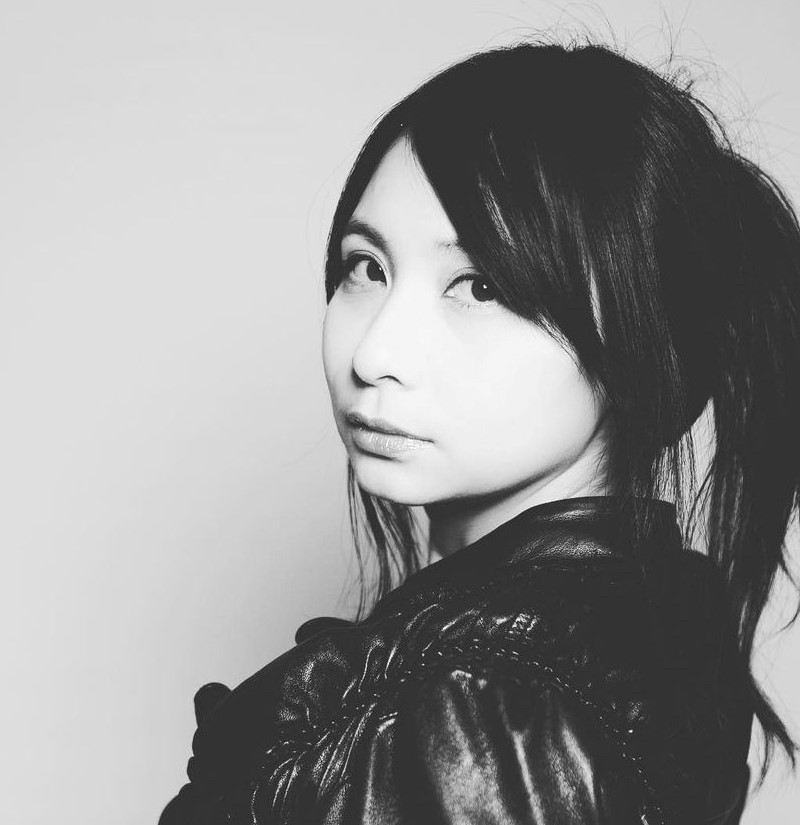公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。
「碁盤斬り」の白石和彌監督=下元優子撮影
2024.5.24
草彅剛「脚本理解が完璧」 白石和彌監督が絶賛した「碁盤斬り」の囲碁と復讐
ヤクザ映画、ロマンポルノ、アウトローものなど多彩な作品を生み出してきた白石和彌監督の新境地となった「碁盤斬り」。名作落語「柳田格之進」をベースの人情話と思いきや、復讐(ふくしゅう)劇も加えて殺陣も見せる、正攻法の時代劇だ。江戸時代の生きざま、京都の撮影所、リアルとけれんの融合など、時代劇映画の愉楽が端々にまで感じられる一本に仕上げた。
囲碁好き浪人の敵討ち
柳田格之進は身に覚えのない罪をきせられたうえに妻も失い、故郷の彦根藩を追われ浪人となって娘のお絹と江戸の貧乏長屋で暮らしていた。実直な人柄で、かねてたしなむ囲碁においてもウソ偽りのない勝負を心掛けてきた。ある日、囲碁で親しくなった萬屋の亭主、源兵衛の家で対局中に大金が消えた。格之進が疑われ、絹が吉原に身を売って金を都合する。一方、旧知の藩士から冤罪(えんざい)事件の真相を知らされた格之進は、復讐を決意する。
「凪待ち」(2019年)で組んだ脚本家、加藤正人からプロットとともに声をかけられた。「もともと時代劇を撮りたかったし、プロットが面白かった。人情話だけでは足りないと思った加藤さんが、復讐劇を加えた」。ぬれぎぬを着せられた浪人の復讐や、娘が吉原に身を売る話は既視感が強いのでは、と聞くと「パターンではあるが気にならなかった。初めて時代劇を撮るから、新鮮な気持ちだった。『またこれか』と思って撮る人とは、多分画(え)が違う。初めての分、ほかの時代劇と差別化できるという感覚があった」
そもそも、なぜ時代劇を撮りたかったのか。「江戸時代は不条理なことがとても多く、その中で自分の生き方を貫く人たちが好き。今回やってみて改めて感じた」。敵討ちもその一つということか。「敵討ちは江戸時代には当たり前のことで、今とは大きく異なる。現代劇より純度も高く多様な感情を浮き彫りにしやすい」と題材探しの段階から考えていたという。

懸念一掃 俳優の力に助けられた
懸念は、復讐の物語だった。「僕自身気持ちがそっちに行き過ぎがちで、人情話の良さをうまく転がせるか、(企画当初は)見えていなかった」。そして、最も気を配ったのは、単調で動きの少ない囲碁のシーンの見せ方。「あの手この手で臨場感を作り出した。撮り方に工夫を凝らし、観戦している取り巻きにどっちが優勢かなど小声で話をさせたりして、観客をドキドキさせようとした。囲碁好きにも楽しんでもらいたかった」
大金が紛失する場面も気になっていた。落語では源兵衛が囲碁に熱中し過ぎたことが原因だが「映像として成立するか、(源兵衛が)バカに見えてしまわないか」と考えた。加藤さんとも相談し「(紛失の場面は)見せない方がいい」と一致したものの、スタッフからは「見せないのは誠実じゃない」という声も上がったという。だが「現場で撮ってみたら違和感はなかった」。まさにこういう時に「俳優さんに助けられる」と実感した。
格之進は、旅に出てから大きく変化する。草彅は渋みと迫力を増し、殺気立つ雰囲気を醸し出した。「作品の真ん中あたりからテンションが一転する。後半は西部劇のように見えたらいいと思っていた。静から動へ、どう表現していくか。(演技の)勘がすごくいい俳優さんで、こちらからお願いしたことはほとんどなかった。脚本をしっかり読み込み、難しいところや理解できないところはないと言ってくれた」

今村力の美術は日本映画の歴史
美術の今村力は、白石監督のデビュー作「ロストパラダイス・イン・トーキョー」(10年)から美術監督として支えてきた。「今村さんと京都に行くのは一つの目標で、80歳までは頑張って一緒にやってくださいとお願いしてきた。ギリギリ間に合った」
「日本映画が長年培ってきた映画美術の歴史みたいなもの、その一部を今村さんが見せてくれた。いや、プレゼントしてくれたと思っている」。この作品でも至るところにその経験と腕がさえる。「吉原の大門の前の橋も、実際は映像で見えるほど大きくはない」。長く見える堀も、実際はせいぜい5メートルくらい。京都の撮影所に「緋牡丹博徒 お竜参上」(1970年)のセット図面が残っていて、これでやったらどうかという話になった。「80歳にしてアイデアが豊富」と全幅の信頼を置いている。「『ぼちぼち』と言っているが、もっと働いていただきたい」と言葉に最大限の敬意がこもる。
もうひとつ、スタッフと白石監督のこだわりの映画作りの例を挙げたい。室内が暗く、その分ろうそくの炎が際立っているシーンがある。「スタンリー・キューブリック監督の『バリー・リンドン』(76年)にある、ろうそくを光源としたシーンのルックを参考にした。ろうそくだけで撮ったとされているが、ベースの光があったのではないか」と話し合った。本作の明かりも暗すぎるかもと懸念したが「大丈夫だった。これ以上暗いと画に力がなくなるギリギリまでテストした」。

〝悪意〟を封印 王道で
白石監督作品の中では異色だ。理由の一つは〝悪意〟が影を潜めていること。人間の心の闇をのぞき込んできた。「ビターエンドが好きだが、脚本に〝悪意〟はなかった」と笑顔で答えた。「加藤さんは王道の作り方が好きで、そうできるのは『白石君ぐらいかな』と言ってくれた。自分が王道かどうかは分からないが、ありがたいこと」と照れながら話した。
初めて挑戦した時代劇を、どうとらえているのだろうか。「もはやSF」と言う一方で、「資料はたくさん残っている」。例えば、特殊な世界である吉原はいろいろな映画に登場する。「京都(撮影所)の人からは『江戸時代を見た人はいないから、面白いと思うやり方で』と言ってもらった。時代考証の先生も言葉遣いについて『昔とは意味合いが180度違う言葉もある。明らかな現代語でなければ大丈夫』と言われた」
さきほどの吉原の大門を出たところの橋。「自由にデフォルメしたことでドラマチックになった。意見はいろいろあるだろうが、表現とはそういうもの」と話した。撮影所の映画人も「とてもウエルカムだった。時代劇で必要なことは僕らがやるので、自由に進めてくださいと言ってくれた」。撮影所の協力を得て乗り切った。

未開拓なのは怪獣映画かな
白石監督は今年50歳になる。「残りの映画人生を考えた時、出発点になる作品」と本作を位置付けた。初めてのG指定(鑑賞年齢の制限なし)という。「以前はR15(15歳未満は鑑賞できない)ぐらいじゃないと映画じゃないと思っていたが、そういうのもなくなってきた。ファミリー映画も撮れるかも」と真顔で話し、こちらが驚いた。
「時代劇もまた撮りたいし、もちろん、R18やR15も撮る。ヤクザもポルノも撮ったし、あとの未開の地は怪獣映画かな」。多彩なジャンルを撮りながら模索するのは「肌に合っている」と言い、「新しくチャレンジすれば、その分野では新人。今回も京都では新人監督だったはず。衝動みたいなものを持ち続けるのは、監督としてのテーマでもある」。今作で時代劇を財産にした。進化はまだまだ止まらない。