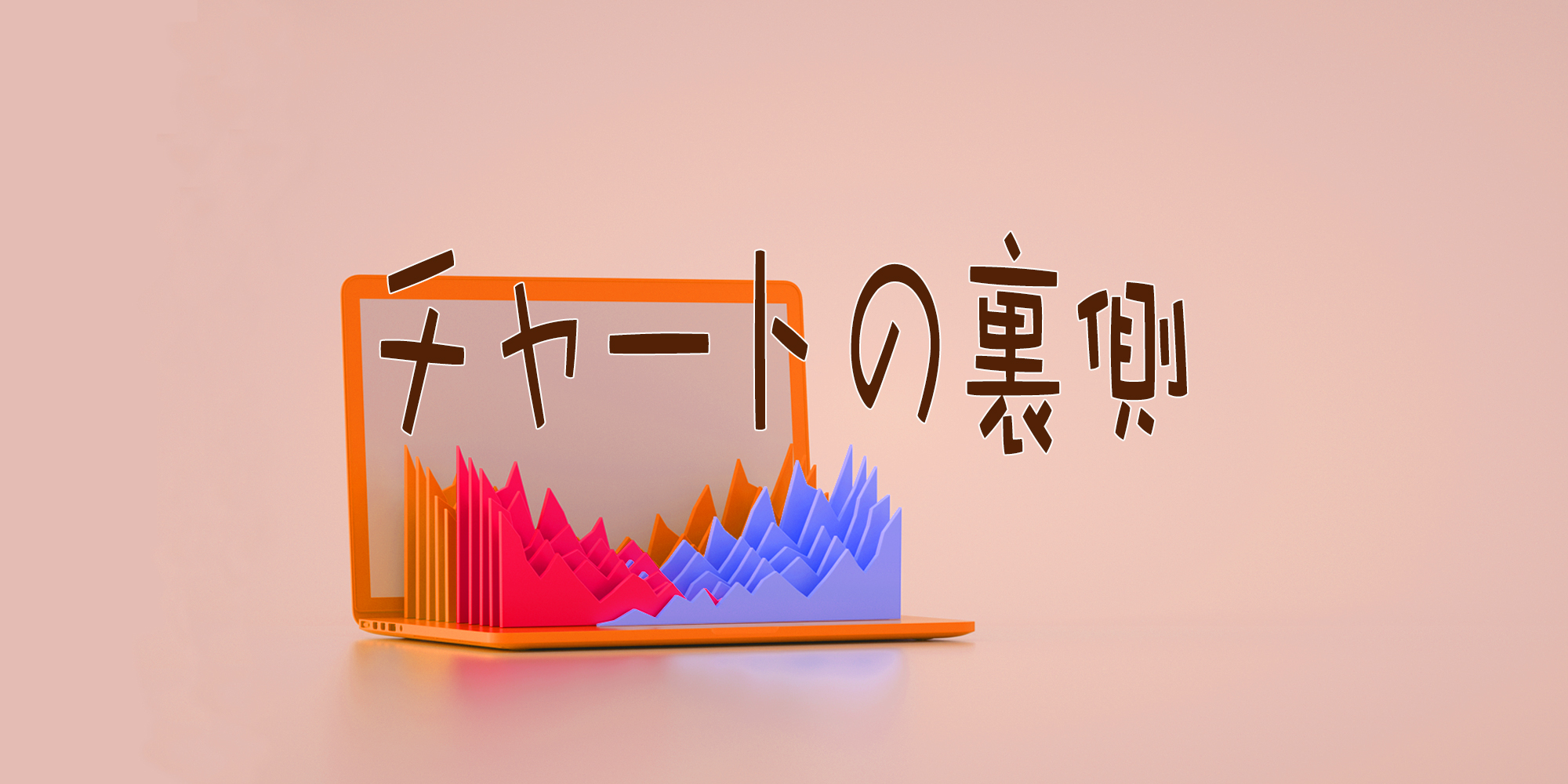毎週公開される新作映画、どれを見るべきか? 見ざるべきか? 毎日新聞に執筆する記者、ライターが一刀両断。褒めてばかりではありません。時には愛あるダメ出しも。複数の筆者が、それぞれの視点から鋭く評します。筆者は、勝田友巳(勝)、高橋諭治(諭)、細谷美香(細)、鈴木隆(鈴)、山口久美子(久)、倉田陶子(倉)、渡辺浩(渡)、木村光則(光)、屋代尚則(屋)、坂本高志(坂)。
シネマの週末
2024.6.14
チャートの裏側:心理の奥底に染みる恐怖
これはちょっとした驚きだ。「関心領域」という作品が、東京・メインシネコンの一番大きなスクリーンで上映されていた。公開3週目の土曜日である。第二次世界大戦下、ドイツ占領下のポーランドのアウシュビッツ収容所隣接の邸宅で、優雅に暮らすナチス幹部と家族を描く。
なぜ、新作や公開されて間もない話題作もあるのに、そのような上映の編成になったか。都心中心ながら集客がいいからである。いわば「格上げ」上映だ。興行収入の見込みは、現段階では4億円に迫るだろう。大きな数字ではないが、「ナチスもの」として健闘だと言える。
米アカデミー賞受賞があり評価も高いが、若い観客が目立っていたことに注目したい。ナチスを題材にした作品では珍しい。作風が影響している気がした。おぞましい収容所と、幸福に見える家族との対比軸に独自性があるからだ。画面の随所から、強烈な映像の電磁波が送り出されている感覚がある。
それが、人間心理の奥底に強烈に染み渡ってくる。身の毛がよだつ。かき乱される。震える。言い方はいろいろだが、表層的な怖さとは一線を画す。この受容のメカニズムは複雑とはいえ、観客は体で感じとることはできる。本作の特筆すべき点だ。若い観客は、それを敏感に受け止めたのではないか。チャートからは見えないことも多い。(映画ジャーナリスト・大高宏雄)