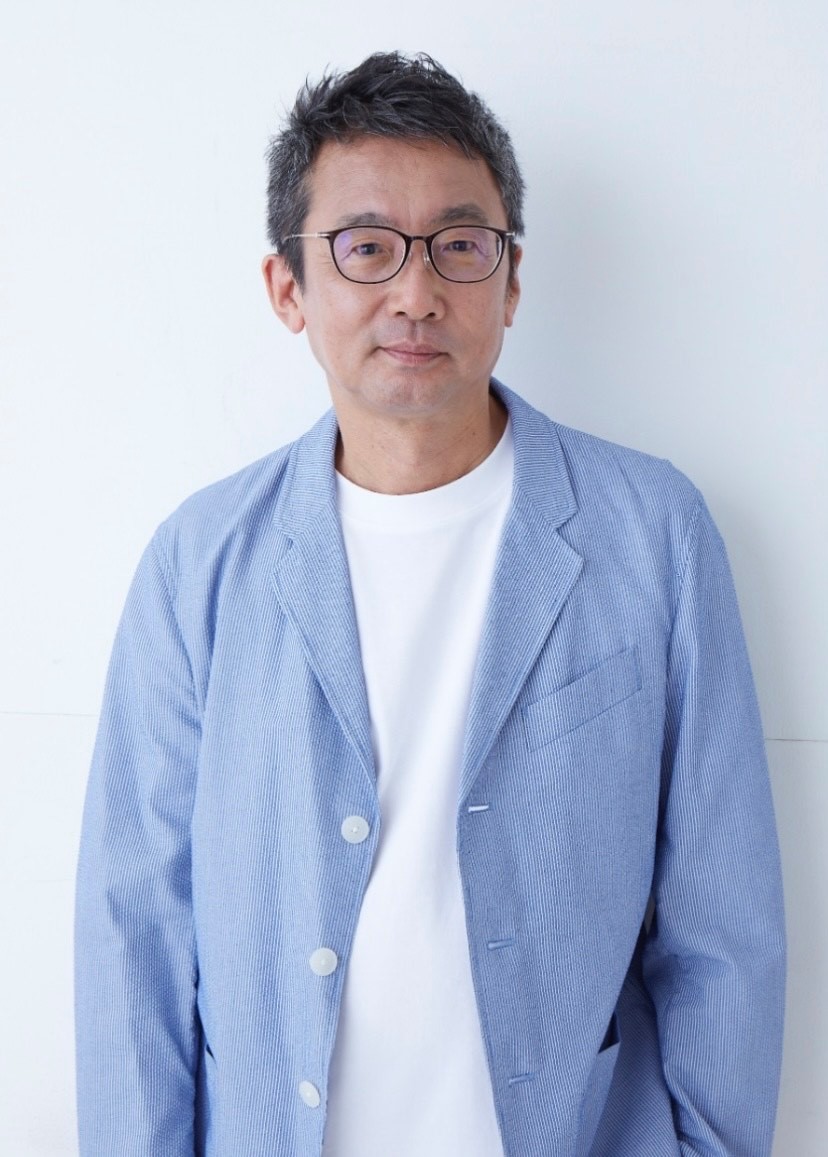音楽映画は魂の音楽祭である。そう定義してどしどし音楽映画取りあげていきます。夏だけでない、年中無休の音楽祭、シネマ・ソニックが始まります。
©️2024「トノバン」製作委員会
2024.5.28
大きなオープンカーでさっそうと現れた加藤和彦さんに会えたのは奇跡だった「トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代」
ある夏の日、ハワイ・マウイ島ラハイナスクエアの駐車場に大きなオープンカーでさっそうと現れた加藤和彦さんに会えたのは奇跡だったのかもしれない。
相原裕美監督とは
2018年に公開された「SUKITA 刻まれたアーティストたちの一瞬」をご存じだろうか。1970年代初頭にT・レックスの写真を撮るべくイギリスへ渡り奇跡的にデビッド・ボウイらと出会った鋤田正義。その後イギー・ポップ、日本ではYMO等のレコードジャケット写真で、ロックミュージシャンの撮影写真家として世界中のファンに認められた彼に迫るドキュメント映画である。被写体であるミュージシャンとそれを撮る鋤田の〝言葉では言い表せない対峙(たいじ)の関係性〟がこの映画ではうまく描かれている。この秀作をもって映画監督デビューしたのが相原裕美監督である(裕美といっても60過ぎのおじさまです。笑い)。その相原監督の3作目がこの「トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代」になる。
ドーナツ盤を手にして歌い踊った
加藤さんは47年3月21日生まれで僕の一回り上、存命ならば77歳である。小学生の僕はテレビから流れてきたどこかで聞いた事が有るような、無いような、マンガのような声と音で奏でられる奇妙な歌を聴く。当時のテレビマンの遊び心からか映像もサイケデリックな演出がなされていたこの曲に僕は熱狂した。ザ・フォーク・クルセダーズの「帰って来たヨッパライ」だ。まだ幼くラジオの深夜放送を聴かない僕らは、お兄さん、お姉さんより少し遅れてヨッパライのとりこになりドーナツ盤を手にして歌い踊った。そこにいたのが加藤さんである。
やがて中学生になりビタースウィート・サンバを口ずさみラジオの深夜放送常習聴視者と育った僕は日本語なのにロックでカッチョイイすてきなナンバーを知ることになる。サディスティック・ミカ・バンドの「タイムマシンにお願い」の登場だ。そこにいたのも加藤さんである。

リズム感良く描かれた音楽映画
私的な、一方的な加藤さんへのリーチはここまでにして、本作品は加藤さんが音楽家として生きた時代と、その時代を一緒に生きた人々が見て、感じて、忘れられない加藤さんへの思いが、リズム感良く描かれた音楽映画である。
ここで彼を語る証言者たちは同じバンドを一緒に組んだメンバーだったり、関係の濃かったミュージシャン、音楽関係者、ファッションデザイナーだったりと多岐に渡るが、誰も皆一流の匂いがある人たちばかりだ。それぞれの観点、それぞれの思いで加藤が語られていく。

多様な加藤さんをスクリーンに登場させる
それは時には明るくコミカルで軽妙だったり、色鮮やかでファッショナブルなパーティー会場のようだったり、真っ青な空を翼を持って自由に飛びまわるスマートな鳥に変身したようだったり、波ひとつない静かな海を優雅に渡るクルーズのようだったり、そして一転にわかにかき曇り嵐がおとずれた荒れ狂う空のようでもあったりした。
それぞれの証言は、それぞれのリズム感による、テンポと喜怒哀楽のコードの使い方で多様な加藤さんをスクリーンに登場させる。やがてそこには次世代のミュージシャンたちも加わり、加藤さんとその仲間たちが繋げた歌が新たに動き出す。少しだけ加藤さんの事を知っていたと思っていた僕は本作品を見ながら途中何度も涙がでてきた。証言者たちの思いがこちらに飛んでくるのだろうか、たくさんのそれぞれの思いが交差しながら加藤さんに近づけてくれているような「錯覚」を覚えた。

加藤さんの事をほとんど何も知らなかったんだ
そんな一つ一つの思いに、僕は本当は加藤さんの事をほとんど何も知らなかったんだとつくづくと思った。そして、「ある夏の日、ハワイ・マウイ島ラハイナスクエアの駐車場に大きなオープンカーでさっそうと現れた加藤和彦さんに会えたのは奇跡だったのかもしれない」と再度思い直したのでした。