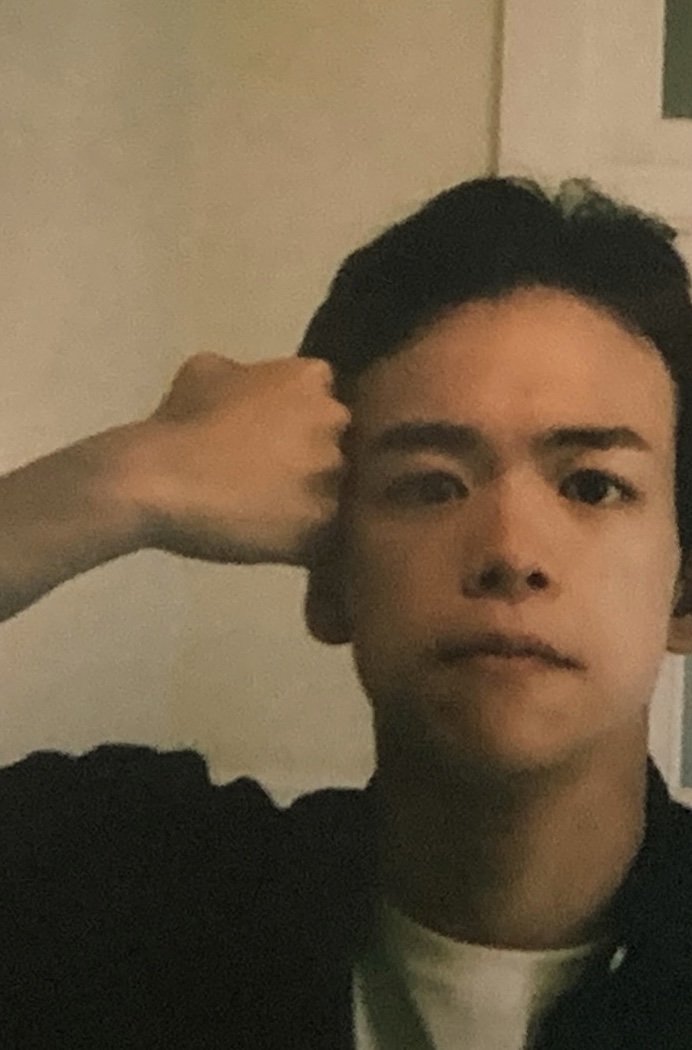毎回、勝手に〝2本立て〟形式で映画を並べてご紹介する。共通項といってもさまざまだが、本連載で作品を結びつけるのは〝ディテール〟である。ある映画を見て、無関係な作品の似ている場面を思い出す──そんな意義のないたのしさを大事にしたい。また、未知の併映作への思いがけぬ熱狂、再見がもたらす新鮮な驚きなど、2本立て特有の幸福な体験を呼び起こしたいという思惑もある。同じ上映に参加する気持ちで、ぜひ組み合わせを試していただけたらうれしい。
「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」© 2019 Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved.
2023.7.10
ディカプリオが読んでいたペーパーバックとあの恋愛映画の過激な回収本 「なに読んでるの?」で始まる物語:勝手に2本立て
今回は、映画と本の話。なにせ格好の映画本が刊行されたばかりなのだから、乗らない手はない。クエンティン・タランティーノが自らの監督作「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」(2019年)を改めて小説化した──とはいえ、細部にとどまらぬあまたの差異があり「ノベライズ」とは違う──「その昔、ハリウッドで」(文藝春秋)がそれだ。
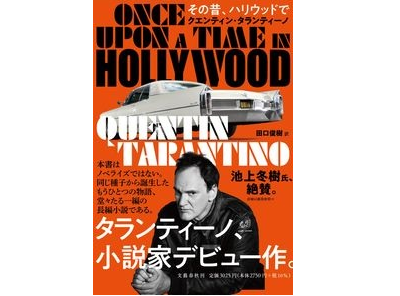
「その昔、ハリウッドで」クエンティン・タランティーノ著、田口俊樹翻訳、文藝春秋、2750円+税
自作を自ら小説化「その昔、ハリウッドで」
1969年の映画業界を舞台としている映画版「ワンス」以上に、小説版は内幕要素が増幅しており、構成も含めて全く別物。映画では印象的だった少なくない場面群がそもそも描かれない一方で、虚実入り交じる業界ウラ話、架空作を含む固有名詞がひしめく。
じつは公開当時、映画版にはノレなかった。終盤のとある思い切った歴史改変展開に、形容しがたい違和感、拒否感を覚えずにいられなかったのである。そもそも、タランティーノが歴史改変を扱った作品は初めてではなく、これまでは無邪気に楽しめていたのだから、単なる相性の問題といえばそれまでだし、いうまでもなく劇映画はフィクション=創作なのだから、私のアタマがカタすぎるのかもしれないが、架空人物たちの業界内幕話にゆったりと終始してくれたらどれほど良かったか、と思わずにはいられなかったのが偽らざる気持ちだった。
しかし本書は、映画版を好ましく思ったひとはもちろん、好めなかったとしても「別物」だからこそ楽しく読めるはずだ。そして、不思議と──私の場合、好んでいなかったのだから──映画を見直したくてたまらなくなる。これ以上に理想的な映画の小説化があり得ようか。
「なに読んでるの?」 役者ふたりの待ち時間
映画版と小説版、どちらにも登場し、ともに印象的な場面がある。
場所は、とあるテレビ西部劇のセット。役者ふたりが休憩時間に出番を待って座っている。ひとりは、かつてテレビ西部劇で主演を務めたものの、いまや緩やかな下り坂のさなかにあり、単発のゲスト出演などに甘んじている男優(映画版ではレオナルド・ディカプリオが演じる主役)。もうひとりは、8歳の子役女優だ。ふたりは初対面。並んで本を読んでいる。
「なに読んでるの?」──この言葉が発せられるのは、そのときである。声をかけたのは、年長俳優のほうだ。落ち着いた子役=年少者は、うれしそうにウォルト・ディズニーの伝記だと答え、「あなたは?」と聞き返す。
.png)
ただの西部小説だが……
年長側が読んでいるのはペーパーバックの西部小説。もともとはズボンの尻ポケットに入っていて、読むときも、読んでいないほうのページ側を背のほうに折り返すように丸めて片手で持つ、まさにペーパーバックに見合った読み捨てスタイル。
〝ただの〟西部小説さ……と返す言葉の通り、そう新奇性のある筋書きでもないのだろう書物のあらすじを、請われてきちんと説明してやるのがいい。しかも、説明しているうちに、どうやらそれまで自覚していなかった、西部小説内の落ち目の主人公と、キャリアが下り坂の自分自身の符合に気づき始めてしまうあたりが切ない。
ちなみに、映画では明かされないが、小説版には読書遍歴の描写があり、彼は若い頃からずっと気軽な大衆三文小説を読み続けていて、ミステリー、戦争もの、そして特に西部小説を好んでいること、作家の名前は覚えているが(おそらくありがちな筋書/題名のものが少なくないためか)タイトルや内容はあまり覚えていないということ、今まさに読み進めているのがマービン・H・アルバート(実在する)の「野生馬を乗りこなせ」という題の小説(こちらは架空)だということも分かるようになっている。
映画版でのふたりは、これ以降とりたてて多くの言葉を交わしはしない。けれど、小説版ではこの会話を入り口に、年の差を越えた、平等な演技者=共演者として、対話を重ねていくことになる。

「ビフォア・サンライズ 恋人までの距離(ディスタンス)」©Warner Bros. Entertainment Inc.
「なに読んでるの?」 見知らぬ男女、列車にて
記憶をあされば、「なに読んでるの?」から始まる関係性を描いた映画はほかにも思い浮かぶ。例えば、ブダペスト発パリ行きの列車内で隣り合わせた若い男女の一晩を描いた、リチャード・リンクレイター監督作「ビフォア・サンライズ 恋人までの距離(ディスタンス)」(95年)がまさにそんな場面から幕を開ける作品だった。
本作で「なに読んでるの?」の言葉が発せられるのは、開幕早々のこと。声をかけるのは、男性のほうだ。女性は無言で表紙を見せる──ジョルジュ・バタイユ「マダム・エドワルダ」と「死者」の合本、そして当然「あなたは?」。

クラウス・キンスキーの自伝だが……
男性が恥ずかしげに見せるのは、字幕によるならば「K・キンスキー自伝」となっている「All I Need Is Love」という本で、「K・キンスキー」は一度見たら忘れられない個性的相貌の怪優クラウス・キンスキー(26~91年)のこと。
なぜ単に表紙を見せるだけなのに、はにかんでいるのかといえば、読んでいる本を明かすさい特有の気恥ずかしさもないではなかろうが、これが「自叙伝」といえば聞こえは良いものの、実態はキンスキーの性豪自慢本だからだ。どこどこで誰々と……そんな描写が延々続く、問題含みのエロ自伝なのである。

選んだ本のエロチシズム
しかも調べてみると改めておかしいのが、これが88年英訳版だということだ。もともと、この本は75年にドイツ語で出版され、88年に英訳版が出たのであるが、これが内容ゆえ(あえて詳しくは述べない)に血縁者や関係者から訴訟まで起こされ、すみやかに回収された書物なのである。
本書は、いまや96年に再度刊行された改題版「Kinski Uncut」で手に入れることができるが、その経緯ゆえ元版からカットされた部分があるそうだ(題は「アンカット」なのに!)。再版バージョンは、どのみち撮影時点ではまだ手に入らなかったわけだが、それだけ問題の過激本を持っていたということ。見知らぬ女性に明かすのだから、恥ずかしがって当然だ。
このあと、ふたりは列車を降りて、ウィーンの街をあてどなく歩き回りながら、翌朝まで話し続けて関係を深めていくことになるのだが、残念ながら2冊の話題は掘り下げられない。とはいえ、バタイユの書物もまたエロチックな内容ではあるわけで、ふたりの選書は、その点において共通しているといえなくもない。
おまけで3本目
余談だが、もしいま「なに読んでるの?」と問われたら、私は「ヒート2」(ハーパーBOOKS)と答えることになる。そう、あの銃撃戦映画史に燦然(さんぜん)と輝くマイケル・マン監督作「ヒート」(95年)の続編小説である。こちらも5月に刊行されたばかり。「その昔、ハリウッドで」と併せて「映画小説月間」をお勧めしたい。
思い返せば「ヒート」も、「なに読んでるの?」から男女の関係性が始まる映画だった。強盗をなりわいとする男と書店員の女がレストランのカウンター席で隣り合わせ、一冊の書物を入り口として、次第に運命を交錯させることになる、悲しい映画だった。
「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」「ビフォア・サンライズ 恋人までの距離(ディスタンス)」は、U-NEXTで配信中。