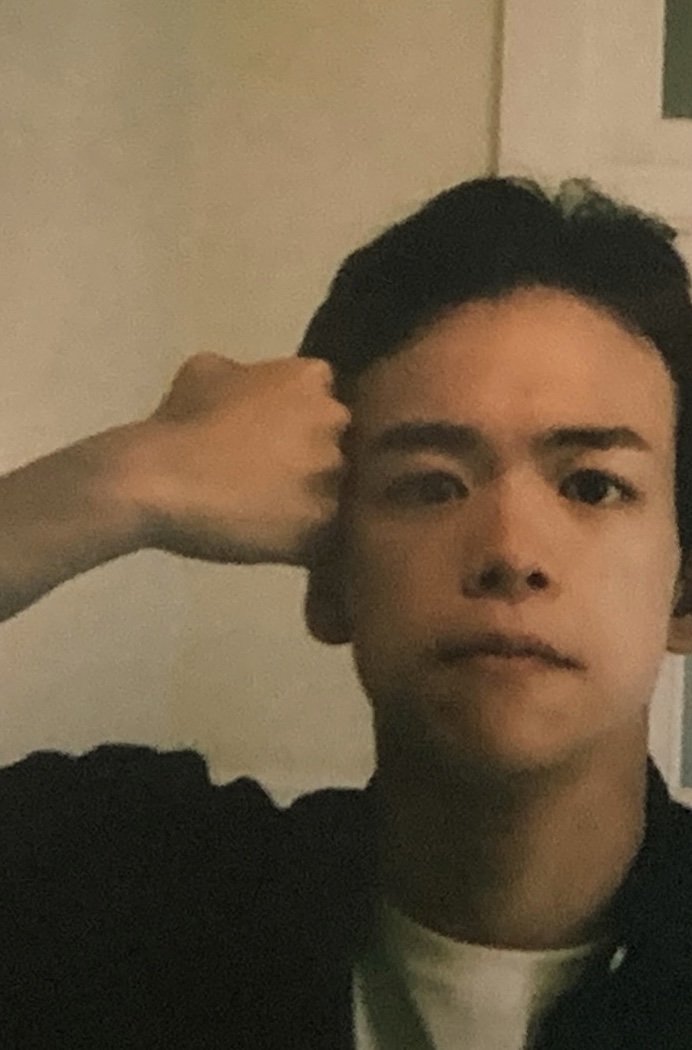毎回、勝手に〝2本立て〟形式で映画を並べてご紹介する。共通項といってもさまざまだが、本連載で作品を結びつけるのは〝ディテール〟である。ある映画を見て、無関係な作品の似ている場面を思い出す──そんな意義のないたのしさを大事にしたい。また、未知の併映作への思いがけぬ熱狂、再見がもたらす新鮮な驚きなど、2本立て特有の幸福な体験を呼び起こしたいという思惑もある。同じ上映に参加する気持ちで、ぜひ組み合わせを試していただけたらうれしい。
「関心領域」© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.
2024.6.05
リアル目指した「関心領域」のウソと違和感 「ありのまま」は難しい
公開から1週間たっているのだし、劇場パンフレットのみならず、いたるところで解説などもされているようだから、もはや細かな説明は不要であろう話題作、ジョナサン・グレイザー監督作「関心領域」を遅まきながら取り上げよう。
例によって本連載では、タイトルが示す本作の主題には触れず、いつものように素朴な(というより下世話な?)視点から作品を見ているときの印象について考えてみたい。まだご覧になっていない方は、できれば見てから読んでいただけたらうれしい。
カメラ10台 あらゆる角度から撮影
家のいたるところに幾つものカメラを設置して、屋内(ときに屋外)で生活する人物たちの「ありのまま」で「リアル」な行動を観察する──「関心領域」で目指されているスタイルはひとまずこのようなものと言っていい。
インタビューやメーキング映像に目を通せば、撮影現場のあらゆる位置からあらゆる方向を同時に撮影するべく最大10台ものカメラが設置され、機材準備を終えた段階で全スタッフが現場を離れ、入れ替わるように入ってきた俳優陣が思いのままに動き回りながら長時間演じ、監督をはじめとしたスタッフらは地下の待機場所でカメラを遠隔操作しつつモニターを確認する……という撮影方法が明かされている。監督いわく「壁にへばりついているハエのように登場人物をひたすら観察する映画作品にしたかった」とのことだ。
上記のようなアプローチを採用することで、あたかも隠しカメラを仕掛けた家のなかをのぞき見るかのような、定点観測的な映像の連なりが実現し、強制収容所所長一家の生活がきわめて客観的に描かれてゆくのであるが、その一方で「リアル」の仮構を目指した肝心の手法が、随所に違和感を生じさせているようにも思える。
映らないことの不自然さと違和感
それは、カメラが画面に映らないことだ。複数の定点撮影素材を組み合わせたかのように見える本作の映像は、見るものに撮影という行為、ひいてはカメラポジションを強く意識させるものとなる──「この部屋のこの位置にカメラが仕掛けられているのだな」という具合に。にもかかわらず、部屋のあらゆる位置からあらゆる角度を同時に撮影しているはずの映像に、まったく他のカメラが映りこむことはない。
もちろん、設置されたカメラがむきだしではなく、家具やら置物に擬態することで見事に隠されていると考えることも可能だろう(本来「隠しカメラ」はバレないための工夫がなされているものなのだから)。けれど作品を見進めるうちに、やはりそれでは説明のつかない撮影が随所に散見されることに気づくはずだ。
たとえば、ザンドラ・ヒュラー演じる主人公の妻が化粧をする場面。カメラはまず鏡に向かって化粧中の表情(および上半身)を右側から至近距離で捉え(①)、次いで背中側から距離をとって撮影された映像(②)に切り替わる。カメラの位置だけを考えれば、①のカメラは人物の真横にあるのだから、背中側から人物周辺を収めた②の映像に①のカメラが映り込んでいてよいはずである。しかしもちろんそうはなっていない。おそらく、まず横から撮ってから次に「もう一回!」と後ろから撮ったか、2台で同時に撮影した映像に映り込んでしまったカメラを画像加工して消しているのだろう(おそらく後者だろう)。

「気づかれないように」の中途半端さ
言うまでもなく、本来これらの撮影は問題にはならない。なぜならこれは劇映画だからだ。じっさいに隠しカメラで盗撮している=バレてはいけないわけではなく、あくまでも「隠しカメラ」風を装っている映像に過ぎない。役者は当然撮影されることを知っているし、演技中も周りのカメラが見えている。だから必要とあらばリテークすることもできるし、隠しカメラとしては明らかに無理のある横移動撮影(5回以上ある)も可能だ。
撮られている人物がカメラに反応を示さないのは、カメラの前で役者が演技をする、あらゆる劇映画に対して当てはまることなのだから、今に始まったことではない「そういうもの」、見慣れた約束事であって、いまさら違和感を覚えるほうがおかしいとも言える。
にもかかわらず、本作を見ながら違和感を覚えずにいられないのは、あたかも隠しカメラによる「気づかれないように撮っている」素材のように見せかけていながら、ときに食い違うポジションや隠す気のない撮影などの逸脱が見られるからだ。中途半端に不徹底だから目につくわけである。
撮られていると知っている「テラスハウス クロージング・ドア」
室内に複数台設置されたカメラで捉えられた生活という点で、本作はある種のリアリティー番組と比べることもできるだろう(監督もインタビューでリアリティー番組「ビッグ・ブラザー」に言及している)。一例として、ひとつの家で共同生活する男女数人のあいだに恋愛関係が生じたり移ろったりする時間を記録するリアリティー番組の劇場版「テラスハウス クロージング・ドア」(2015年)を思い浮かべてみたい。
映画「テラスハウス」もまた「関心領域」と同じく基本的に「家のいたるところに幾つものカメラを設置して、屋内(ときに屋外)で生活する人物たちの「ありのまま」で「リアル」な行動を観察する」スタイルだ。しかし、参加している人物たちが撮影行為を認識している点が異なってもいる。
それゆえ、撮影機材が「隠しカメラ」である必要はない(もちろん生活のノイズにならない程度に目立たないような工夫がされているだろうが)し、野外デートの撮影(あきらかにスタッフが同行している)なども違和感なく見ることができる。撮られていることを知っている人が撮られている映像だからだ。
映画「テラスハウス」の映像も、複数のカメラが同時に回っていながらカメラが画面に映り込むことがない点では「関心領域」と共通しているのだが、「あらゆる位置からあらゆる角度を同時に撮影している」わけではなく、ある一方向に撮影が偏っている。部屋のなかでもほとんど映らない区画があり、そちら側にカメラが集中していることがわかるのである。
あるていどカメラの位置に制約があるということは、すなわち明らかな死角があるということでもある。テラスハウスの住人たちには、見られたくない行為を死角で行うという選択がありうる(極端な例だが、当然のことながらトイレやお風呂なども出てこない)から、たとえ重要な出来事が描かれなかったとしても、必ずしも編集でカットされているとは限らないわけだ。

不都合な部分はしれっと省略
「関心領域」は、生活の外側をあえて「映さない」ことが主題と密接に結びついた作品なのだが、それとは異なる次元で、単に映されないものもある。
それは、性行為である。中盤、部屋に入ってきた女性(クレジットでは役名「赤毛の女性」、演じているのはアンナ・マルシニシン Anna Marciniszyn)が無言で椅子に腰掛け靴を脱いで脚を投げ出し結んでいた髪を解いて電話中の主人公に視線を送る場面がある。しかしその女性は次の画面には出てこない。編集点をまたぐと、どうやらすでに「事後」なのだ。主人公は蛇口で必死に局部についた行為の痕跡をゴシゴシと洗っている。
このように前後の場面が接続されれば、なにが起きたのか(省略されたのか)は容易に想像がつく。ならば行為自体を描かなくてもよいではないか、描いたのと同じではないかという見方もあろう。じっさい、直接的描写をせず観客に想像させる演出は決して珍しいものではない。作り手からすれば、いかなる深刻な題材であろうと、裸体が画面に映し出されれば「エロ」として消費される可能性を排除することはできないわけで、それを避けたいという事情もありうる(あるいは、作品によっては必要性を認識していてもレーティングの問題で諦めるということもあるだろう)。
不徹底さが際立たせた〝つなぎ目〟
とはいえ、特異な撮影スタイルによって「ありのまま」な感覚を醸成しようとしている作品でありながら、肝心の出来事を省略することは、恣意(しい)的な編集=つなぎ目を際立たせてしまいもするだろう。本作の登場人物はリアリティー番組と異なり、カメラの死角を認識しているわけではない(ことになっている)。要は、カメラの前では見せたくない行動はしないでおくという選択がありえないわけで、カメラの前で始まった行為は、カメラの前で起きているからには、そのまま記録されている状態が「ありのまま」であるはずだ。しかし本作はそうしない。起きたことをほのめかすにとどめ、どこか検閲的に、都合よく、ありのまま描写することからは距離を取る。
つまるところ、本作を見つつ感じる違和は、志向と画面とのズレというか、不徹底ゆえに埋まらない隙間(すきま)にあるのだろう。ひそかに生活をのぞき見る「ありのまま」のように見えて、「ありのまま」には無理のある撮影が随所で活用されるところ、不都合な時間をしれっと間引いているところに。
これらの違和感はあくまで「語り方」の次元にとどまるものではあるが、とはいえ、このような手法由来のノイズが、題名が示しているような意義ある主題──本稿ではほとんど触れていないけれども──について作品を見ながら深く考えることを妨げてしまう可能性に思いをはせずにはいられない。もしほかの手法が採用されていたならば、どうだっただろう。たとえばロングショット主体のワンシーン=ワンカットであったなら、感じ方はどのように異なっただろうか(あるいは、それほど変わらなかっただろうか)……と、いまもまだ考えている。やはり、いまいちど見直してみるしかないかもしれない。

「エンド・オブ・ウォッチ」©2012 SOLE PRODUCTIONS, LLC AND HEDGE FUND FILM PARTNERS, LLC
〝ロス市警のリアル〟を描いた「エンド・オブ・ウォッチ」
そんな「関心領域」を見ながら、ふと思い浮かべた映画がデビッド・エアー監督作「エンド・オブ・ウォッチ」(12年)だ。ロサンゼルスの制服警官を題材にした本作は、主題も手法も雰囲気も大きく異なるが、まるで人物たちの実際の日々を垣間見るかのような「リアル」の仮構が目指されている点で共通しているのである。
映画はまずパトカーに備え付けられたドライブレコーダーがとらえた銃撃戦で始まり、次いで警察署内のロッカー室で主人公がビデオカメラに向かって自己紹介をしたり装備を紹介したりする映像、さらに胸元につけた小型カメラがとらえた勤務中の映像、と続いてゆくなかで、主人公が警官として勤務する傍ら法学部入学を目指していること、入試課題のために日々の仕事を撮影していることがさりげなく説明され、本作が主人公による撮影素材によって構成されていくとわかる仕組みになっている。
とはいえ、じつは本作もスタイルの不徹底が気になる映画だ。手持ちカメラ、胸元の小型カメラ、パトカー内に固定されたカメラなどの存在がきちんと示される(しばしば映り込む)点は好ましいものの、誰が撮っているのかわからない映像が随所に平然と挟み込まれる。そのうえ性行為が省略される点も完全に「関心領域」と同じである。
つまり、「エンド・オブ・ウォッチ」の鑑賞もまた、かすかな違和感がつきまとう時間ということになってしまうのだが、けれども、「違和感」と書けばネガティブに思えるこの感覚、「入り込めなさ」もまた、じつは映画を見る醍醐味(だいごみ)のひとつと言える。すなわち、違和感を抱くという事実自体が、検討に値する興味深い出来事であるように思えるのだ。
「関心領域」や「エンド・オブ・ウォッチ」に限らず、作品を見て抱いた印象(もちろん違和感もそこに含まれる)について真剣に考えることは、たえず細やかな演出に注目し、効果を検討することの豊かな楽しさを教えてくれる。場所を選ばず、独りでできて、終わりがないのだから、これ以上ないほどありがたい、お得で刺激的な時間と言ってもいいほどだ。これもまた映画作品がもたらす余韻、余波のひとつのありかたであろう。
「エンド・オブ・ウォッチ」はU-NEXTで配信中。