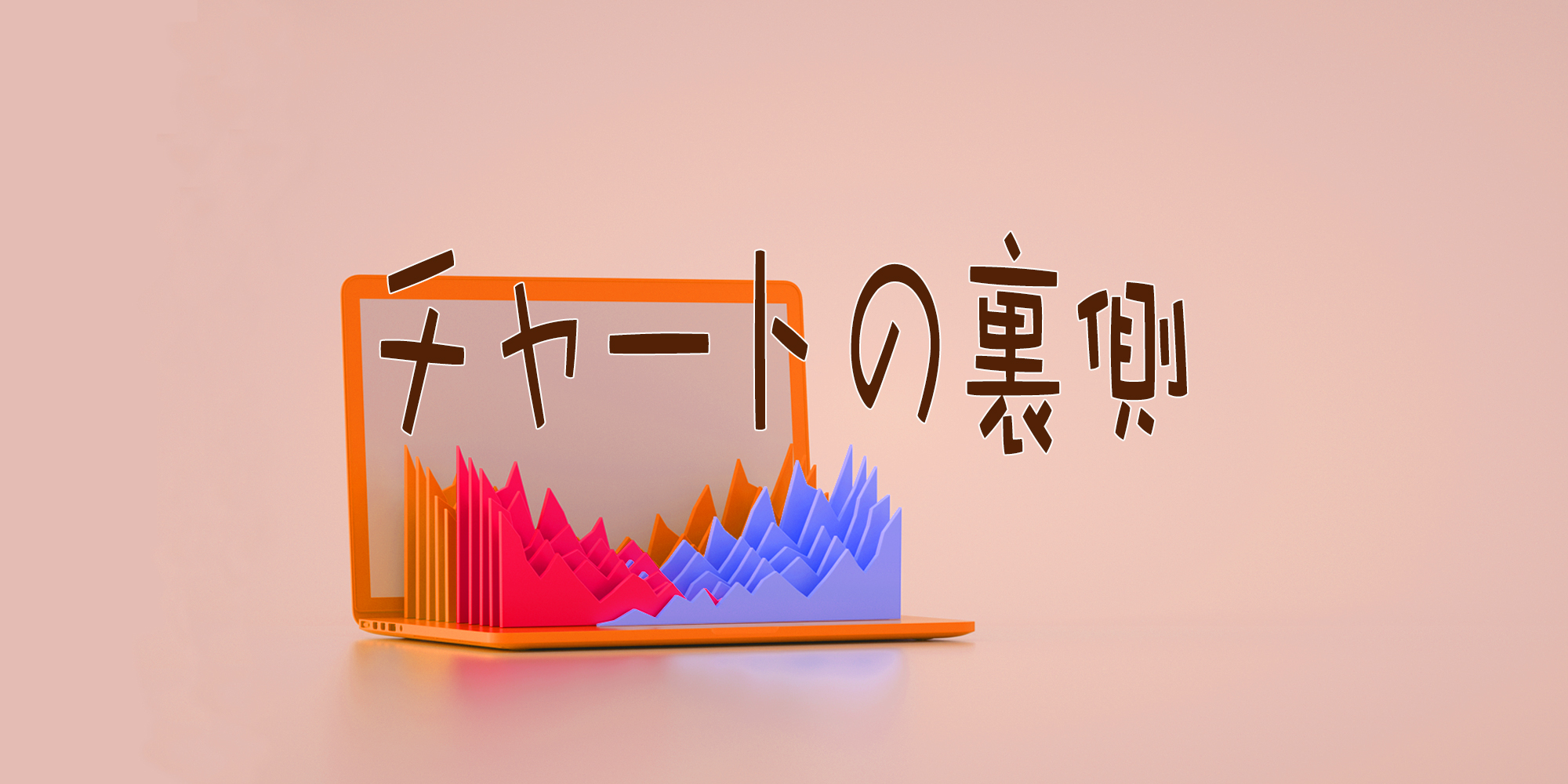公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。
「関心領域」早川書房刊 税込み2750円
2024.6.20
映画とは別物でも同様に恐ろしい 原作小説「関心領域」を読み解いた
アウシュビッツ強制収容所から壁を1枚隔てただけの場所で、幸せに暮らす家族を描いた「関心領域」が劇場公開中である。そして映画の公開と合わせて、原作小説マーティン・エイミス著「関心領域」の邦訳版(北田絵里子訳)も、公開同時期に早川書房より発売となった。
この小説は、大まかな舞台設定や主要登場人物は映画と共通しているものの、内容ははっきり言って別物だ。登場する人間の数も、共通している人物でさえもそのキャラクターの造形がまるで違う。しかしこの作品の根幹ともいうべき、「無関心さ」を浮かび上がらせ見る者をぞっとさせるような視点の巧妙な演出は、映画と原作の両方にある重要な共通点だ。本稿では映画と原作小説の違い、そしてそれぞれの良さについて触れてみたい。
原作の三つの視点 収容所長ルドルフ、連絡将校トムゼン、ユダヤ人シュムル
まずは主要なキャラクターについて。映画ではアウシュビッツ強制収容所の所長ルドルフ・ヘスとその妻ヘートビヒ・ヘスの2人を中心に展開していくのに対し、原作では3人の人物の視点が切り替わりながら、それぞれの主観で語っていくという形で物語が進行する。
その3人とは、所長のルドルフと、映画には登場しない若き連絡将校のトムゼン、そして被収容者でゾンダーコマンド(遺体の処理などを担うユダヤ人の特別労務班)の班長シュムルである。原作の各章は3人がそれぞれ一度ずつ語って次の章に行く流れとなっており、全6章と後日談というのが全体の構成だ。
映画と原作の両方で重要な役割を担う所長のルドルフは、多くの部下から誕生日を祝われるなどそれなりの人望を持った人物として映画では描かれていたが、原作では大酒のみでほぼ常に酩酊(めいてい)状態、自分のことを「正常」と連呼する異常で器の小さい人間として描かれているなど、キャラクターがかなり異なる(被収容者との不貞行為やその強要、パーティー会場に集まった参加者をいかに効率的に毒ガスで処理できるかを妄想するなど、ネガティブな面での描写には共通点も多い)。
原作の物語 カギ握るヘートビヒ
若き将校トムゼンは、ナチ党全国指導者で総統秘書の叔父を持つ自信過剰な政治家タイプ。このトムゼンが、ルドルフの妻ヘートビヒに一目ぼれするところから原作は幕を開ける。映画でザンドラ・ヒュラーが演じたヘートビヒは、夫の精神的な支配からあらゆる方法で逃れて振り回す妻として、また成就のかなわぬ一目ぼれの恋の対象として、ルドルフとトムゼン両方のパートにおけるキーパーソンとなっているのだ。
そして唯一の被収容者であるシュムルは、ルドルフとトムゼンほどは長く登場しないものの、強制収容所内の様子を客観的に、そして淡々と見つめる視点として存在する。語り手となる3人の中でシュムルは唯一敬語で話す。その落ち着いた語り口からは絶望しつつも達観した様子が垣間見える。ちなみに、原作における収容所所長夫婦の名前は、パウル・ドルとハンナ・ドルである。モデルとなった実在の人物(ルドルフ・ヘス、ヘートビヒ・ヘス)の名前を変えて小説にしたのを、映画化の際にジョナサン・グレイザー監督が本名に戻したという経緯がある。

映画「関心領域」© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.
独自演出加えたグレイザー監督
原作から大きく変わって(または追加され)、映画オリジナルとなったシーンも多い。例えば、川で釣りをしていたところへ遺灰と思われるものが大量に流れてくるシーンや、ヘートビヒの母親が家を訪ねてきてしばらく滞在するシーン、博物館となっている現代のアウシュビッツなどは、映画独自の印象的な場面となっている。
これらは、ホロコーストをあえて直接的には描かないことで残虐性を際立たせる手法を取った映画における、ジョナサン・グレイザー監督独自の演出だろう。夜中に果物を配る少女を追ったモノクロのシークエンスは、監督がポーランドで、12歳の時にレジスタンス活動をしていた女性に会ったことがきっかけとなり、追加された。脚本の執筆前に2年の時間を割いてリサーチを重ねた監督が、原作の要素に調査結果を加える形で表現したかった部分なのかもしれない。
メディア特性を生かした描写と演出
虐殺の直接的な描写がないのは、映画も原作も共通する。興味深いのは、両者でその形が異なるにもかかわらず残酷さを伝えるという点で同じ効果をもたらしていることだ。映画では収容所内の映像は出てこないが、壁の向こう側に見え隠れする煙や炎、また銃声、叫び声などの音が嫌でも絶え間なく耳に入ってくることで、ホロコーストの影がある意味で、観客にとっても慣れたものになり、そして日常化してしまう仕掛けとなっている。
一方原作は、トラックで運ばれていく遺体の山など、ビジュアルとして想像してしまう残酷なシーンはあるにはあるが、銃の引き金を引く瞬間や、毒ガス室で苦しむ人々といった「死の決定的瞬間」は文字に起こされていない。しかし先ほどまで話していた人物がページをめくると遺体となって運ばれているような、「決定的瞬間」の時間を飛ばすことで残虐な行為がいともかんたんに行われているという事実が際立っている。
映画は「映像」と「音声」、小説は「文章」のメディアであるという点で表現に違いが出るのは当たり前のことではあるが、ホロコーストを直接的に描かないという大きな特徴を、それぞれのメディア特性を生かして作品に昇華しているのだ。
「視点」は違えど効果は同じ
原作小説から映画になる際に、その形は変わったものの同じ効果をもたらしている重要な要素がもう一つある。それは誰の「視点」かという観点だ。ジョナサン・グレイザー監督は2014年に出版された原作を読む前に、その宣伝文を見かけたことから作品の「視点」に興味を抱いたという。そもそも「関心領域」にひかれたきっかけが「視点」だったのである。
原作には多数いる登場人物が、映画では所長夫妻を中心に絞られたという話は先述の通りだが、重要なのは、監督がゾンダーコマンドの班長シュムルの視点も削ったということ。つまり映画では、唯一のユダヤ人だったシュムルの視点がなくなり、ナチス・ドイツ側のみの視点で語られているのである。ユダヤ人視点がなくなり、むしろなくしたからこそ、見え隠れする断片や音などが観客の想像力を引き出しているのが、映画の大きな特徴と言える。
原作はというと、視点は多いが、恐ろしいのはその全てが並列化されてしまっているという点だ。死と隣り合わせになりながら同胞の遺体を処理しなくてはならないゾンダーコマンドの絶望と、収容所長の妻への嫉妬心、若き将校の自尊心などが、同じ日常の一部として語られる。ルドルフが、死亡者数の計算には頭蓋(ずがい)骨を数えるのかそれとも大腿(だいたい)骨を数えて2で割る方がよいのかを議論しているそばから、妻のひそかな文通相手が誰なのかをあれこれ詮索するという頭の中を、読者はのぞかなくてはならない。

映画「関心領域」© Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.
アカデミー賞受賞が証明した音の演出
このように原作と映画では内容が異なるものの、どちらも残酷な状況を平然と扱う登場人物の異常性をどう受け止めれば良いのか分からなくなってしまう。同じ効果をもたらしているのは、それぞれの媒体特性に適したアプローチがなされたためではないだろうか。
その証拠に、映画「関心領域」は音による演出が評価され、第96回米 アカデミー賞で音響賞を獲得している。すでに映画をご覧になった方でも、「音」に注目し、原作小説において「音」がどのように表現されているのか気になったという方も多いだろう。
小説及び映画「関心領域」は、虐殺の場面を、直接的に見せないという類いまれな切り口で表現したというだけでなく、その両方を楽しむ組み合わせの中でも、独創的な存在感を放っている。