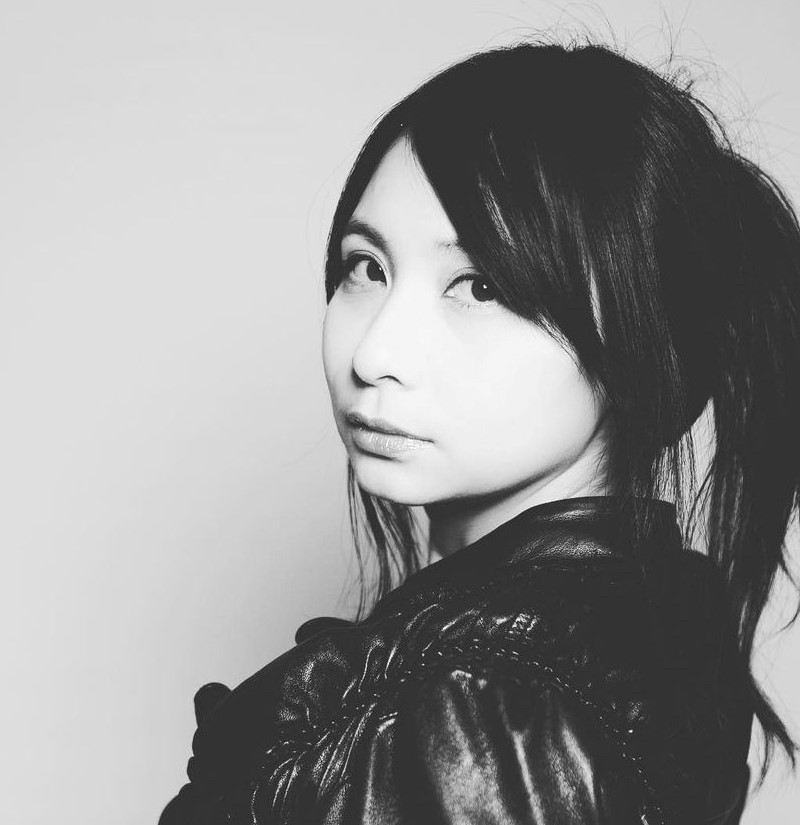公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。
「ディア・ファミリー」などのプロデューサー大瀧亮さん
2024.5.22
大ヒット「ゴールデンカムイ」プロデューサーが手がける「ディア・ファミリー」奇跡的な流れが公開までつながった愛の実話を映画化
現在公開中の「ゴールデンカムイ」、「ミッシング」、6月14日公開の「ディア・ファミリー」(毎日新聞社など製作委員会)と話題作のプロデューサーを務めた大瀧亮。内容、成り立ち、スタイルなど大きく異なるが、3作とも注目度は圧倒的に高い。映画のとっかかり、企画段階から2次利用まで一つの作品に長期にわたって一緒に歩み、生みの親であり、育ての親としてかかわってきた。「大切な子供が成長する過程が楽しみ」と話す大瀧の作品へのアプローチ、所属するWOWOWの映画戦略の一端について聞いた。
新たな一歩を踏み出した「ゴールデンカムイ」
「ゴールデンカムイ」は野田サトルの大ヒット漫画の実写映画化。WOWOWは2021年秋に映像化権の獲得にエントリーした。コロナ禍で大手の配信業者が国内マーケットに参入して実績を押し上げ、業界が大きく変化していた時期だ。上質なドラマを作ってきたWOWOWにとって正念場となり、危機感も覆う中で「映画もドラマも作れる前提で映像化権を取りにいった」と話す。TBSテレビと共同制作した「MOZU」などはあったものの、「ゴールデンカムイ」は「はじめましてと言えるほど大きな作品へのチャレンジだった」という。
映画化権は手に入れたものの、22年4月末の実写化発表(活字のみ)の際のファンの反応は「ネガティブが8割」と予想されたこととはいえ、ファンの原作愛の高さを再確認するものだった。原作へのリスペクトは絶対不可欠、として「作品に関わる全員が細部まで読み込んで準備にとりかかった」。それが奏功してビジュアルや映像など2回目の発表を行った23年8月末の解禁への反応は「正反対の8割以上がポジティブに変わった」という。
実際に公開中の映画は大ヒット中だ。「脚本段階から野田先生や発行元の集英社と入念な意見のやり取りを繰り返し、リアリティーにも配慮して製作した」。アイヌのコミュニティー、史実に沿った部分、グルメなど専門家の監修を多方面にわたって導入。「漫画から実写への転換の難しい部分も克服した結果」とみている。今秋WOWOWで続編となるドラマ版の放送・配信開始予定、そして更にその先の続編映画版も構想中で準備に余念がない。

©野田サトル/集英社 ©2024映画「ゴールデンカムイ」製作委員会
吉田監督と伴走した「ミッシング」
「ゴールデンカムイ」とは全く異なる進め方だったのが吉田恵輔監督の「ミッシング」だ。大瀧は、吉田監督の「空白」を見て感動した。「人は苦しみとどう折り合いをつけていくかというテーマに共感。吉田監督と仕事をしたい一心で、次の企画に関わりたいと『ミッシング』の企画を進めていた河村光庸さんがいた会社スターサンズの門をたたいた」
「吉田監督に全幅の信頼を置き、基本的にやりたいことをフルに撮ってくださいというスタンス。伴走させてもらった」。河村は撮影前に急死してしまったが、後に残ったメンバーが遺志を受け継いだ。プロデューサーとして考えたのは「2時間つらいだけの作品に観客は足を運んでくれないと考えた。大事にしたのは、最後に人のやさしさに触れられること」と話した。大瀧の言葉がより力強くなる。「苦しい場面の連続だったが、最後に見える一筋の光がこんなに大きく見える。それが担保できる脚本と演出、仕上げだった」
配給をワーナーにお願いし、吉田監督作品の中でも規模の大きい250館規模での公開を決めた。河村も「ぜひ」と話していたという。それにはメジャーのキャストをそろえることも不可欠だった。作品は誹謗(ひぼう)や中傷があふれる現代社会、報道機関の裏事情なども交え「時代を切り取る作品。被害者が加害者のように扱われる世の中の今を映し出した。現代的な事象を映し撮った分、10年後には『あんな時代もあったのか』と思える作品になったかもしれない」と語った。

©2024「missing」Film Partners
この物語をどうしても伝えたい「ディア・ファミリー」
「奇跡的な流れが公開までつながっている」と話すのが「ディア・ファミリー」である。原作者であるノンフィクション作家の清武英利が追いかけてきた実話を同僚から引き継いだ。町工場の社長、筒井(映画では坪井)宣政さんが娘の命を救おうと人工心臓の開発に専念、亡くなってしまった娘との約束で心臓治療の医療器具IABPバルーンカテーテルを開発していく物語だ。「実話とは思えないくらいパワーを感じた」

©2024「ディア・ファミリー」製作委員会
当時、東宝も筒井さんのドキュメンタリーを見て映画化に向け動きだしており、一緒に進めることになった。清武の取材メモから林民夫に脚本を依頼。数々の余命ものを手がけ自身も2児の父親であり「絶対やりたい作品」と言った月川翔を監督に指名した。「家族が病気になり亡くなる悲しい話ではなく、そこを起点に家族が団結して新しいものを作り、それが今の時代に受け継がれ、世界中でたくさんの命を救っている。とても希望や夢のある物語」と製作への強い意欲が大瀧を支えた。物語の中間あたりで、娘が「私の命は大丈夫」という場面がある。「その先の家族の姿がすごい。多くの人に体感してもらいたい」。18年から6年かけて公開にこぎつけた。「この物語を伝えたい」という思いからだった。
一方で、会社や医療、大学などこの実話に関わってきた方も多く、エンターテインメントとして見せる上でフィクションにしたところもあった。「筒井さんの過去の経験があってこそ、カテーテルの開発につながったことを目で見えるように苦心した」。大瀧は清武の取材にも同行して、筒井さんとも何度も話をしてきた。長い年月、苦楽をともにしてきたのである。「見てくれた人が一人でも多く喜び、感動してくれたら救われる作品」
世に送り出す瞬間の感動
プロデューサーとして「大変なことやつらいことがあってもマインドリセットして、最後は一人の観客として、(作品を)子供と思って見る。元々(藤原竜也の)マネジャーをしていたので、一番近くで俳優やコンテンツと向き合っていたいと思ってきた。彼らが世に出る瞬間のお客さんのリアクションを見て感動させてもらってきた」。
大瀧の話の端々に、作品製作の先導者として粘り強く前向きに進んでいく姿が見える。「ディア・ファミリー」の主人公、筒井さんに通じる部分を感じる。「シンパシーは感じます」。立場上、どうしても調整ごとは多くつきまとう。「大変なこともあるが、自分が投げだしたら、それで全部終わってしまいますから」と前を向く。もう一つ大切なこととして、今の映画作りの主流ともいえる製作委員会方式を挙げた。「皆さんにお願いし、助けられたこともたくさんある」と好意的にメリットを受け入れてきた。
ビジネスチャンスの発掘と挑戦
大瀧の考えには当然ながらWOWOWのスタンスや方針が見える。「サブスクビジネスの選択肢がたくさんある中で加入者の満足度を担保していくとともに、プロデューサーが結集して生み出すコンテンツをWOWOWの外でも見てもらうこと。既加入者にはもう一度、そして加入していない人は初めて楽しんでもらい、収益がたつことも推進していく」。音楽の分野ではすでに、ライブ番組の画と音を再編集し、映画館で見てもらうためのラグジュアリーな展開を始めている。
映画の世界でも、配給機能を学び劇場営業やブッキング、宣伝業務ができるよう研さんを重ねている。ビジネスチャンスを太い幹にしていくための人的リソースを強化してきた。もう一つ大事なことを指摘した。「映画業界は企画、営業、配給、宣伝、2次利用と分業体制になっているが、WOWOWにいることでその全部をやっていく。18年くらいから分業という概念は取り払ってやってきた。営業の大変さ、配給や宣伝の難しさも身に沁みて分かった」というのだ。
収支で見ても、配給会社にとっては多くの作品の中の1本だが「WOWOWにとっては一球入魂」の1本。この思いを最後まで発信しないといけない」と話す。さらに、「ゴールデンカムイ」に関わったことで、「今まで経験したことのない枝葉に分かれたビジネスチャンス、『ゴールデンカムイ』があるからこそ劇場公開だけでなく商品化できるもの、付帯で見えてくるビジネスがたくさんあった。例えば、音楽チャンネルがあるからできたことだが、主題歌を担当してもらったACIDMAN(アシッドマン)のオリジナルライブをWOWOWで蘇生してライブ興行、放送もする。劇場公開の宣伝にもつながる。多層的な取り組みになっていった」と語った。