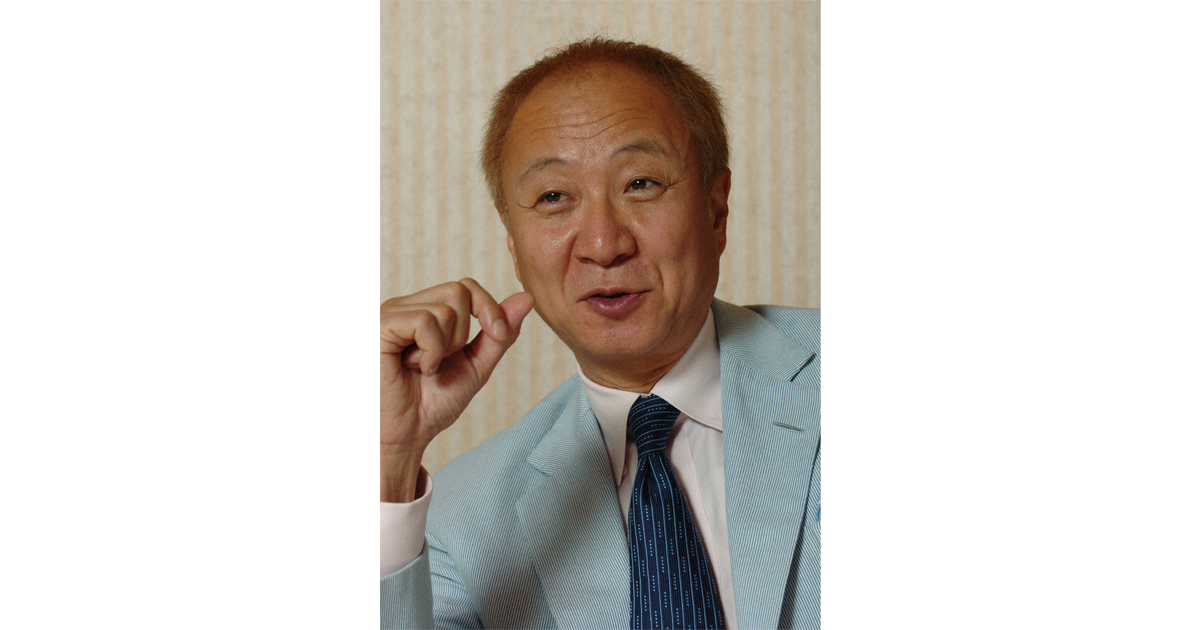音楽映画は魂の音楽祭である。そう定義してどしどし音楽映画取りあげていきます。夏だけでない、年中無休の音楽祭、シネマ・ソニックが始まります。
「トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代」
2024.7.03
なぜ今「トノバン 加藤和彦」なのか 同時代伴走したベテラン音楽記者の目に映った〝昭和の天才〟
この映画「トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代」ができたと聞いた時、周囲の音楽関係者は「なぜ、今?」といぶかった。彼らは、加藤和彦が「天才的発想と行動力を持った音楽家」であると知っている人々である。いや音楽家としてだけでなく「人格」「存在」として付き合っていた方々もいる。ただ、話していて「確かに、彼のことを記録としてちゃんと残していなかった。僕らもじきにいなくなっちゃうから、そんなタイミングかもね」という結論に落ち着いたものだ。そして、こうやって映像を見ると「よくできている」という感想と「そんな人だったっけ」という気持ちが相半ばする。それは、彼と同じ時代を生きてきた人間の目と、今のこの時代から彼を振り返る視点の差なのかな、と感じるのだ。
世界的サウンド 「美的人生」の象徴的存在に
まずは、映画の主人公・加藤和彦を紹介しよう。ベビーブーム真っただ中の1947年3月に京都に生まれ、大学時代からプロの音楽活動を始めた。バンド「ザ・フォーク・クルセダーズ」の解散記念として発表した「帰って来たヨッパライ」が67年、社会的ヒットになる。次作予定の「イムジン河」が北朝鮮まで巻き込んだ大騒動になって発売中止になるが、代わりに出したコミックソング「水虫の唄」もヒットする。
ソロになってからは、欧米の先端音楽から世界の民族音楽まで視野を広げて学び取り、71年「サディスティック・ミカ・バンド」を結成して世界レベルのサウンドを生み出す。70年代半ば再びソロに戻ると、トップ作詞家・安井かずみと結婚。80年代にかけて映像や舞台、アニメと活動の場を広げるとともに、ファッションや料理、生活スタイルなど「あこがれの美的人生」を提案する象徴的存在にもなる。
その後も、活発な活動を行う中、安井が94年に死去。2009年10月2日に松任谷由実のコンサートにゲスト出演した半月後の17日、軽井沢のホテルで遺体で発見される。これが、音楽人名録的加藤像である。
〝最高の瞬間〟共にした人たちの証言
この映画でも語られている通り、加藤は、ほぼ音楽的天才である。その派生として洗練されたセンスがライフスタイルににじみ出たと感じられる。どうやら加藤は、どんな時も最高に美しいものを探し、手に入れると、また見たことのない「新たな最高」を探しに行っていたようだ。映画は、その折々の最高の瞬間を共にした、あるいは目撃した人々の証言ででき上がっている。
最高を探し尽くし味わい尽くしやり尽くしたのか、加藤は自ら命を絶つわけだが、その理由が本作で明らかになったわけでもない。映画に登場するきたやまおさむの見立てがほぼ正答であろうと、想像するのみである。

時代の先行く〝天才〟から〝変人〟へ
では、なぜこれほどまでに、加藤和彦が死の直後でなく「今」話題になるのか。
冒頭にも触れたが、同時代の空気を吸ってきた者には、加藤は常に何歩も前を走り続けて追い付けない憧れであり、見方を変えれば憎たらしい存在だった。このことを大抵の人は感じていた。裏を返せば「知りはしないが後ろ姿は見慣れた人物」だったのだ。
ところが、令和の時代から見直すといわゆる「変人」である。命を削ってまで何かを追い求める必要や根拠や動機があるのか。若い人々はそう問うに違いない。昭和では見慣れていたものが令和では違和感を持たれる。その逆目をなでられるような肌触りが、時代の興味を引くのではないか。
才能散財したレジェンド
戦前の文化も含めて昭和時代は「無駄」や「無意味」に対して寛容だった。若旦那がぜいたくをして身上(しんしょう)をつぶしても、笑える一夜話だった。もちろんそれで泣く人はいたろう。現代社会は泣く人だけが大切であり、「無駄」「無意味」は「ぜいたく」としてできうる限り排除される。あれだけデザインも機能も豊富で華やかに展開されていた「ガラケー」は、白物家電のような個性のないスマホに取って代わられた。あの素晴らしい日々を送っていた加藤に、進化系統樹の先端まで到達したガラケーの華やぎを見るのは失礼だろうか。今の若い人々には加藤が「無駄に才能を散財したぜいたくの極みの」輝かしいレジェンドに映るのではないか。
ただ、疑問が残るところがある。相原裕美監督は、「加藤が正当に評価されるべきだ」という一点だけで、この映画を撮ったのだろうか。そのことと「加藤とは何であったのか」を探ることとは少し違う。音楽関係者は以前から「正当に評価」していたからだ。もし「加藤とは何であったのか」の解を求めるのならば、3人の妻(安井は亡くなっているが、著作は多い)の証言が必要であったろう(監督は百も承知であろうが……)。そこは、積み残しの大切な荷物のような気がする。

相原裕美監督が誠意込めた加藤和彦像
音楽記者を30年以上やっているので、加藤を含め登場人物のほとんどと面識がある。また、長い間取材をしていると、人は、問いに「すべて」本当のことを答えるとは限らないということを学ぶ。「うそはつかない」が「完全な真実ではない」ということが少なからずあるのだ。実は本人が書いた自伝よりジャーナリストの評伝の方が信用できる場合が少なくない。ジャーナリストの技は、多数の証言の中から真実を類推して抽出し、それを重ね合わせて対象を浮き彫り、透かし彫りすることである。
つまり、現れた像はジャーナリストの誠意を担保に入れた、極めて真実に近いであろう創作物なのである。このドキュメンタリーで浮かび上がってくる「トノバン」は、相原監督が誠意を込めて作り上げた、見事な人格であることは間違いない。
加藤の肉声が知りたければ、書籍の「あの素晴しい日々」(加藤和彦・前田祥丈著)の方が詳しいだろう。また、安井かずみに関しては証言集「安井かずみがいた時代」(島崎今日子著)も参考になる。