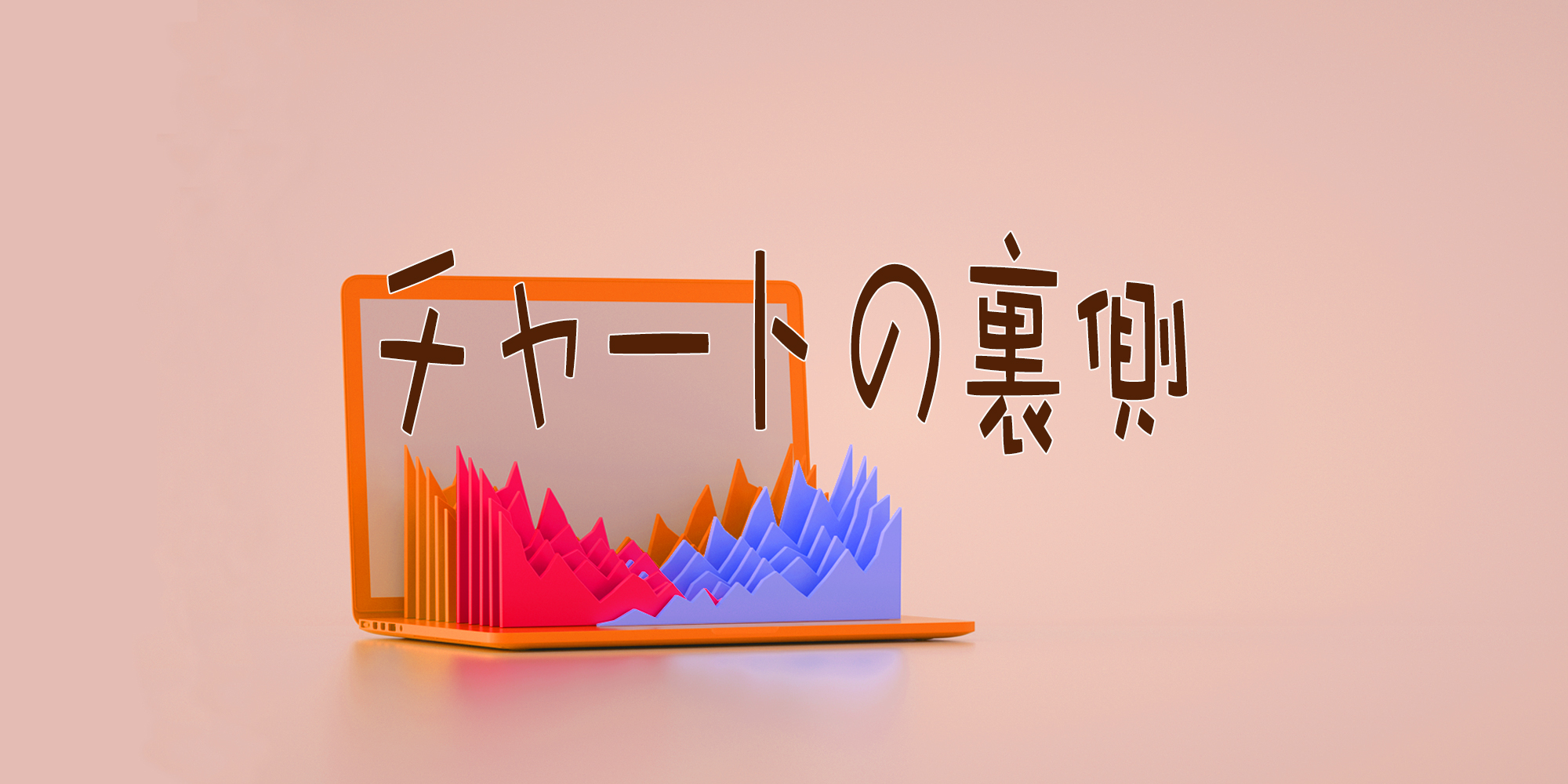映画の魅力は細部に宿る。どうせ見るならより多くの発見を引き出し、よりお得に楽しみたい。「仕事と人生に効く 教養としての映画」(PHP研究所)の著者、映画研究者=批評家の伊藤弘了さんが、作品の隅々に目を凝らし、耳を澄ませて、その魅力を「よくばり」に読み解きます。
「室井慎次 敗れざる者/生き続ける者」で室井が住む家©︎2024 フジテレビジョン ビーエスフジ 東宝
2024.11.27
「室井慎次」が黒澤明、イーストウッドから〝盗んだ〟もの 次に見るべき1本への道しるべ
テクストとは、無数にある文化の中心からやって来た引用の織物である。(注1)
あらゆる表現行為はつねにすでに「盗用」と骨がらみである。およそ盗用でない表現など存在しない。いまここに書かれつつある私の文章とてその例外ではない。「盗用」がドギツク感じられるようなら「流用」や「奪用」でもいいし(いずれもアプロプリエーション[appropriation]の訳語である)、さらにソフトな表現を望むのであれば(バルトに倣って)「引用」としても差し支えない。そうしたければ「オマージュ」でも「パロディー」でも「パスティーシュ」でも「コラージュ」でも「アダプテーション」でも何でも、文脈に応じて銘々が好きな言葉をあてがえばよい。
言葉は無から生じない 「文化」も源はラテン語
「そんなことより早く映画の話をしろ」と思われるかもしれないが、ピンときていない読者のために言語表現を例にとって補足しておく。言語それ自体は我々に先立って存在する。言葉は我々が発明したものではなく、我々は他者の言葉を模倣することによってしか、自らを表現できない。たとえば「文化」という言葉がある。我々がごく日常的に用いる言葉であり、特に難しい語彙(ごい)ではない。しかし、無から突然生じたわけでもない。
日本語の「文化」は英語cultureの訳語として幕末から用いられ始め、明治時代に定着を見た。西洋から流入してきた概念に数々の卓抜な訳語を与えた哲学者の西周(にし・あまね)は、早くから今日とほぼ同じ意味で「文化」を使用している(「概念」や「哲学」もまた西が考案した訳語である)。「文化」という語自体の典拠は中国に求められるが(注2)、英語のcultureにしても、「耕作する」という意味のラテン語の動詞colereやその名詞形culturaに由来すると考えられている(注3)。「文化」のような一般的な語彙でさえ、我々は複数の文化(言語)からの盗用を試みており、そうして成立した語を自分の文章のなかで盗用し続けているのである。(注4)
「いやいや、そうした伝播(でんぱ)の仕方はむしろ言語の本性であって、一般に〝盗用〟とは言わないだろう」と思われるかもしれない。「そんなものまで盗用扱いし始めたらすべてがそうなってしまうじゃないか」と。だから「およそ盗用/流用/奪用/引用でない表現など存在しない」と言ったのである。その意味で、人類の文化史は盗用の歴史である。もちろん、これは言葉の定義の問題であって、じっさいにどう呼ぶかはことの本質ではない(注5)。盗用にも程度の差があることは自明だが、ここではその差を意図的に捨象している。私の想定している定義に同意できなくとも、そのような営みが広く存在していることを思い出してもらえればまずは十分である。
〝盗用〟からは逃れられない
よもや誤解の余地などあるはずもなかろうが、私は盗用が悪いことであるとは言っていないし、もちろん考えてもいない(良かれあしかれ盗用からは逃れられないのだから引き受けるしかない)。著作権法のような何らかの外的基準に照らして「良い盗用」と「悪い盗用」を想定することは一応可能だが、しかし、法はすべてを解決してくれるわけではない。「法に反した良い盗作」や「反していないが悪い盗作」を考えることもできる。
法的な問題はなくとも、倫理的な問題が指摘される事例など枚挙にいとまがない。多くの場合は両方の観点が混じり合って収拾がつかなくなっている。いずれにせよ、白か黒かの二分法で決められるようなものではなく、広大なグレーゾーンを挟んでさまざまな「盗用」がグラデーション様に分布している。言葉の意味には厚みがあるので、法が想定している盗用や引用と、日常語彙としてのそれとのあいだには乖離(かいり)があるし(注6)、個々人の感覚の差も大きい(注7)。現実に盗作騒ぎが持ち上がった場合には、その性質(法的な問題なのか倫理的な問題なのか)や程度(アイデアが共通しているのか、具体的な表現が酷似しているのか)、あるいは分野ごとの慣習などを勘案して総合的に考えなければならない(「総合」も西による訳語)(注8)。
鑑賞の質高め、鑑賞眼も鍛える効用
映画においても事態は同様である。あらゆる映画は一本の作品として独立しているように見えつつ、同時にほかのさまざまな作品とのあいだにつながりを持っている(間テクスト性)。「踊る大捜査線」シリーズの最新のスピンオフ映画たる「室井慎次 敗れざる者/生き続ける者」(本広克行監督、2024年)2部作もまた、先行作品に多くを負っている。先の定義に照らせば「盗用」の実践例ということになろうが、もちろん、法的な意味で作品を断罪する意図はみじんもなく、また倫理的な観点から批判しようという気もさらさらない。
むしろ、わかりやすい「盗用」は観客にとってはありがたいものであるとさえ言える。ある映画を起点にして、そこから関連する別の映画へと鑑賞を進めていくことは、映画をよくばりに味わう極意である。先行する作品から何をどのように取り入れたのか、その試みは成功しているのか等を考えながら見ることで、おのずと映画鑑賞の質が高まり、楽しさの幅が広がるのみならず、鑑賞眼も鍛えられるからである。
「七人の侍」想起させるタカと杏の出会い
たとえば、「踊る」シリーズはたびたび黒澤明を参照してきた。「室井慎次 敗れざる者」にも黒澤映画を連想させるような具体的な場面がある。室井(柳葉敏郎)が里子として養育している高校生のタカ(斎藤潤)は、山の中に人影を見つけ、あとを追う。捕まえてみると、果たしてそれは自分と同年代の女の子だった【図1】。その後のシーンで、女の子の正体は日向真奈美(小泉今日子)の娘・日向杏(福本莉子)であることが判明する。

【図1】タカはそれまで逃げる人物の後ろ姿しか目にしておらず、捕まえた際に顔を見て初めて女の子であることに気づいた。
このシーンについて、ライムスターの宇多丸は「要するに『七人の侍』で勝四郎が志乃と出会う場面の、オマージュがやりたかっただけです。後ろの方でね、またぞろ黒澤明全集かなにかが並んでいて」と指摘している(注9)【図2】。じっさい、劇中には「全集 黒澤明」が映り込む場面がある【図3】(注10)。映画の公式パンフレットもこの全集に言及しており「『踊る』第1作で『天国と地獄』の話をした青島の影響で室井が黒澤映画にハマったという裏設定」があることを明かしている。製作者が「踊る」シリーズと黒澤映画とのつながりを積極的に認めている証左である。

【図2】「七人の侍」より。勝四郎(木村功)は森のなかで遭遇した志乃(津島恵子)を男だと思って追いかけるが(年ごろの娘が侍たちから狙われることを恐れて、父親[藤原釜足]が志乃の髪を切って男装させていたからである)、組み伏せたところで女であることに気づいて跳びのく。

【図3】室井が寝起きしている仏間の机上には「全集 黒澤明」が並んでいる。その隣には後藤新平の評伝が置かれているのが見える。飼い犬(秋田犬)のシンペイの名前の由来だろう。
「室井慎次」文机の上にある「全集 黒澤明」と「踊る大捜査線」のルーツ
病に侵された主人公と「生きる」
「室井慎次 生き続ける者」では、胸に強い痛みを感じた室井が医者を受診し、狭心症の疑いを指摘される。それが死に至る病であるかどうかは必ずしも明らかにはされないが、もし室井が自分に先がないことを悟っていたのだとすれば、「生きる」(黒澤明監督、1952年)の主人公(志村喬)の姿に重なるし、最後に室井が打って出た無意味かつ無謀としか言いようのない行動にも一応の説明はつく。重篤な病に侵された主人公が生き方を迫られるという設定は劇場版第3作「踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!」(本広克行監督、2010年)でも採用されており、シリーズを通した自己引用と見ることもできる。その場合、勘違いで済ますことのできた劇場版の青島と最新作の室井の対比が際立つことになる。
「室井慎次」が参照しているのは、もちろん黒澤映画だけではない。たとえば監督の本広克行は、参考にした映画として「グラン・トリノ」(クリント・イーストウッド監督、08年)と「ラスト・バレット」(フレデリック・プティジャン監督、19年)のタイトルを挙げている。作品のルックを象徴する室井の家は、「ラスト・バレット」でジャン・レノが暮らしている山小屋をイメージして制作部に探してもらったのだという(注11)。いずれの家も池のほとりにひっそりとたたずんでおり、また雪景色のイメージと遭難しかねないような周囲の地形も共通している【図4、5】。「正体不明の若い女性が突然やってくる」という設定にも連続性を見いだすことができる。

【図4】室井の家を正面から捉えた画像。桟橋に立っているのは日向杏。奥のバルコニーには秋田犬のシンペイの姿が見える。

【図5】「ラスト・バレット」より。画像では雪と氷に閉ざされているが、山小屋から延びる桟橋の先には池が広がっている(ジャン・レノが魚を釣るシーンがある)。
「グラン・トリノ」の換骨奪胎
本広はまた「ガレージは、クリント・イーストウッド監督・主演の映画『グラン・トリノ』(2008)みたいに、道具がピシッとそろってる、男の子の大好きなヤツをやらせてもらいました」と述べている(注12)。だが、私見では「室井慎次」2部作が「グラン・トリノ」から借り受けているのは単にガレージのイメージだけにとどまらない。これは脚本家の君塚良一の手腕によるものだろうが、本作は「グラン・トリノ」を換骨奪胎したものと言ってもいいくらいである。作品の根幹をなすテーマや登場人物の造形から、鍵となるいくつかの設定に至るまで、「グラン・トリノ」は重要な参照源となっている。
そのゆえんを詳しく紹介するための紙幅はもはや残されていないが、「室井慎次」に満足した人にも、あるいは不満を覚えた人にも、次に見るべき映画としてぜひとも「グラン・トリノ」をおすすめしたい。「グラン・トリノ」は、真に賢い犬がどういうものかを教えてくれる映画である。
注1 ロラン・バルト「作者の死」、『物語の構造分析』花輪光訳、みすず書房、1979年、80ページ。
注2 「文選」には「観乎天文以察時変、観乎人文以化成天下(天文を観て以て時変を察し、人文を観て以て天下を化成す)」の一節がある。そもそも漢字は中国から輸入したものであり、そこからかな(ひらがな・カタカナ)を派生させて今日のような日本語の体系を作り上げた点にも思いをはせておくべきかもしれない。
注3 「文化」という語をめぐる一連の説明は、小松寿雄・鈴木英夫編「新明解語源辞典」(三省堂、2011年)と廣松渉ほか編「岩波 哲学・思想事典」(岩波書店、1998年)の記述に依拠したものである。
注4 これに限らず、和漢の典籍から流用しているケースは非常に多い。「昭和・平成・令和」といった我々にとってなじみの深い「元号」もそうである(「文化」も江戸時代に元号として採用されている)。あるいは、私は愛知県にある時習館高校出身だが、校名の「時習」は「論語」の一節「学びて時に之を習う、亦説(よろこ)ばしからずや」に由来する。吉田藩の藩校の名称をそのまま引き継いだものである。同名の藩校は全国にいくつか存在しており、熊本藩にもかつて時習館が存在した。現在、熊本大学の隣には濟々黌(せいせいこう)という高校があるが、こちらは「詩経」の「濟濟たる多士、文王以て寧んず」に由来する。出典を同じくする四字熟語に「多士済済」がある。
注5 「批評家たるもの言葉の意味には厳密でなければならない」という規範が存在するとして、そこで言われているのは「誤解の余地なく言葉の意味を一意に定めて用いること」ではない。むしろそれとは逆に「言葉の意味に幅があること」を引き受け「意味の幅を不当に縮減しないこと」が求められる場合もある。
注6 おそらく哲学や現代思想の難しさの一因でもある。哲学者はしばしば日常的な語彙を抽象度の高い術語に転用し、独自の意味を与える。その用語を別の哲学者が引き継ぐ際には、さらに意味がずらされていく。その意味の揺らぎに付き合い、のみならず簒奪(さんだつ)のすきをうかがうこと。それが人文学における記号操作の基本であり、習得には多年を要する。
注7 先ごろ「渋谷ハロウィンは文化かどうか」をめぐってSNS上で展開された論争は典型的な例である。人によって「文化」の意味が異なるのだから、「文化かどうか」を議論しても落としどころなど見つかるはずもない(ちなみに私は「渋谷ハロウィン」は立派な文化だと思っている)。むしろ批評的には、その意味の乖離(かいり)がなぜ生じているのか(ある種の人々は何をもって文化と見なす/見なさないのか、その歴史的経緯はどのようにたどれるか)について考えをめぐらせた方がはるかに生産的だろう。
注8 具体的な事例については栗原裕一郎「〈盗作〉の文学史 市場・メディア・著作権」(新曜社、2008年)などを参照されたい。
注9 【後編】宇多丸「室井慎次 敗れざる者」を語る!【映画評書き起こし 2024年10月31日放送】、https://www.tbsradio.jp/articles/89509/
注10 「全集 黒澤明」(岩波書店)は6巻+最終巻の合計7巻からなるが、この場面には6巻までしか映っていない。ここに存在しない最終巻には黒澤の晩年の作品「夢」(1990年)、「八月の狂詩曲」(91年)、「まあだだよ」(93年)の3作のシナリオが収録されている。黒澤の遺作となった「まあだだよ」の終盤には、喜寿を迎えた内田百閒(松村達雄)がケーキを運んできた子どもたちに「生き方の指針」を語るシーンがあり、里子たちの将来を見据えていた室井の姿と重ならなくもない。つまり、7巻のうちの1巻分をあえて写さないことで、むしろ注目を集め、深読みを誘うように促しているのではないか。一方で、6巻まで(87〜88年)と最終巻(2002年)のあいだには刊行時期の隔たりがあり、単に小道具として用意したのが6巻までのセットだった可能性もある。
注11 「「踊る大捜査線」本広克行、再始動は一度断った 『室井慎次』監督を引き受けた理由」(取材・文:早川あゆみ)、「シネマトゥデイ」、最終閲覧日2024年11月22日、https://www.cinematoday.jp/news/N0145571。
注12 同前。
図版クレジット
【図1】「”踊るプロジェクト”映画最新作『室井慎次』 <スーパーティザー映像5>」東宝MOVIEチャンネル(YouTube)、最終閲覧日2024年11月22日、https://youtu.be/OvtddZgefS0?si=EqQOUYmOdLbGtGEG
【図2】「七人の侍」黒澤明監督、1954年(DVD、東宝、2015年)
【図3】「”踊るプロジェクト”映画最新作『室井慎次』 <スーパーティザー映像5>」東宝MOVIEチャンネル(YouTube)、最終閲覧日2024年11月22日、https://youtu.be/OvtddZgefS0?si=EqQOUYmOdLbGtGEG
【図4】「”踊るプロジェクト”映画最新作『室井慎次』 <スーパーティザー映像5>」東宝MOVIEチャンネル(YouTube)、最終閲覧日2024年11月22日、https://youtu.be/OvtddZgefS0?si=EqQOUYmOdLbGtGEG
【図5】「ラスト・バレット」フレデリック・プティジャン監督、2019年(DVD、TCエンタテインメント、2020年)