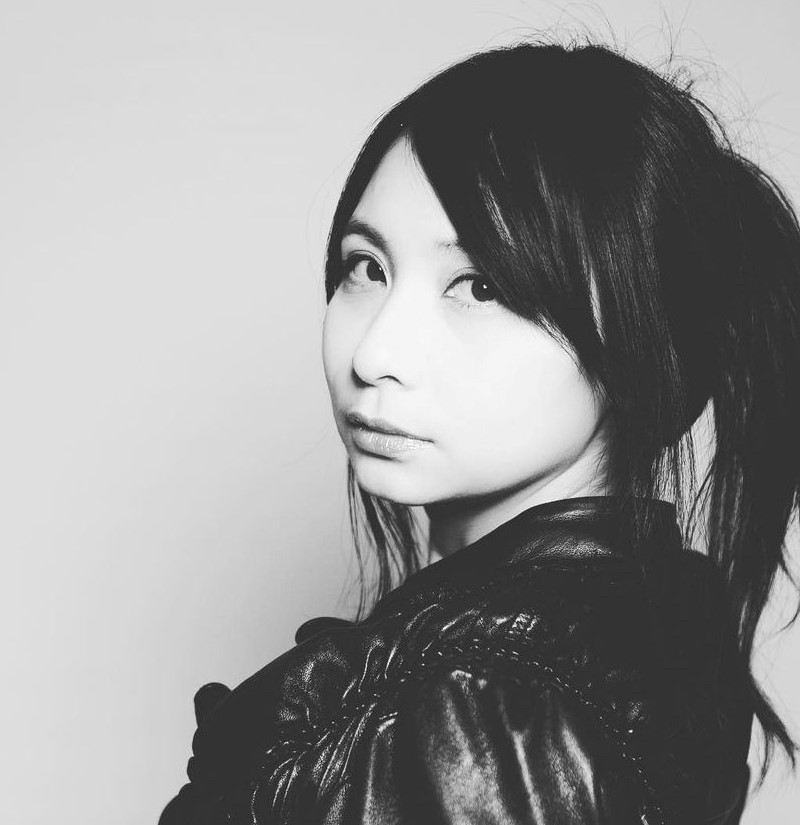公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。
「ディア・ファミリー」を語る東宝プロデューサー、岸田一晃 撮影:下元優子
2024.6.14
「ゴジラ-1.0」プロデューサーが奇跡の実話「ディア・ファミリー」を手がけるまで
「作らねばならない」映画だった
映画「ディア・ファミリー」(毎日新聞社など製作委員会)は、難病で亡くなった娘の父親が開発した医療機器「IABPバルーンカテーテル」が多くの命を救っているという実話の映画化だ。悲しみはあっても家族愛と希望を実感できる物語として製作された。企画、開発から深くかかわったのは、米アカデミー賞視覚効果賞を受賞した「ゴジラ-1.0」も製作した東宝のプロデューサー、岸田一晃。良質のエンタメを提供する作品作りに加え、本作で岸田を大きく揺さぶり、突き動かしたのは何だったのか。
心を動かした佳美さんの言葉と父親の挑戦
2018年ごろ、テレビ番組で人工心臓を作ろうとした父親の筒井宣政さん、余命10年と告げられ亡くなった次女の佳美さんのことを知った。「すごい話」と思い、翌日には映画化の企画書を上司に提出した。同日、同じ番組を見て別のプロデューサーも提出。2人はニュースやネット情報の収集から始めた。約1カ月後、WOWOWから同様の企画が東宝に持ち込まれ、一緒に企画開発することになる。WOWOWは原作者となる清武英利さんと別作品のドラマ化で接点があり、清武氏は筒井家の家族と20年来の仲だったと知る。「ご家族の取材をお願いしたい」と製作が具体的に始まった。
岸田をひきつけたのは「私の命は大丈夫だから」という佳美さんの言葉。もう一つは、医学の知識が全くない父親が人工心臓の開発に挑んだことだった。「なぜ、そんなことが言えたのか。挑戦しようと思ったのか」。心を奪われ、まさに映画化の起点になった。プロデューサーとして「いつか実話を映画にしたい」とも思っていた。
「(ドラマを)創作していくとキャラクターを動かし、ご都合主義になってしまいがち。実話ならば人間は想像もつかないことを言い、動く。実話にはリアリティーが詰まっている」。さらに続ける。「この実話は今もなお続いているのが魅力だ。今の人の生活に直結している」。
岸田はこれまでになかった感覚を覚えていた。この映画を「作らねば」と初めて思った。「映画を通じて多くの人にこの話を伝えなくてはならない。作りたい映画ではなく、作らなければいけない映画だった」。モチベーションの高さは、その後多くの障壁に見舞われても崩れることはなかった。
コロナ禍、実話、医学的監修の壁
コロナ禍が作品の企画、開発をも襲った。20年4月、緊急事態宣言が発令される。映画界もその波にのまれて展望が閉ざされ、宣言は幾度となく繰り返され多くの作品が消えた。東宝は「ディア・ファミリー」を残し続けた。医療従事者やエッセンシャルワーカーへの感謝を改めて痛感した時だった。「筒井さんの物語は(私たちに)必要な物語。その意義はとてつもなく大きい」と岸田は感じていた。一見暗く地味な内容に見えるが「ストーリー性が強く、娘のために懸命になる父親や家族の実話にみなぎる力があった」と感じていた。
一方で、実話であるからこその課題もあった。「佳美さんはなぜ、大丈夫と言えたのか」。当初、佳美さんにリアリティーを与えることは難しかったが「清武さんが綿密な取材で聞いてくれたこと、20年来のつきあいによって導き出したことで、キャラクターをうそなく紡ぐことができた」と感謝の意を込めた。清武さんには脚本の確認もしてもらった。
コロナ禍ならではの問題も立ちふさがった。「医療界への取材がとにかくできなった」。筒井さんが住む名古屋に行くことも難しかった。「家族の物語としての幹は太くなったが、医学的な監修という幹を加えていくのに時間がかかった」。医療従事者に無理を言える状況ではなかった。「心は何度も折れかけたが、スタート時からの信念がそれを支えた」。コロナ禍の映画製作は日がたつにつれ周囲で始まっていたが、この企画はなかなか進められなかった。それでも「会社も周囲も理解してくれた」。
撮影はようやく、22年12月から翌23年2月初旬まで順調に行われた。
「広めたい」意義を感じる作品に出合った
映画製作を通じ何に血湧き肉躍ったか聞いてみた。「プロジェクトを立ち上げ、初めて作る意義のようなものを感じている。それは初めての経験だ。今までも伝えたいテーマとかはたくさんあって、エンタメとして作ってきた。ただ、これほどまでに広めたいと思った作品は初めて。僕たちは筒井さん一家の物語、人生をお借りして、それを届けようと考えて映画を作った。もし誰かに届いたのなら、その人も誰かに届けてほしい。人のつながりを信じたいと思える作品になった」。
肩ひじ張らない、けれども気持ちのこもった言葉が岸田の口を突いて出てくる。「シンプルなエンタメも素晴らしいが、今回は『ただ、面白い』で終わるものではない。人のつながりを信じることを実感したい」と言い切った。
プロデューサーになって8年。アシスタントプロデューサーを含めれば、11本の映画を製作してきた。「今まで映画を見て楽しんでもらえることだけを考えて作ってきたが、今回は少し違う。この作品に携わったことは僕にとって大切なことであり、視野も広げることができたと心から感謝している」
プロデューサー中毒とは!
プロデューサーの面白さとはいったい何だろうか。岸田は少し考えて、こう切り出した。「僕が一番好きなのは完成披露試写会。一般の人に初めて見てもらえる場だから」。舞台の袖から「観客の反応、笑ったり、泣いたり、怒ったりを見るのが楽しい」と話す。映画として、作品として完成したことはもちろんうれしいが「僕の〝 妄想 〟した映画を楽しんでいる人がいる。作ってよかったと感じる瞬間」と声を弾ませる。
初めてアシスタントプロデューサーとしてついた「君の膵臓をたべたい」(17年)の完成披露試写会でそう感じて「(この仕事)いいなあ」と実感した。「それからは麻薬みたいなものです」と柔らかい表情になり、「運がいいんです。先輩にも感謝しています」と話した。
「プロデューサーは(映画の)設計士、監督は棟梁(とうりょう)。どんな映画を作り、どんな話にするかなど最初に絵をかくのはプロデューサーの仕事」。現場は監督のもので、何かあればプロデューサーも出ていくという。「仕事は、8割は大変だが、2割は楽しい」とも語る。「嫌なことは日々あるが、技術が進んでも、相手はどこまでいっても人だと思っている。映画は作ることが目的ではなく、見てもらうことが目的。その先に観客がいる。人と営み、人から逃れることはできない」とにこやかに話した。