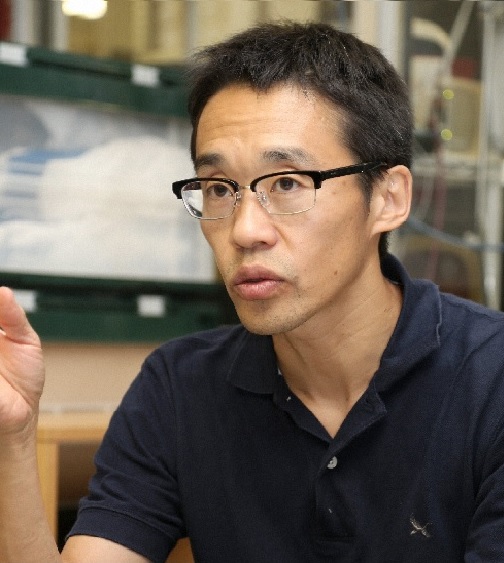公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。
「ディア・ファミリー」について語る月川翔監督=幾島健太郎撮影
2024.6.11
「お父さんならできると思っていた」月川翔監督も驚いた前向き一家 「ディア・ファミリー」
「ディア・ファミリー」は不治の病と闘う父娘の物語。泣ける場面がたくさんあっても、いわゆる難病ものと違い、見終わって悲壮感よりも大きな希望が残る。娘を救いたい一心で画期的な医療器具を開発した実話の映画化で、月川翔監督は「リアリティーを大切に、前向きな映画にしたかった」と語る。
娘を救いたい一心が、画期的医療機器を生んだ
1970年代末、町工場を経営する坪井宣政(大泉洋)の次女佳美は心臓の難病で、20歳まで生きられないと告げられた。しかし宣政は「絶対治す」と人工心臓の開発を決意する。大学研究室の協力を取り付け、私財を投じて研究に打ち込むものの、ある時「明日人工心臓ができても治癒不能」と宣告される。しかし佳美は「技術を苦しんでいる人のために役立てて」と宣政に託し、宣政は日本人の体質に合ったカテーテルの開発に没頭する。
物語はほぼ実際の出来事の通り。月川監督は映画化を打診され、あまりに劇的な内容に「本当か」と驚いたという。特に、娘を亡くした後も、苦しんでいる人を救おうと開発を続けたことに興味がわいた。「どんな心持ちだったのか。家族の話を聞いてみたい、映画にしたいと思った」。この家族を20年にわたって取材し、ノンフィクションとして出版した清武英利の取材ノートを借り、家族を何度も訪ね、話を聞いた。
「一番心が躍ったのは、佳美を助けられないと分かった後で、医療機器の開発が家族みんなの目標になっていくところ。命が尽きて悲しい物語ではなく、家族が目標を達成して、今も救われる人がいることに感動させる映画にしたかった」

「ディア・ファミリー」©2024「ディア・ファミリー」製作委員会
作り物と思われたら観客の気持ちが離れてしまう
「こだわったのはリアリティー」と月川監督。凡百の映画よりも映画的な展開だけに「作り物と思われたら観客の気持ちが離れてしまう」と覚悟した。父親には何度も質問をぶつけた。「人工心臓の大きさや色など、気になったことを一つずつ。医学的、工学的な面もないがしろにしたくなかったので、別の技術者にも確かめたりもしました」。あきれられるほど根掘り葉掘り聞いたのは、「『携わった人がウソとは言えない』というラインを指針にした」からだ。映画に登場する実験装置もできるだけ実物に近づけ、人工心臓の試作品は本物を借りた。40年以上前の町並みや風俗も、忠実に再現。家族のエピソードや会話も、証言に基づいたという。
宣政は医療の知識は皆無でも、娘を救いたい一心で猪突(ちょとつ)猛進。遅々として進まない開発にいら立ち、借金を背負い、大学の理不尽な慣行にも悩まされながら、妻や子どもたちに励まされて苦難を乗り越える。実際の父親を、月川監督は「タフな人だと思います。『なんでうまくいかないんだ』という怒りをエネルギーに変える人だと思う」。大泉が演じた宣政は、少しマイルドにしたそうだ。そして家族。一家の長女に「本当はお父さんをムチャだと思ってたわけですよね」と聞いたら「いや、できると思ってたんですよ」と即答だったとか。「何とかなると思っていたようです。それがすごい。きっと、そういう人たちじゃなかったらできなかった」
一方で、あえて〝泣かせどころ〟を抑えた部分もあった。「家族が話す度に涙ぐむエピソードがあるんですが、あえて映画には盛り込まなかった」。というのも「佳美が、他の人の命が救われて喜ばしく受け止める、前向きな映画にしたかったから」。

濱口竜介監督と同門 「PASSION」見て「やめようか……」
月川監督は「君の膵臓をたべたい」(2017年)、「君は月夜に光り輝く」(19年)など、泣かせる恋愛ものをヒットさせてきた。濱口竜介監督をはじめ、鶴岡慧子、真利子哲也といった監督を輩出する東京芸大大学院の出身。作家性の強い作品を撮る卒業生が多い中で、娯楽映画の本流を行く。自身を「エンターテイメントの職人」と言う。「大学時代には娯楽映画が好きだったんですが、芸大院では作家性とか、映画祭で評価されたいとかヨコシマな気持ちが入ってきて。でも濱口監督の『PASSION』を見たら、同じカリキュラムでこんなものを作る人がいるんだ、もう自分は作る必要がないと、やめようかと思ったんです」
思い直したのは恩師からの「君には娯楽作という土俵がある」という一言だった。「ギリギリ自分が続けられるやり方を見つけたかもしれないと。それからは、自分が打席に立つ番が来たら……というつもりで、シミュレーションをしたり、少女漫画を読んで自分だったらこうするみたいなリストとかを作ったりして、チャンスを逃さない準備をしていました」。同じ事務所の三木孝浩監督に教えを請い、芸大院時代に師事した黒沢清監督とも交流を続け「監督のすべき仕事は何か」を学び取った。
「とにかくお客さんを楽しませたい。初めて自主映画を作った時から、どうやって喜んでもらうかを考えていた。自分が血湧き肉躍る瞬間を分析して、作品に入れ込んでいく。その繰り返しで今に至っています」。「ディア・ファミリー」は「いつかやってみたかった」という実話の映画化。「ストーリーの都合で人が動くのではなく、実際に起きた出来事の中の人たちの視点で、物語を掘り下げられた」。新たな経験も糧に「いずれは世界に」と目を向ける。「外国映画のまねじゃなく、日本の良いものを追求した結果、世界に届けばいいと思う」