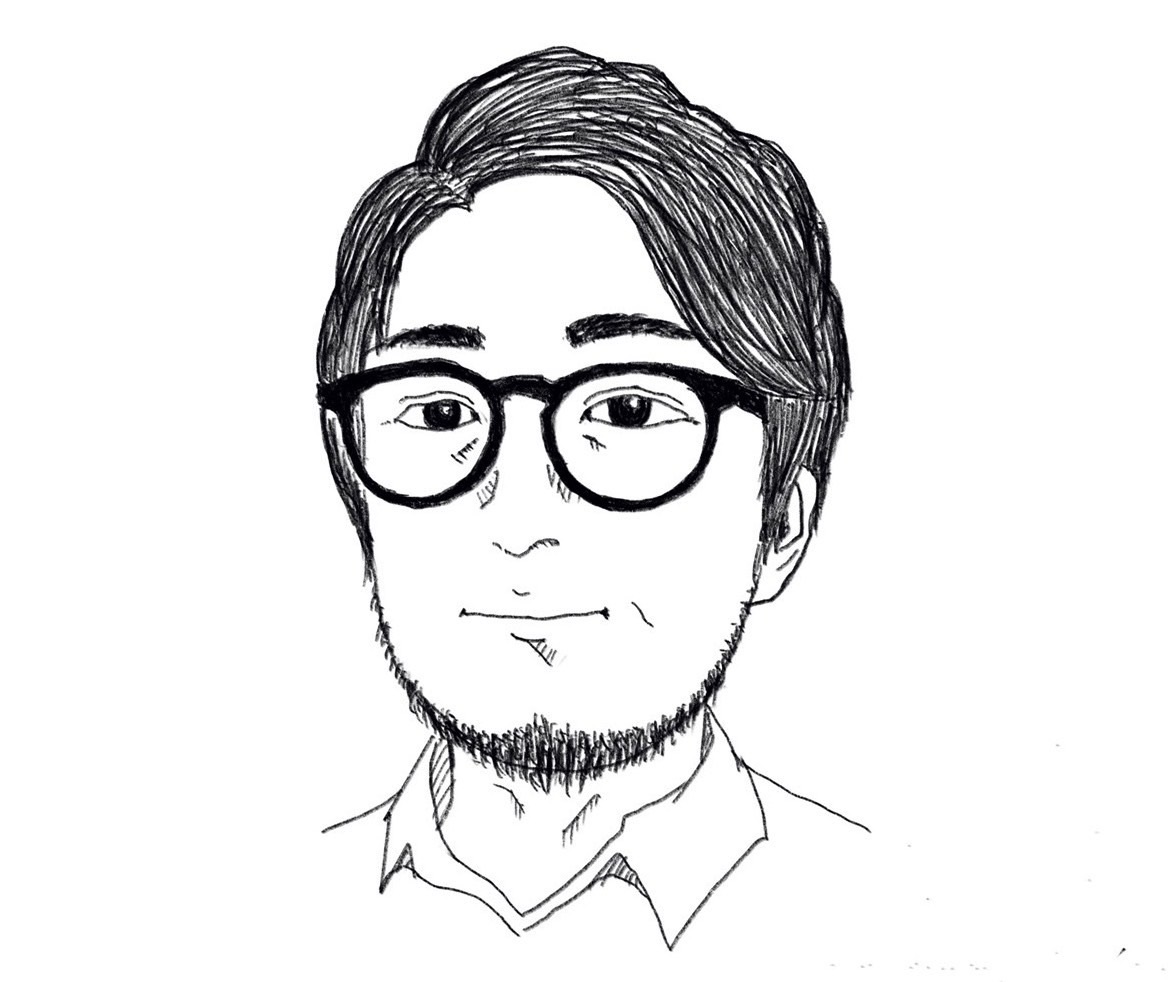〝原爆の父〟と称される天才物理学者の半生を描いた「オッペンハイマー」。第二次世界大戦末期、広島、長崎に投下された原爆開発の舞台裏と天才科学者の葛藤を、壮大なスケールで映像化。日本公開までに曲折を経た一方、アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演男優賞など7部門を制覇。賛否渦巻く問題作を、ひとシネマが独自の視点で徹底解剖します。
「オッペンハイマー」© Universal Pictures. All Rights Reserved.
2024.4.18
科学記者が見た「オッペンハイマー」 現代日本に問う科学と政治 「適性評価制度創設」と「軍事研究」誘導の危うさ
20世紀は「物理学の世紀」だった。特に前半、相対論と量子力学という二つの革命が、時間と空間の概念を一変させ、微小世界での物質やエネルギーの理解に新たな地平を開いた。それは文明を飛躍的に発展させた一方、人類を滅亡させうる悪魔の力をもたらした。
映画「オッペンハイマー」には、この革命期のスター物理学者が続々と登場する。ノーベル賞の栄誉に輝いたニールス・ボーア、アーネスト・ローレンス、エンリコ・フェルミ、ハンス・ベーテ。後に「水爆の父」と呼ばれるエドワード・テラー。そして、大統領宛ての手紙で原爆開発の端緒を作りながら、反核運動に転じたアルベルト・アインシュタイン……。
いずれも科学史に残る傑物たち。だが、映画館で個々の業績が思い浮かぶ観衆は少ないだろう。一見しただけでは顔と名前すら一致しないかもしれない。それでも、恐らくあえて次々に現れる科学者の姿。「全米の産業力と科学イノベーションをここに集めた」という劇中のセリフと相まって、原爆開発の極秘プロジェクト「マンハッタン計画」の異質さを印象づける。
世紀のスター科学者の栄光と失墜
この計画を率いたロバート・オッペンハイマーも、世紀を彩るスターの一人だった。青年時代は内省的で、共産主義に傾倒。研究面では若くして頭角を現し、20代で名門のUCバークリー(カリフォルニア大学バークリー校)とカルテック(カリフォルニア工科大学)の教職に就いた。ユダヤ系移民の子であり、ナチスの脅威から早急な原爆開発の必要性を痛感。2人の女性と関係を続けながら、気難しい天才たちを卓越した指導力でまとめ上げ、目標達成に導いた。ところが、戦後は「原爆の父」とたたえられるも、大量虐殺の罪悪感にさいなまれる。東西冷戦下の「赤狩り」(反共産主義運動)の被害者となって、名声は失墜させられた。
その栄光と没落の生涯はドラマチックである。ピュリツァー賞に輝いた原作の評伝は時代を追って描いていたが、クリストファー・ノーラン監督はカラーとモノクロの映像を織り交ぜ、時代を行き来しながら巧みに見せていく。
すでに批判があるように、広島・長崎の被爆の実相や、米南部の核実験場を巡る先住民の追放と健康被害が十分描かれていない点は、やはり物足りなさが否めない。ただ、日本の核開発史や軍事と科学の関係を取材してきた私は、より議論が必要な、現代日本にとって別の重大な示唆が二つあると感じた。

権力者の意向と社会の空気が人生を左右する
一つ目は、今まさに法案が国会審議されている「セキュリティークリアランス(適性評価)制度」創設の問題だ。赤狩りに遭い、ソ連への内通が疑われたオッペンハイマーは、密室の聴聞会でさまざまな難癖をつけられた末、機密情報へのアクセス権を奪われて公職追放される。当時の有力政治家ルイス・ストローズの私恨によって陥れられるシーンは、実にスリリングで本作品のヤマ場だが、実際には手に汗握るだけでは済まされない。
オッペンハイマーは聴聞会で人間関係や米政府の水爆開発への反対姿勢を詰問される。しかし、共産党員らとの親交は戦時中から当局は把握済み。水爆開発に異を唱えても追放されなかった科学者は少なくない。彼は死後55年を経た2022年になって公職追放が取り消され、名誉回復が果たされた。それは、処分が恣意(しい)的だった証左でもある。権力者の意向や社会の空気感で、人の一生が左右される。そんな時代の不条理と恐ろしさも、本作品は描いている。

特定秘密保護法の延長にある「重要経済安保情報」
他方、審議中の法案は、外部に漏えいすると日本の安全保障に支障を来す恐れがある経済関連の情報を、国が「重要経済安保情報」に指定。この情報を扱う人を身辺調査する制度の導入が柱だ。もちろん、漏えいには5年以下の拘禁刑をはじめとする罰則がある。同様の制度が、かつて大きな導入反対運動があった特定秘密保護法だ。日本弁護士連合会などは「秘密保護法制の拡大版だ」として、導入反対を訴えている。
問題は、重要経済安保情報の主な対象が先端技術に関わる点だ。つまり、研究機関や企業の科学者・技術者が適性評価の対象になる。だが、人工知能(AI)、量子技術、バイオ、半導体などのデュアルユース技術は軍民の線引きが明確でない。なのに、機密指定の基準は不明確。身辺調査は本人の病歴や経済状況、家族や同居人の国籍まで調べられる。
経済安保と言えば、軍事転用可能な機械を中国へと輸出したと決めつけられた大川原化工機を巡る冤罪(えんざい)事件が起きたばかり。国賠訴訟などで明らかになった捜査の実態は、あまりに恣意的で社会を驚かせた。だが、冤罪を作り出した警察と検察は謝罪すらしていない。そこにこんな制度を導入したら、どうなるか。聴聞会で難癖に苦しんだオッペンハイマーの顔が浮かんでこないだろうか。

マンハッタン計画を成功に導いた巨額予算
二つ目の示唆は、より大きな科学と政治の関係である。マンハッタン計画は「全米の産業力と科学イノベーションを集めた」ことで達成できた。より具体的には、巨額の予算が付き、科学者の動員に成功した点が鍵だった。
世紀の天才科学者たちは、なぜ続々と計画に加わったのか。愛国心や名誉欲はもちろんあるが、それだけが理由ではない。戦時中の緊縮財政下でも、この計画だけは特別で自らの研究が実現できる環境があったことが大きい。劇中で周囲の忠告を無視し、水爆研究にこだわったテラーの振る舞いが象徴的だろう。
科学者にとって、研究は自らの存在意義に関わる。その継続には何より研究費が必要だ。米国は科学技術予算の半分近くが国防用で、先端技術は主に国防総省の国防高等研究計画局(DARPA)が巨額予算を差配する。暗号などに幅広く使える量子技術のように、重要テーマは今でも国を挙げた大型プロジェクトを動かしている。

科学者を軍事に誘い込む公募研究費制度
日本も近年、DARPAを模倣した競争的資金が増えてきた。第2次安倍晋三政権では装備品開発を目的とした防衛装備庁の公募研究費制度も始まり、「軍事研究への誘導」だと波紋を広げた。科学技術予算が先細る中で、この研究費を得た国立大学の研究者は「この制度でなくても研究ができるなら応募はしなかった」と苦しい胸の内を私に語った。
あまり注目されていないが、経済安全保障の枠組みで、軍民両用の研究開発予算は一層拡大している。日本の学術界は軍事研究に距離を取っているが、「背に腹は代えられない」となびく研究者も増えていくだろう。
資源の乏しい私たちの国の国是は「科学技術創造立国」とされている。問われているのは、平和国家の前提を無視した軍事大国の二番煎じの先に、日本が目指すべき国家の姿があるのか、ということだ。映画「オッペンハイマー」は科学者の倫理とともに、科学と政治のありようも問いかけている。あの時代の米国の話ではなく、現代を生きる私たちの問題として受け止めたい。
【関連記事】
〝原爆の父〟半生描く圧巻の映像叙事詩 「オッペンハイマー」が映さなかったもの
「シネマの週末」 天才の苦悩、映像に迫力
元広島市長「原爆の恐ろしさ不十分」 アーサー・ビナード「観客が立場に同化」 「オッペンハイマー」広島試写会
「オッペンハイマー」祖母、父が被爆した記者の涙 描かれなかった〝その後〟に思いはせ
「恐怖の時代の始まり」だけでいいのか 死者と残された人への視点がない 「オッペンハイマー」:藤原帰一のいつでもシネマ
クリストファー・ノーランは何者か 「技術がもたらす虚無」時間軸を操り問うもの
「オペンハイマー」映画のスペクタクル 濃密な歴史描写の原作全3巻 違いを読み解いた