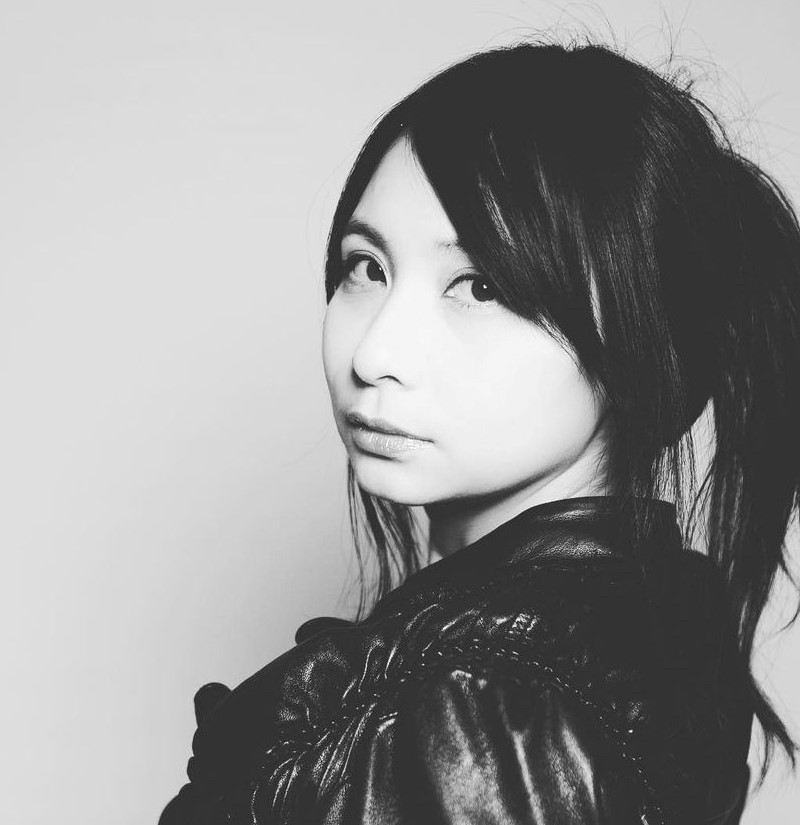実際にあった障害者殺傷事件に着想を得た辺見庸の同名小説の映画化。重度障害者施設で働く作家とその夫、同僚の職員と暴力や虐待、隠ぺいが横行する施設の実態を描き命の尊厳と社会の欺まんを描いた問題作だ。施設の職員で理不尽な現実に憤り、一線を越えてしまう青年さとくんを演じた注目の若手俳優、磯村勇斗さんに常軌を逸した行動に出るさとくんの繊細な役作りや本作品への確かな思いなどを語ってもらった。
洋子はデビュー作は評価されたが、新作を書けない元有名作家。幼くして亡くなった子供への悲しみから夫と不安定な日々を送っている。彼女は重度障害者施設で働き始め、同僚の作家を目指す陽子や心優しいさとくんと親しくなるが、施設内の虐待や隠ぺいに疑問を感じる。さらに、洋子は妊娠が判明しひとり不安を抱える。一方、施設でのいじめや暴力、社会の理不尽に怒りを募らせたさとくんは、ある行動へと突き動かされていく。

責任感を背負い、役と向き合う
小説の元になった事件が社会に与えた衝撃が大きく、演じる俳優にとっても〝 覚悟〟が必要な本作。「お話をいただいた時から直感的に参加したいと思った。表の面だけを描くのではなく、裏に眠っているものは何かという部分が鋭く、自分も参加しないとだめじゃないかと。(さとくんの)役に挑戦したい気持ちが湧きメッセージを届けたいと考えた」。ハードな役だけに抵抗感はなかったのか。「実際の事件とは描き方が違うが、大きな責任感を背負うと思った。公開後に何かあるかもしれないという恐怖も持ちながら覚悟を持って演じないといけない役と感じた」
演じてみてどう感じたのだろうか。「事件は衝撃的だったし、怖いというのが最初の印象だった。ただ、当時は正直どこか人ごとのようにも感じていたが、映画に携わって人ごとではないと実感した。社会全体の問題だと認識し、施設の闇、社会のしわ寄せが彼を生んでしまったという考えもあり、本人を責める瞬間もあった。映画でさとくんと向き合いいろいろ考えた」

細かな感情の起伏に苦心
磯村さんはさとくんの変化をどう考え表現しようとしたのか。磯村さんの分析の一端はこうだ。最初はピュアでやさしい好青年、中盤では少し変化が訪れて自分や世の中にストレスや生きづらさを感じている。終盤は自分の意志が固まり(自分の中での)正義感に満ちて思いを実行するさとくん、とおおむね3段階に分けて演じていった。
現場では「とても細かな感情の起伏を意識」したという。「最初は少し不気味というか変かなというところを作って。最も大事だったのは中盤の変化していく過程で、上司(先輩)からのいじめや日々感じる言葉、障害者と接する中でのフラストレーションやその蓄積を印象づけるように目線や表情のちょっとした動きをやりすぎないように演じた。サイコパスのような猟奇性を見せないようにもした。例えば、さとくんが描いた絵を捨てられた後、外と施設のはざまに立っている姿を見せるなど、ニュアンスをちょっと乗せたくらいの表現でおさめた」
石井裕也監督とはさとくんをどう作っていくかなど、撮影中も何度も話をした。石井監督は「事件の被告をリアルに表現しなくていい」とも言ってくれた。「石井監督も自分も一番恐れていたのは、第二のさとくんを生んでしまうことへの危惧」だったという。さとくんを演じ表現する立場としては石井監督も含め極めて重要なことであり、そのさじ加減は大変だったことは容易に想像がつく。

さとくんの正義感
「この映画で、さとくんにどこか共鳴してしまう瞬間があると思うし、それはそれでいいと思うが、彼は人をあやめてしまった殺人犯。気持ちの部分を分かるのはいいが、それを行動に、そして犯罪に結び付けるのは良くない。そうならないために、どこに杭(くい)を打って止めていくか、石井監督と話し合いながら演じた」
実際、終盤のさとくんは髪を金髪にして、自らの正義感で行動するから「前を向いていて姿勢もよく生き生きしているように見せたい」と考えたという。「彼にとってはいいことをするわけで、悪いこととは思っていない。これで日本が変わると考えて計画を実行する。世間的にどうかは置いておいて、さとくんは自分の中の正義として答えがすっきり出た後だから心情は明るい」。ここでも「柔らかくそのニュアンスを出すようにした」と話す。
後半、施設で同僚の洋子と対峙(たいじ)する時は、自分の正義を明確に話す。ただ、セリフは棒読みに近い。「とにかく、淡々と色を付けないで進めていくスタイルを徹底した。あの場面で音色を変えたり、リズムを付けると共鳴してしまうシーンにもなるし、演説者みたいになってしまう。賛同する人を生む怖さもあって微妙な言い回しだ。日々考えていることを口からぼろぼろ出しつつも洋子に向かっていくシーンにするためにフラットを心掛けた」

普通が一番難しかった
さとくんを演じながらも、その考え方から微妙な表現方法が連続する難役。磯村さんが何度も口にしたのは「いかにフラット、普通をつくっていくか」という言葉。「改めて、普通って一番難しかった」と振り返った。「役者はどうしても脚本を読んで、原作を読むと色を付けたがる。演じてて気持ちがいいから。でも、役者が気持ちいいって時は、芝居はたいていダメ。石井監督も普通が最も難しいって話していて、そういう芝居をどうやって作っていくか話し合った」
撮影現場には実際の障害者の方もいれば、障害者役の役者もいた。撮影前には和歌山県内にある障害者施設を何カ所か訪れたほか、出身地の静岡県の施設にも足を運んだ。ご飯を一緒に食べたり介助食の手伝いをしたり、体を拭いたり、トイレに一緒に行ったり、散歩や遊びなど可能な限り体験させてもらった。「少しでも体験したことで、撮影現場にスムーズに入っていけた。事前に訪問し、意見を聞き、体験させてもらって本当に良かった」と語り、演じる上でのヒントを数多くもらったようだ。
社会的なテーマの作品に関心
磯村さんはこれまでにも「PLAN 75」や「波紋」「渇水」など社会的な背景が濃い作品への出演が目立つ。本作はまさにそのど真ん中といえる作品。磯村さん自身は出演作の傾向をどう見ているのか。「タイミングでそうした作品のお話をいただいていることもあるが、自分自身も日本や未来、今置かれている状況が気になるし不安もある。そういうものを届けたいというか、僕には映画しかないし、そこで表現するしかない」。さらに続ける。「映画を見るのもエンタメも好きだが、グッと心に残ったり、考えさせられたりする作品が好き」。例えば、と尋ねると「ラース・フォン・トリアーの映画とか好き。違う角度の行き過ぎた感はあるけど。伝えたいものが芯にあって余白が多かったり、社会的テーマを扱ったりする作品が以前から好きだ」
本作の出演も自分としては「当初から自分としてはやりたかったが、周囲から結論は慎重にすべきだという意見が多かった。河村光庸エグゼクティブプロデューサーや石井監督とお会いして不安や気になるところをお話しして最終的に決めた」という。今後に関しても「何か一つ抱えている役、ほかの人はなかなかやらないような役、キャラクターを演じたい」。今回の役しかり。「自分の許容範囲で演じるのはつまらない。たとえ失敗しても怖い所を飛び越えてチャレンジしたい」

役者デビューから10年近くがたつが、役者としての向き合い方も変化した。「最初の頃は考えて考えて作って作って現場に行くのが良し、としていたが、いろいろな作品や監督さんたちと出会い、それを捨てていくことの勇気とそれによって生まれる芝居の良さみたいなものを知るようになった」。肩の力が少しずつ抜けながら現場に入れるようになってきたかな、とほほ笑む。「現場で起きていることが全て。いくら作っても相手がいて、場所がある。相手に乗っかっていくのが芝居の面白さ。そこにある生(なま)を大事にしたい」と話した。
本日公開。