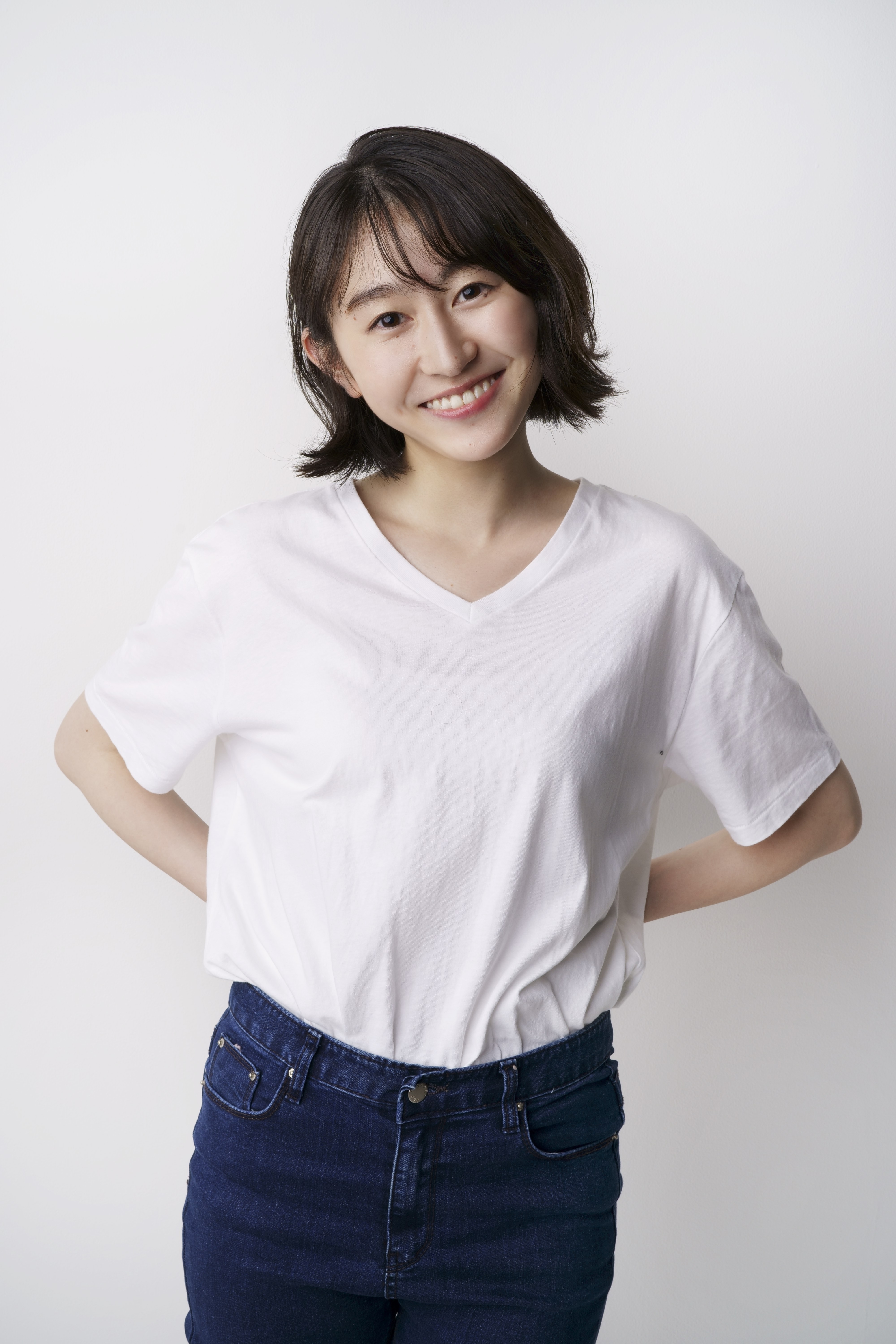ひとシネマには多くのZ世代のライターが映画コラムを寄稿しています。その生き生きした文章が多くの方々に好評を得ています。そんな皆さんの腕をもっともっと上げてもらうため、元キネマ旬報編集長の関口裕子さんが時に優しく、時に厳しくアドバイスをするコーナーです。
©映画「ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい」制作委員会
2023.8.12
映画の作り手と、映画の書き手。その、ひとつのコラボレーションの形! 大学生ライターが書いた「ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい」のコラムを元キネ旬編集長が評価する
大学生のひとシネマライター青山波月さんが書いた映画コラムを読んで、元キネマ旬報編集長・関口裕子さんがこうアドバイスをしました(コラムはアドバイスの後にあります)。
書きっぷりもしたたか、かつ見事。
ものごとを伝えるとき、それについて単刀直入に語るのが伝わりやすいのか? はたまた相手の理解しやすいことに置き換えて語るのが分かりやすいのか? やり方はさまざまにある。
青山さんのコラムはたぶん後者だろう。一見、自分の考えを語っているように感じるが、実際は読む同世代の人々に、なるべく興味を持ってもらうべく共感部分を作ろうと、話のポイントを作っている。
青山さんが大好きだと語る、白城さんというキャラクターの説明に文字数を割いているのもそのためだろう。「ぬいサー」の部員たちにも、白城さんの所属する陽キャサークルの人々にも、自分を投影しづらいと感じる人々にとって、白城さんは一番理解しやすいキャラクターだと思う。その白城さんがなにを考え、なにを恐れ、それらをどう対処しようとしているのかをつまびらかにすることで、観客予備軍にとってこの映画はグッと身近なものとなり、映画にアクセスしようとするきっかけになるのではないか。
白城さんを〝したたか〟と書いているが、青山さんの書きっぷりもしたたか、かつ見事。
同時に、「ぬいサー」の部員たちを、一見〝弱い人々〟のように描き、その見せかけに引っ掛かり、自分を強い人間だと勘違いする人々をもあぶり出すように仕掛けた金子由里奈監督も、かなりしたたかなクリエイターなのだと思う。
映画の作り手と、映画の書き手。その、ひとつのコラボレーションの形としてとても興味深いものとなっている。
青山さんのコラムはこちら
やさしいって危なっかしい。やさしいのは善いことだが、その人にとってやさしくあることは良いことなのか。「やさしい」について考えさせられる映画「ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい」
それぞれ悩みを持つ学生と「ぬいサー」で出会い
物語は、大学に入学した男子学生・七森が、ぬいぐるみとお話しするサークル「ぬいぐるみサークル」(通称ぬいサー)と出会うところから始まる。”大学生ノリ”や”恋愛”というものがいまいち分からない七森は、同じようにそれぞれ悩みを持つ学生と「ぬいサー」で出会い、次第にこのサークルが彼の居場所となる。自分の悩みやたわいもない話をぬいぐるみに聞いてもらうことで、彼らは誰も傷つけずに心の平穏を保っているのだ。
サークルの部員は、それぞれ思い思いのことをぬいぐるみに語りかける。世界のどこかで起こっている事件や戦争に悔しさや、自分が何もできないことへの罪悪の念を持つ鱈山。自分のセクシュアリティーについて他者から言及された言葉を引きずってしまう西村。自分が女性であるが故に、社会で感じる生きづらさ・怖さにおびえる麦戸。
誰のことも傷つけない一種の自己保身
自分が人とは違うことを誰かに話したら笑われるんじゃないか、誰かを傷つけてしまうのではないか。そんな中、彼らはぬいぐるみに囲まれた部室の中でぬいぐるみと対話することを選んだ。
情報がそこら中にあふれている現代。知りたくなかったことや、聞きたくなかった言葉も不可抗力で流れてくる。日々を生きているだけでも、私たちの精神は消費され、搾取されていく。だから、匿名性のあるネットで日々の鬱憤を憂さ晴らしして、また誰かを傷つけて・・・・・・その連鎖なのだ。
その点、「ぬいサー」の活動は消費されていく自分自身を守りながら、誰のことも傷つけない一種の自己保身だと私は思った。いうならば現実逃避。彼らはやさしい。やさしすぎて、世界のいろいろな事象が淘汰(とうた)されずに彼らの心の内側へ直に入り込んでしまうから、彼らはぬいぐるみというフィルターを利用する。
七森は劇中で何度か「話さないと相手のことにも自分のことにも気付けない」と言っている。たしかに、心の内にたまった抽象的な感情を言語化することで、自分の思考の輪郭がくっきりすることがある。ただ、あることをきっかけに話すことに注力し過ぎてしまった麦戸は、世の中の怖さや自分の弱さに気付いて不登校になってしまった。ここまで観客が見ていた「やさしさ」が、これを皮切りに形を変えてく。
彼女は世界を直視できる人
私はこの映画の中で大好きなキャラクターがいる。七森と同期で「ぬいサー」に入部した、白城という女学生。彼女の存在が、前半とはまた違った視点で「ぬいサー」を見せてくる。白城は他の部員とは違い、大学ノリ存分の陽キャサークルにも所属していて、彼氏を途絶えさせないような子だ。「ぬいサー」の活動中もぬいぐるみに話しかけることはなく、静かに本を読んでいる。
それでも白城が「ぬいサー」に居続ける理由は、「ぬいサー」が安心できる場所だからと語っている。セクハラざんまいのサークルとか、まるで社会の縮図のような大学生活に白城は順応して過ごしている。これから目の当たりにする厳しい社会の中で打たれ強くいるために。だから白城にとって、やさしい部員が集まる「ぬいサー」は避難所のような存在だった。
白城がぬいぐるみと話さないのは、それが彼女にとっての保身だからなのかなと思ったりした。社会や自分自身の奥にある、恐怖や弱さに気づかないように、自分の心に壁を作っている。「ぬいサー」の部員が、ネガティブな感情を淘汰できずに心の内側へ直に入り込ませてしまう人間なら、白城はいろいろなことを諦めているから落ち込みもしないような人間。
白城は、「ぬいサー」は「落ち込みたいまま落ち込める人が集まる場所」と言うが、だからといって「ぬいサー」の存在を否定もせずに寄り添っている姿勢が私は大好きなのだ。したたかかな人だと思った。
「ぬいサー」の部員が集まったこの映画のポスターは、みんな手に抱えているぬいぐるみを見つめている。しかし、白城だけは真っすぐにこちらを見据えている。そのポスターが、あまりにも彼女のキャラクターを表していて、「ああ、彼女は世界を直視できる人なんだ」と感じる。
今日も打たれ強く生きていく
と、ここまで私がどれだけ白城というキャラクターが好きか語ったが、実際のところ白城はやさしくないと思う。彼女は、自分が女性であるが故に、この男社会の中で理不尽な思いをしても何の怒りも湧かない。何の解決策も考えない。自分一人が落ち込み、反発したところで10年後も何も変わらないと思っているから、彼女は社会を諦めている。自分と関係ない事件にも心を痛めてしまう「ぬいサー」の部員とは真反対だ。
私はそんな白城の姿を見て、とてつもなく悲しかった。生きづらい社会に心を痛める「ぬいサー」部員の姿を見て、惨めになった。
やさしくありたいのに、ただそれだけなのに、なんでこんなに苦しまなきゃいけないのか。それって私たちのせいなのかな?やさしくいたいのに、やさしくいれないし、自分が信じてきたやさしさを疑ってしまうし、そういうのは実は社会のせいだったりするし。
白城みたいにしたたかでありたいけど、「ぬいサー」の部員みたいにやさしくありたい。それって絶対共存できないわけでないと思う。すっっっごく難しいことだけど、社会の理不尽を諦めないことも、自分にも人にもやさしくあることも、どっちも善いことであると信じて、今日も打たれ強く生きていく。